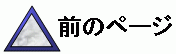高校2年になり学ぶ「極限」は、微分の計算をする上で必要になった計算技術です。
そのため、微分の計算を先にして、計算に困ったときに「極限」を学ぶという勉強スタイルでも良いと考えます。
そういう計算の役に立つように、頭を整理することが、極限を学ぶということです。
高校2年の微分積分の勉強のためには、「やさしく学べる微分積分」(石村園子)を読むと、内容がわかり易くて良いと思います。その4ページには、ε-δ論法を使わないで、極限値を簡単に定義しています。
高校生は、極限を学習する初めには、数列の極限を学ぶと思います。数列の極限を理解するために頼れる証明が済んでいる定理はなるべく多く用意して考えの支えに使うのが良いと思います。推薦できる高校数学の参考書:「生き抜くための高校数学」(芳沢光雄)の「数列の極限」は、その入門用のいくつかの定理が書いてあるので参考になると思います。
それを見た後で、ここをクリックした先の、数列の極限を詳しく書いてあるサイトの情報を参考にして、
その後に、数列の極限に係る多くの定理の情報を得るため、ここをクリックした先のサイトに数列の極限に係る定理の情報が多いので参考にしたら良いと思います。
高校3年になって本格的に微分積分を学びたくなった学生は、学生が微分積分を無駄なく学べるよう工夫がこらされている本:小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」を読むと、微分積分が無駄なく勉強できて良いと思います。その22ページに数列の極限値の定義が書いてあり、76ページに、ε-δ論法を使った極限値の定義が書いてあります。
ただし、数列の極限値についての参考書は、高校生は、先ず、推薦できる高校数学の参考書:「生き抜くための高校数学」(芳沢光雄)の「数列の極限」に関する説明を読むのが良いと考えます。それを理解した後で、小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」の22ページの数列の極限値の説明を読むようにした方が良いと思います。
関数の極限の定義は:
(1)第1の定義の極限:
開放された区間(a<x<b)の関数f(x)でxの右側極限と左側極限が一致する場合に極限があるものとする極限の定義。
(2)第2の定義の極限:
閉区間( a≦x≦b)の関数f(x)の、x=aとx=bとの区間の端点では、片側極限があるだけで、極限があるものとする極限の定義。
との2通りの定義があるので要注意です。
「区間」という数学用語は、実数の集合として定義されている用語である事に注意が必要です。
a≦x≦bを満足するxの区間という表現は、a≦x≦bの範囲内の全ての実数xという意味です。
-∞<x<∞という区間もあります。
区間はxの値の範囲を限定するためのa≦x≦bという式とは意味が異なることに注意する必要があります。
(A)「0≦x≦2の区間の変数xで定義された関数f(x)がその区間の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という文では、
f(x)は、0≦x≦2の区間で1つながりに連続した関数f(x)として定義されます。
一方で、
(B)「変数xの0≦x≦2の範囲内の値で関数f(x)が定義されていて、その関数f(x)が定義域の各点で連続であるとき,f(x)は誤解された連続関数である」という文では、f(x)は、例えば、
0<x<1で f(x)=0, この定義域内の各点で連続。
1<x<2で f(x)=1, この定義域内の各点で連続。
結局、0≦x≦2の範囲内の全ての定義域の各点で連続な誤解された連続関数f(x)として定義されます。
この例の様に、「区間」という用語は変数xの集合をあらわす用語であって、変数xの範囲をあらわす用語では無いことに注意する必要があります。
区間a≦x≦bが命題の中に記載されている場合は、その範囲内の全ての実数xについて命題を検討する必要があります。被積分関数f(x)が定義されていない変数xの点があっても、その点も、その命題が検討されるべき点の1つです。
《命題を検討すべき優先順位》
(1)関数f(x)を収める区間:
a≦x≦b(あるいはa<x<b)内の全ての実数x。
(2)その区間内の座標xにおける点。
(3)その区間内で関数f(x)が定義されている(f(x)の値が存在する)変数xの範囲(xの定義域):
a<x<(b-(a+b)/2) という範囲を定義域とする事や、
その範囲内の有理数のxのみを定義域とする事。
です。
区間について考えるという事は、その区間内の全ての実数の座標xの点を考え、その座標xでf(x)が定義されていない場合でも、その座標xについて考えるという事を意味します。
区間を使って考える場合は、例えば、ある区間内の全ての実数の点のうち、関数f(x)が定義されず関数f(x)が連続で無い(数直線上の)点xについては、「区間内のその点xでf(x)が定義されず関数f(x)がその点xで連続していない」というふうに考えます。xの区間とは、そのようにして、関数の定義域よりも優先して考えるxの数直線上の、実数が隙間なく充填されている範囲の事です。
----------区間の定義終わり-------------
【直感的極限値】
関数f(x) において, x をx0 に限りなく近づけていくとき,
f(x) がある値C に限りなく近づくならば,値Cをx がx0 に近づくときのf(x) の極限値といい,
で表わします.
さて,ここで限りなく近づくというのはどういうことでしょうか.
x がx0 に限りなく近づくとは,
絶対値|x−x0| を限りなく小さくできるということと同じだと考えてもよいでしょう.
同様に, f(x) が値Cに限りなく近づくということも
|f(x) − C| を限りなく小さくできることだと考えてもよいでしょう.
そこで,限りなく小さくできるということで考えてみると,以下の様に考えることができます。
《ε-δ論法(その1)》
(1)
どんな小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,|f(x) − C| をそれよりも小さくできるならば,
つまり、変数xの値がx0に近い全てのxの値のどれであっても漏らさず、ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値)に関して、
|f(x) − C| をεよりも小さくできるならば,
(2)
関数値f(x)の値のバラツキを漏らさず限りなく|f(x) − C| を小さくできるといえるのではないでしょうか.
この考え方が数学でいうところの限りなく小さいということなのです.
これを用いて関数の極限をもう一度定義します.
この定義はδ − ε 論法と呼ばれる証明法のもとになっていますが,難しく感じる人は,直感的極限値で十分です.
(注意)
ただし、直感的極限値で考える場合でも、変数xの値がx0に近いどの実数にした場合でも、
(条件1)
f(x)が(無限大では無い)ある値Cに近づく事。
(条件2)
そして、x0に近いどの実数に対してもf(x)の値が定義されていなければならないという事が、
極限が存在するための条件であると認識しておいてください。
(注意すべき点)
x=x0での関数f(x)の極限を求める場合、変数xの値がx≠x0となる値x0の近傍の範囲内の全ての実数ですきま無く関数値f(x)が定義されている関数f(x)についてのみ、極限が存在し得るものとして極限が定義されています。
【事例(ε-δ論法を先行して使う)】
以下の例の様に関数値f(x)が区間で定義されていない場合は、極限があるとは定義しません。
x=0,2,4だけで定義された関数f(x)の例:
f(0)=10,
f(2)=11,
f(4)=12,
この関数f(x)は、
どんなに小さい正の値εに対しても、
正の値δ=1を使ってxの範囲(区間では無い)を、
1.5− δ<x<1.5 +δ
に限定すれば、
その範囲内のf(x)の定義域のxの値は、x=2のみになる。
その全てのxの値(x=2だけですが)に対して、
-ε< (f(x)-11)<ε
が成り立つようにできます。 ε=1/10000という小さなεの場合でも上の式が成り立ちます。対象となるxはx=2しか無いからです。
しかし、そうであっても、f(x)はx=1.5で極限があるとは言えません。
極限がある場合は、区間
1.5− δ<x<1.5 +δ
内の全て実数に対して、f(x)の値が存在する事を要請しているが、関数f(x)はその条件を満足しないからです。
【極限が存在しないもう1つの例】
関数f(x)が、xが有理数の場合は
f(x)=x
であり、
xが無理数の場合は、
f(x)=100
とする関数がx=0での極限値を持つかどうかを考えます。
【解答】
自然数mで表す
x=1/m
を限りなく0に近づけて行くとき、
f(x)が限りなく0に近づきます。
しかし、
限りなく小さな値の無理数xに対して、
f(x)=100
になり、
その限りなく小さな値の無理数では、
f(x)は0に近づかないので、
f(x)は、
x→0の場合に、 f(x)→0となるとは言えません。
よって、この関数f(x)には、 x=0での極限値がありません。
(解答おわり)
(極限を考える場合の根本的な注意点)
極限を、x0に近いどの実数に対してもf(x)の値が定義されていなければならない事は、極限の定義の姉妹にあたる関数f(x)の連続性の定義が、すなわち、変数xの値x0における関数の連続性の定義が、x0に近いどの実数に対しても関数f(x)の値が定義されていなければならない事と対応しています。
【ε-δ論法による極限の定義(その1)】
ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値)に関して、
任意の正の実数ε に対して,
0 < |x − x0| < δ となる全ての実数xに対して,
(すなわち、x ≠ x0 であるxで、上式の条件を満たす全ての実数xについて)
|f(x) − C| < ε が成り立つように
正の実数δ が選べるならば,
(すなわち、その範囲の全ての実数xに対して、必ずf(x)が定義されていて、かつ、そのf(x)に関して上の式が成り立っているならば、)
である。
----極限の定義おわり---------
ここで、極限を定義するε-δ論法(その1)が出て来ましたが、ε-δ論法というものは、εとδを使って極限を表現する手段であって、ε-δ論法を使った極限の定義は、上の形の表現に限られません。
後で説明する、区間の端では、片側極限について、上の表現とは形を変えた別のε-δ論法(その2)によって片側極限が定義されます。
-----(極限の定義を言い換えて定義を理解する)----
大学1年生が、初めてこの極限の定義を学んだとき、定義の意味が分からず、微分積分学が分からなくなり脱落する大学1年生が多いらしい。
この定義を理解するには、想像力を膨らませて、この定義を、以下の様に噛み砕いて自分の言葉で言い換えると、この定義の意味が理解でき、定義がすんなり覚えられるようになると思います。
先ず、以下の図のようなメチャメチャな関数f(x)で、ただ1つの点のx0=0の点で極限を調べる事をイメージしましょう。x0=0の点以外では関数f(x)が連続でも無いというメチャメチャな関数を考えます。
上図の様にメチャメチャな関数で、x=x0の近くの関数値は、任意のバラバラな数値で考えても良い関数を考えます。そのため、順次に取り出す関数値を、単なる数列の数値の順列と考えるのと同じになります。そして、数列の極限を考えるのと同じように関数の極限を考える事ができます。
(1)
どんなに小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,
充分小さい正の微小量δを選べば、
ーδ<x-x0< 0 及び、 0<x-x0<δ
を満足するx0に近い、x0では無い全ての実数値のxを漏らさず調べた関数値f(x)が、
ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値:この値は複素数であっても良い)に関して、
全て、
|f(x) − C| < ε
を満足するということが、
関数f(x)にx0の極限値が存在するという事である。
その値Cを点x0での関数f(x)の極限値と定義します。
(1-1)
すなわち、関数f(x)の値が存在する変数xが、
x0に近いがx0では無い、x0に近い全ての実数xの範囲が、
言い換えると、
(A)充分小さい正の微小量δによる、
0 < |x − x0| < δ
となる範囲の全ての実数が関数の変数xの定義域に含まれている。
(B)また、上の式(満足させる目標をあらわす式):
|f(x) − C| < ε
を満足するある値C(εの値にかかわらず固定した値)が存在する。
ということが、
関数f(x)のx0の極限が存在するという事である。
(1-2)
極限の定義において、xをx0に限りなく近づけてf(x)を考える際に、x0の点を除外して考えることが極限の概念の本質的な特徴になっています。もし、x0の点を除外しないで”極限”の有無を調べることにすると、それは、関数の”連続性”の有無を調べることになります。極限の概念は、関数が連続で無い場合も視野に入れた関数の特徴の把握のために、x0の点を除外して考えるという特徴を本質的に持っています。
すなわち、関数f(x)の極限を求める点x0で関数f(x)が連続で無くても極限値が存在し得るのです。
(2)
ここで、x0から、実数値δの範囲内でずれる、x0では無い全ての実数xについてf(x)を考えなければならない。
この定義における「全ての実数x」の意味は、他の制限、例えば関数の変数の定義域を有理数だけに定めて定義域外の無理数の変数に対する関数値を考え無い事にしていても、その制限に制約されずに定義される全ての実数xを意味します。
(関数f(x)の変数xの定義域に制約されない全ての実数xを考えるということです)
(3)
その全てのf(x)の値(その値は複素数であっても良い)のバラツキの誤差を求める。
その誤差<εとするεでバラツキの範囲を定める。
(4)
(4-A)xの値のx0からずれる範囲の値δを十分小さくすれば、
その範囲内の全ての実数値のx(ただし、値x0は除外)によるf(x)の値のバラツキが小さくなり、
そのバラツキの範囲の値 ε は、
いくらでも小さな値εが得られる、
という条件が満足されるならば;
(4-B)また、そのどの実数値x(ただし、x≠x0)についても、
-ε< |f(x)-C|<ε
となる値C (この値は複素数であっても良い)が、どのように小さなεの値についても、
変わらない確固とした値で存在するならば;
その関数の値の極限が存在し、
その確固とした値C が極限値である。
----(定義の言い換えおわり)-----------
(疑問に思う点)
そのある値Cをどの様にして見つけたら良いのだろうかという疑問がわくと思います。
ε-δ論法によって極限値を定義しても、ある値Cが分からなければ、極限値の存在が確かめようが無いのではないか。
ある値Cを仮定して、定義にあてはめても、ある程度小さいεまでは確かめられても、それ以降は、定義通りにならず、その値Cは、結局は極限値では無い事がわかるという事になるのではないか。
その極限値Cを確かめる試行錯誤を無限に繰り返せと言うのかといった腹立ちを感じるのではないでしょうか。
その疑問に対しては、以下の様に考えたら良いと考えます。
極限値Cを確かめるには、単に、xをx0に近づけて関数値f(x)を求めて行くだけで良いのではないか。
極限が有るか無いかの問題は、その方法で極限値を求める事ができる関数であるか、そうで無いかを判定できるだけで良いと考えます。
(A)先ず、その様にして求める事ができる極限値Cが存在する事が第1に必要な条件です。
(B)次に、その極限値Cが存在するとして、関数f(x)は、その極限値Cにどの様に近づいていかねばならないかの、関数の構造を知る事が第2に必要な条件と考えます。
極限が存在する関数が満足させるべき目標をあらわす式:
|f(x)-C|<ε,
を以下の様に変形して考えます。
-ε<(f(x)-C)<ε,
C-ε<f(x)<C+ε,
f(x)-ε<C<f(x)+ε,
この(満足させる目標をあらわす)式によって、ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値)が、関数値f(x)の誤差εの範囲で求められる事が、極限値Cが存在し得るという事です。
その誤差εは、xをx0に近づける事で小さくできれば、極限値Cが存在し得ると言えます。
すなわち、
0 < |x − x0| < δ
となる誤差δの範囲内の全てのxについて、
上の式が成り立ち、誤差δを小さくすればいくらでも誤差εを小さくできれば極限値Cが存在すると言えます。
関数の構造を調べるために全てのxについてのf(x)を考えるのが大変なので、以下の様に考えて関数の構造を調べます。
全てのf(x)のうち、
f(x)の上限値を求めf2とする。
f(x)の下限値を求めf1とする。
(端点が開放された区間では、開放された端点の近くで関数f(x)が上限値f2に限りなく近づくが決してf2になる事が無い事が起き得る事に注意する)
全てのf(x)について、
f1≦f(x)≦f2です。
そうすれば、全てのf(x)について満足させる目標が:
f2 -ε<C<f1+ε,
という関係だけを満足させる事を考えれば良い事になります。
(補足)
ここで、想像力を働かせて、一番突飛な例を想像しましょう。
例えば、誤差δを小さくすれば、f(x)のグラフの最大値 f2 がx0の左にあったり右にあったりし、x0の前後のxの順では、f1,f2の順になったり、f2,f1の順になったりする突飛な関数の事例を想像してイメージを膨らませましょう。
---補足おわり--------------
この(満足させる目標をあらわす)式
f2 -ε<C<f1+ε,
によって小さい値εの小ささの限界が決められます。
先ず、必須の条件に、
2ε>f2-f1
があります。
しかし、これだけでは、満足させるべき目標が達成できません。
そこで、
ε=(f2-f1)+(0+)
とすると、
f2 -ε<C<f1+ε,
は、
f1-(0+)<C<f2+(0+),
になり、また、以下の式にもなります。
f1≦C≦f2,
(極限値Cが存在する事を前提として考えて)この式は必ず成り立つ関係を表していると考えられますので、この式なら目標の式を満足させることができます。
(また、後で説明するように、この様に値Cのバラツキの範囲を定めるならば、数直線上の区間を考える場合、最小値f1と最大値f2を両端に持つ区間を、その区間の幅を無限に小さくしていくことができる関数の場合は、その幅を無限に小さくする各段階での値f1及び値f2とは独立した値の極限値Cが存在する事が証明できます。)
そのため、誤差εは、
ε=(f2-f1)+(0+)
に決めることができます。
これにより、このε-δ論法による極限の定義は、
以下の定義と等価だと分かりました。
【等価な極限の定義】
0 < |x − x0| < δ となる全ての実数xに対してf(x)の値があり,
(すなわち、x ≠ x0 であるxで、上式の条件を満たす全ての実数xについて、必ずf(x)が定義されていて)
(A)
そのxの範囲内のf(x)の下限値をf1とし上限値をf2とするときに、
f2-f1をいくらでも小さくするxの範囲を定める正の実数δ を選べることができるならば,
(B)
f1≦C≦f2
となる値Cで、f2-f1を小さくする各段階でのf1及びf2の値とは独立して存在する値Cを見つけて、その値Cを極限値と定義する。
そして、
と記述する。
----等価な極限の定義おわり-------
誤差εをどんどん小さくしていっても、
0 < |x − x0| < δ
となる範囲内の全てのxの関数f(x)の上限値f2と下限値f1が、
δを十分に小さくすることで、f1とf2の差が十分小さくなるなら、そのf1とf2の間に求める極限値Cが存在すると言えると考えます。
そのように、f1とf2の差をどんどん小さくしていくことができるならば、
xをx0に近づけて関数値f(x)を求めて行くだけで、
極限値Cが求められると言えると考えます。
(極限値Cの存在の証明)
なお、このようにxの範囲の幅のδを小さくしてxの範囲の領域の幅を無限に小さくし続けて、その範囲内の関数f(x)の下限値f1と上限値f2を求めて、Y=f(x)の区間で、f1とf2を両端に持つ区間を考え、そのY座標でのf1からf2までの区間の幅を無限に小さくし続けることができるなら、その場合に、そのY座標の、f1からf2までの区間が、1点の極限値Cに収束する事が証明できます(ここをクリックした先の定理18)。
このように、f1とf2の差≒ε がいくらでも小さくできる条件が成り立つならば、関数f(x)の値が極限値Cに近づいていき極限値Cが求められるので、これによって、極限値が存在する条件が正しく表わされている様に思います。
(注意)以下の様なメチャメチャな関数の場合:
xをx0の近傍の誤差δの範囲に近づけて、その範囲内の全ての関数値f(x)の上限値f2と下限値f1を調べるので、作業量はとても多い大変な作業が必要です。
ただし、その作業量の多さは、元のε-δ論法でも、xをx0の近傍の誤差δの範囲に近づけて全ての関数値f(x)で|f(x)-C|<ε を調べる作業量も同じ多さです。
極限値Cの定義は、最悪なメチャメチャな関数の極限値を求める場合を想定した場合の極限値の求め方をあらわしたものであって、現実的な素直な関数の極限値Cの求め方を表したものでは無かったのです。
素直な関数ならば、上限値f2と下限値f1を求めてから極限値Cを求める作業は比較的楽になると思います。
(注意)
ここで、極限を定義するε-δ論法(その1)が出て来ましたが、ε-δ論法というものは、εとδを使って極限を表現する手段であって、ε-δ論法を使った極限の定義は、上の形の表現に限られません。
後で説明する片側極限についても、上の表現とは形を変えた別のε-δ論法(その2)によって片側極限が定義されるのです。
(極限の定義の第1のポイント)
上のε-δ論法による極限の定義の第1のポイントは:
「f(x)の値のバラツキを表す正の数ε をどれだけ小さくしても,関数値f(x)を必ずそのバラツキ内に漏れなく入れることができるx0に近い実数xのバラツキの範囲を表す正の値δが必ず存在することである。
すなわち、その正の数εのバラツキ内に関数値を漏らさず入れる、x0に使い全ての実数xの範囲を
0 < |x − x0| < δ
とする正の数δ が必ず存在すると言うことである。
0 < |x − x0| < δ の条件を満足する全ての実数xに関してf(x)の全てにおいて、条件を満足するならば、
という説明が隠れて入っているので「全て」というキーワードを忘れないようにしましょう。
この極限の定義は、関数f(x)がx0の近くの全ての実数xに対して関数値が定義されている関数でなければならないという事を前提にしています。
関数f(x)が有理数のxに関して定義されていても、無理数のxに関して定義されていなければ、関数f(x)には極限が有りません(極限が定義できない)。
(極限の定義の第2のポイント)
上のε-δ論法による極限の定義の第2のポイントは、
x→X0を、
0 < |x − x0| < δ
(すなわち、x ≠ x0 の場合に)
と定義し、
一方で、
f(x)→Cを、
|f(x) − C| < ε
(すなわち、f(x) = Cの場合を含む)
と定義して
極限を定義していることです。
これにより極限の意味を明確にしていることです。
すなわち、
x→x0 (x≠x0となる場合のみ)と、
f(x)→C (f(x)=Cとなる場合も含む)は、
同じ「→」であらわしていても、
意味が異なっていることを明確にしています。
【問題1】
関数f(x)は、整数mと、0以外の整数qに関して、
有理数x=m/qの場合に、
f(x)=0
となる関数である。それ以外のxの場合にこの関数f(x)は値を持たない。
この関数f(x)は、
x→0における極限値を持つか?
【解答】
この関数f(x)の値を与える有理数x=m/qが何であっても、その有理数xの値より0に近い無理数yが必ず存在する。そして、その無理数yに対して値f(y)を持たない。
よって、この関数f(x)は、xを限りなく0に近くしても関数値が定まらず、極限値が存在しない。
(解答おわり)
《ε-δ論法(その2)》
また、以上で説明したε-δ論法(その1)による極限の定義によると、変数xの値が、x0から微小な値 δ 以内の誤差の全ての実数xの値に対してf(x)が定義されていなければ、x0で関数f(x)の極限値が存在しない。
そのため、関数f(x)の変数xの実数の定義域の境界x0 では、
x0から微小な値 δ 以内の実数の領域の半分が関数f(x)の定義域からはみ出して、定義域内に存在しないので、定義域の実数の境界x0 では関数f(x)に極限値が存在しないことになってしまいますが、以下の第2の定義(ε-δ論法(その2))の様に、閉区間の端点での極限値の定義を修正し、閉区間の端点で極限値がある、と定義します。
(第2の定義の極限の条件)
関数f(x)が、a≦x≦bで定義されている場合、
そういう閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の端点については、以下の条件を満足する左側極限値、または、右側極限値が存在すれば、その端点で極限があると定義されています。
(1)左側極限値
どんなに小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,
充分小さい正の微小量δを選べば、
ーδ<x-b< 0
を満足するbに近い全ての実数値のxが、
ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値)に関して、
|f(x) − C| < ε
を満足するということが、
関数f(x)のbの左側極限が存在するという事である。
その値C =f(b-)
とあらわす。
この極限を、
x → b− 0 またはx → b−
のとき、
f(x)→ f(b-)
であると表現する。
f(b-)が存在するならば、端点bで関数f(x)に極限値があると定義します。
(2)右側極限値
どんなに小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,
充分小さい正の微小量δを選べば、
0<x-a<δ
を満足するaに近い全ての実数値のxが、
ある値C(その値Cは、εの値によらない固定値)に関して、
|f(x) − C| < ε
を満足するということが、
関数f(x)のaの右側極限が存在するという事である。
その値C =f(a+)
とあらわす。
この極限を、
x → a+ 0 またはx → a+
のとき、
f(x)→ f(a+)
であると表現する。
f(a+)が存在するならば、端点aで関数f(x)に極限値があると定義します。
【等価な片側極限の定義】
上に記載した片側極限(のうちの1つ)を、以下の、等価な定義であらわすこともできます。
0<x-a<δとなる全ての実数xに対してf(x)の値があり,
(すなわち、x < aであるxで、上式の条件を満たす全ての実数xについて、必ずf(x)が定義されていて)
(A)
そのxの範囲内のf(x)の下限値をf1とし上限値をf2とするときに、
f2-f1をいくらでも小さくするxの範囲を定める正の実数δ を選べることができるならば,
(B)
f1≦C≦f2
となる値Cで、f2-f1を小さくする各段階でのf1及びf2の値とは独立して存在する値Cを見つけて、その値Cを極限値と定義する。
そして、
x → a+ 0 またはx → a+
のとき、
f(x)→ f(a+)=C
と記述する。
----等価な片側極限の定義おわり-------
(極限値が存在しない点が有限個ある関数)
以下の図の関数f(x)のグラフを考えます。
(その1)この関数は、xの定義域をー100から100までで考えると:
x=0の点での極限とx=2の点での極限が存在しません。
x<0で、x→0とすると、f(x)→0になり(左側極限値)
x>0で、x→0とすると、f(x)→1になります(右側極限値)
関数の定義される領域の端点以外の点で、左側極限値と右側極限値が一致しない場合は、極限値が存在しません。
(その2)この関数は、xの定義域を0から2までで考えると:極限の第2の定義を適用し:
閉区間 0≦x≦2
において、その端点x=0もx=2も、片側極限が存在するので、端点での極限が存在し、閉区間全体で極限が存在します。
(注意)上で説明した、その1とその2の関数は定義域が異なるので異なる関数です。
異なる関数ですので、その1とその2で、x=0及びx=2の極限の有無の判定が異なっても、問題ありません。
関数の極限値が存在しないもう1つの例として、以下の図の関数 Y=sin(1/x) は
x→0で
Yの極限値が存在しません。
(この関数Yは、x→0において、ー1から1まで振動し、安定しません)
(極限値が存在しない点が無限にある関数の例)
例えば、xが有理数の場合のf(x)の値とxが無理数の場合のf(x)の値が1以上異なるような関数には極限が存在しません。
どの位置においても関数の極限値が存在しない関数は、例えば下のグラフの関数のようになります。
上図のノコギリ関数g(x)を使って以下の関数を作ります。
この関数は、以下のx座標で極限が存在しない。
その他、
x=奇数/(整数×2)
の点では極限値が存在しない。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
【問題】
「下図の様に、線を曲げて上下に段差があるグラフを作る。
そのグラフの段差の間隔を、先のグラフの間隔より狭めて変形したグラフを作る。
この作業を無限に繰り返して段差の間隔を無限に狭めたグラフの関数f(x)を作ったら、そのグラフは段差の部分で連続か否か?」
(問題おわり)
という問題を問われたら、
「 いや、そうなったら、それは、もはや、その無限にグラフの段差を狭くしている点x=0で、グラフの極限が存在しなくなりグラフが不連続になります。」(事実はこの通りですが)
と即答できるでしょうか。
こういう問題に論理的に(数学的に)返答できるようにするため、極限を厳密に定義したのです。
【解答】
上図の様に、x=0でのグラフの段差を無限に狭くしたら、
(1)
どんな小さな正の数 εを比較の相手と選んでも,
|f(x) − 0| < ε
とできるような、x0に近い実数xの範囲が存在しない事が以下の様にして証明できます。
(2)
以下の式で定義する実数xの範囲δをいくら狭くしても、すなわち、
0 < |x − x0| < δ となるxの範囲をいくら狭くしても、
上のグラフの関数f(x)の段差が無限に狭くなって、
0 < |x − x0| < δ となる範囲内にグラフの段差が包含されてしまいます。
(3)
グラフの段差が、
0 < |x − x0| < δ となるxの範囲内に包含される結果、
その範囲内のxに、
|f(x) − 0| の大きさが段差の高さ(の半分)くらい大きいxの値があります。
それゆえ、そのxの値では、小さな正の数 εによって、
|f(x) − 0| < ε
とする事ができません。
そのため、x=0で極限が存在しません。 極限が存在しないので、極限を使って定義した連続性も無く、この関数はx=0で不連続になります。
(解答おわり)
リンク: