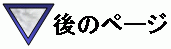ε-δ論法の論理式の意味
【問1】
数列 (a_n) の極限αを定義する式に関して:
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n>N)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (1)
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≧M)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (2)
(1) ⇔ (2)を証明せよ。
【証明開始】
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n>N)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (1)
⇔
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≦N)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (1b)
である。
また、
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≧M)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (2)
⇔
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n<M)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (2b)
である。
先ず、式(1b)を同値変形する。
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∀n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∩P2∩・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNが連立される。
そのため、
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≦N)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (1b)
という論理式は、以下の連立論理式を意味する。
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=1[(1≦N)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=2[(2≦N)]
・・・
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N[(N≦N)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+1[(N+1≦N)∪(|(a_n)−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+2[ |(a_n)−α|<ε]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+3[ |(a_n)−α|<ε]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+4[ |(a_n)−α|<ε]
・・・
という連立論理式全てが成り立つという意味である。
これは、以下の連立論理式と同値。
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+1[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+2[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+3[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+4[(|a_n−α|<ε)]
・・・
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∃n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∪P2∪・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNの和集合になる。
そのため、
上の連立論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, N=1, n=2[ |(a_2)−α|<ε]
∀ε>0, N=1, n=3[ |(a_3)−α|<ε]
∀ε>0, N=1, n=4[ |(a_4)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, N=2, n=3[(|(a_3)−α|<ε)]
∀ε>0, N=2, n=4[(|(a_4)−α|<ε)]
∀ε>0, N=2, n=5[(|(a_5)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, N=3, n=4[(|(a_4)−α|<ε)]
∀ε>0, N=3, n=5[(|(a_5)−α|<ε)]
∀ε>0, N=3, n=6[(|(a_6)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, N=100, n=101[(|(a_101)−α|<ε)]
∀ε>0, N=100, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, N=100, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, N=101, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, N=101, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, N=101, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
更に、この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, n=101[|(a_101)−α|<ε]
∀ε>0, n=102[|(a_102)−α|<ε]
∀ε>0, n=103[|(a_103)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
この連立論理式の和集合を、第1の論理式とする。
次に、式(2b)を同値変形する。
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∀n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∩P2∩・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNが連立される。
そのため、
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n<M)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (2b)
という論理式は、以下の連立論理式を意味する。
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=1[(1<M)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=2[(2<M)]
・・・
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M[(n<M)∪(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+1[(M+1<M)∪(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+2[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+3[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+4[(|a_n−α|<ε)]
・・・
という連立論理式全てが成り立つという意味である。
これは、以下の連立論理式と同値。
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+1[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+2[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+3[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+4[(|a_n−α|<ε)]
・・・
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∃n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∪P2∪・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNの和集合になる。
そのため、
上の連立論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, M=1, n=1[|(a_1)−α|<ε]
∀ε>0, M=1, n=2[|(a_2)−α|<ε]
∀ε>0, M=1, n=3[|(a_3)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, M=2, n=2[|(a_2)−α|<ε]
∀ε>0, M=2, n=3[|(a_3)−α|<ε]
∀ε>0, M=2, n=4[|(a_4)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, M=3, n=3[|(a_3)−α|<ε]
∀ε>0, M=3, n=4[|(a_4)−α|<ε]
∀ε>0, M=3, n=5[|(a_5)−α|<ε]
・・・」
∪
・・・
この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, M=101, n=101[(|(a_101)−α|<ε)]
∀ε>0, M=101, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, M=101, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, M=102, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, M=102, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, M=102, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
更に、この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, n=101[(|(a_101)−α|<ε)]
∀ε>0, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
この連立論理式の和集合は、第1の論理式と同値である。
よって、
(1) ⇔ (2)が証明された。
(証明おわり)
リンク:
19世紀の解析学における「厳密化革命」とは何か
ε-δ論法の誕生
【ε論法】関数の連続性とδのテクニック
連続関数の定義
高校数学の目次
新型コロナウイルス感染対策
数列 (a_n) の極限αを定義する式に関して:
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n>N)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (1)
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≧M)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (2)
(1) ⇔ (2)を証明せよ。
【証明開始】
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n>N)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (1)
⇔
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≦N)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (1b)
である。
また、
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≧M)⇒(|(a_n)−α|<ε)]… (2)
⇔
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n<M)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (2b)
である。
先ず、式(1b)を同値変形する。
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∀n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∩P2∩・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNが連立される。
そのため、
∀ε>0, ∃N∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n≦N)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (1b)
という論理式は、以下の連立論理式を意味する。
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=1[(1≦N)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=2[(2≦N)]
・・・
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N[(N≦N)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+1[(N+1≦N)∪(|(a_n)−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+2[ |(a_n)−α|<ε]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+3[ |(a_n)−α|<ε]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+4[ |(a_n)−α|<ε]
・・・
という連立論理式全てが成り立つという意味である。
これは、以下の連立論理式と同値。
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+1[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+2[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+3[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃N∈ℕ, n=N+4[(|a_n−α|<ε)]
・・・
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∃n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∪P2∪・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNの和集合になる。
そのため、
上の連立論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, N=1, n=2[ |(a_2)−α|<ε]
∀ε>0, N=1, n=3[ |(a_3)−α|<ε]
∀ε>0, N=1, n=4[ |(a_4)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, N=2, n=3[(|(a_3)−α|<ε)]
∀ε>0, N=2, n=4[(|(a_4)−α|<ε)]
∀ε>0, N=2, n=5[(|(a_5)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, N=3, n=4[(|(a_4)−α|<ε)]
∀ε>0, N=3, n=5[(|(a_5)−α|<ε)]
∀ε>0, N=3, n=6[(|(a_6)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, N=100, n=101[(|(a_101)−α|<ε)]
∀ε>0, N=100, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, N=100, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, N=101, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, N=101, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, N=101, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
更に、この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, n=101[|(a_101)−α|<ε]
∀ε>0, n=102[|(a_102)−α|<ε]
∀ε>0, n=103[|(a_103)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
この連立論理式の和集合を、第1の論理式とする。
次に、式(2b)を同値変形する。
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∀n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∩P2∩・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNが連立される。
そのため、
∀ε>0, ∃M∈ℕ, ∀n∈ℕ[(n<M)∪(|(a_n)−α|<ε)]… (2b)
という論理式は、以下の連立論理式を意味する。
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=1[(1<M)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=2[(2<M)]
・・・
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M[(n<M)∪(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+1[(M+1<M)∪(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+2[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+3[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+4[(|a_n−α|<ε)]
・・・
という連立論理式全てが成り立つという意味である。
これは、以下の連立論理式と同値。
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+1[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+2[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+3[(|a_n−α|<ε)]
∀ε>0, ∃M∈ℕ, n=M+4[(|a_n−α|<ε)]
・・・
任意のN個の命題P1,P2,・・・PNに対して、
(∃n∊{1,2,・・・N},{Pn})⇔(P1∪P2∪・・・PN)
が成り立つ。すなわち、命題P1から命題PNの和集合になる。
そのため、
上の連立論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, M=1, n=1[|(a_1)−α|<ε]
∀ε>0, M=1, n=2[|(a_2)−α|<ε]
∀ε>0, M=1, n=3[|(a_3)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, M=2, n=2[|(a_2)−α|<ε]
∀ε>0, M=2, n=3[|(a_3)−α|<ε]
∀ε>0, M=2, n=4[|(a_4)−α|<ε]
・・・」
∪
「∀ε>0, M=3, n=3[|(a_3)−α|<ε]
∀ε>0, M=3, n=4[|(a_4)−α|<ε]
∀ε>0, M=3, n=5[|(a_5)−α|<ε]
・・・」
∪
・・・
この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, M=101, n=101[(|(a_101)−α|<ε)]
∀ε>0, M=101, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, M=101, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, M=102, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, M=102, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, M=102, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
更に、この論理式は、以下の連立論理式の和集合と同値。
「∀ε>0, n=101[(|(a_101)−α|<ε)]
∀ε>0, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
・・・」
∪
「∀ε>0, n=102[(|(a_102)−α|<ε)]
∀ε>0, n=103[(|(a_103)−α|<ε)]
∀ε>0, n=104[(|(a_104)−α|<ε)]
・・・」
∪
・・・
この連立論理式の和集合は、第1の論理式と同値である。
よって、
(1) ⇔ (2)が証明された。
(証明おわり)
リンク:
19世紀の解析学における「厳密化革命」とは何か
ε-δ論法の誕生
【ε論法】関数の連続性とδのテクニック
連続関数の定義
高校数学の目次
新型コロナウイルス感染対策
微分積分の礎の関数の連続性と現代数学の位相空間論
やさしい微分積分
〔前のページ〕〔次のページ〕〔微分積分の目次〕
《実数とは》
例えば、以下の図の規則によってx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が有理数の中には無い。しかし、そのように限りなく近づく先の数が存在すると考えた。その数を実数と呼ぶ。

このように、「限りなく近づける」操作(極限の操作)が、数の概念を拡張することを要請し、そうして拡張された新たな数が実数であった。この拡張された数である実数から成るとされる数直線には数の連続性があるとされた。このように極限の操作によって数の概念が実数にまで拡張され、それが数の連続性と微分積分の礎になった。
1970年代の高校数学の参考書「大道を行く数学(解析編)」から、以下の知識が得られる。
[連続の定義]

のとき、関数y=f(x)は x=a で連続であるという。
また、f(x) がある区間のすべてのxで連続のとき、その区間で連続であるという。
しかし、(10)式は単なる定義であって、それだけではいろいろな問題を考察するのに不十分であろう。連続について知るには、裏返して不連続である場合を知るのが早道である。不連続の場合は、(10)式が成り立たない場合だから、次の4通りが考えられる。

以下、これらについて、例をもって説明しよう。




例2.9 [x] はxを越えない最大の整数とする.




どちらも存在しない.このことについては多くを語る必要もないであろう.


例2.10 無限個の項の和が存在するとして定義された関数

は、x≠0のとき、次のような工夫をすると簡単な形にまとめられる.


この関数のグラフは図2.10 の通りである.

不連続な場合、f(x) のグラフは不連続なxにおいて切れていて、連結していない.このことは逆に連続なときは、グラフはxにおいて切れ目のない線になっている.また(10)式は、
x-aが無限小のとき、f(x)-f(a) が無限小
ということである.したがってf(x) が連続なところでは
xの微小変化に対応し、f(x) が微小変化する
そして、このような関数を連続関数というといいかえても良い.
(参考)藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」によると、「f(x)がx=ξで連続でない場合に、x=ξ(という変数xの数直線上の点)をf(x)の不連続点という。」と定義されている。
〔定義の役割〕
連続関数とは、第1の条件として、関数の定義域が連結していること、第2の条件として、定義域の点毎に関数f(x) の値域が連結していること。その2つの条件が成り立ちグラフが1つながりに連結している関数f(x) をどのように表すかが連続関数の定義の役割である。
(注意1)関数f(x) の点とは、関数をあらわすグラフ上の点ではなく、変数xの数直線上の点である。
(注意2)
「不連続点」の定義は、現代数学の位相空間論の定義では、その不連続なxの値で関数値f(x) が定義されている場合のみに「不連続点」という言葉を使っている。つまり、古典的(基礎的)な微分積分学における上の例2.8 のx=1の点のように関数値f(1) が定義されていない点は、位相空間論の定義では不連続点とは呼んでいない。(しかし、後に説明するように、これは誤りである)
〔古典的(基礎的)微分積分学〕
古典的(基礎的)微分積分学では、関数の連続性の定義は、〔定義の役割〕における2つの条件が満足されるように定義する。先ず、第1の条件を満足するために、変数xの点aの近傍で実数が連結する区間内(連結する全ての実数)での極限を用いる。次に、第2の条件を満足するように、式(10)によって関数f(x) の連続性を定義している。
「区間で定義された関数f(x)が、その区間のすべてのxの値で古典的(基礎的)な連続性があるとき、f(x)は古典的(基礎的)な微分積分学で定義された連続関数である」
そして、実数上のx=aの点で関数f(x) の連続性の条件が満たされない場合を、その(実数上の)点aを、不連続点と呼んでいる。
実数上のx=aの点は、関数f(x) の連続な点であるか、関数f(x) の不連続点(当ブログでは「連続でない点」と呼ぶ)かの2つの場合のどちらかである。
すなわち、あるxの点が不連続である条件は、そのxの点が連続でないことである。
古典的(基礎的)微分積分学は、実数全体の数の集合に基づいて解析することで、関数の性質の解析の見通しを良くしています。
〔位相空間論によって再構築した微分積分学〕
(微分積分を学び始めた高校生はこれ以降は読まないで良い)
一方で、位相空間論によって再構築した微分積分学は、位相空間の数の集合(限定された数)のみに基づいて関数の性質を解析するので、関数の解析の見通しが極めて悪い。手探りで関数を解析するので間違え易いという特徴があります。
位相空間論によって再構築した微分積分学では、関数の連続性の定義は、〔定義の役割〕における2つの条件のうちの第2の条件のみを満足する定義である。
すなわち、例えば位相空間の数の集合を有理数のみ(数の集合が連結しない)に定めても良く、関数f(x) の定義域はその数の集合の部分集合に限られる。そのようにして定義域の連結性が要求されていない。
そして、式(10) により値域の連続性を定義する。

すなわち、独立変数x及び点aが、位相空間の数の集合(例えば有理数)に属する場合のみを考える。そして、関数f(x) の定義域は位相空間の数の集合の部分集合に限られ、点x及び点aは定義域内の点である。式(10) は、その点xが限りなく点a近づくときに、f(x) が限りなくf(a) に近づくという関係があることによって関数f(x) の値域の連続性を表している。
「関数 f(x) が、その関数f(x) の定義域のすべての x =aの値で位相空間論的な連続性があるとき、 f(x) は位相空間論で定義された連続関数である」
そして、例えば有理数の位相空間の数の集合に属するx=aの点で関数f(x) の連続性の条件が満たされない場合を、その点aを、不連続点と呼んでいる。
位相空間の数の集合(有理数)に属するx=aの点は、
①関数f(x) の定義域に属さない点aの不連続点であるか、
②定義域上の点aであって関数f(x) の連続な点であるか、
③定義域上の点aであって関数f(x) の不連続点であるか、
の3つの場合のどれかである。
(4つ目の場合として、例えば無理数のx=βの点などの、有理数の位相空間の数の集合に属さない点βについては、位相空間の数の集合に属さないので存在しない数とみなす。その点βについては言及しない)
位相空間論では、(3°の)関数f(x)=1/x において、点x=0は、関数f(x) の定義域内の点ではないが、位相空間の数の集合(有理数や実数)に属する点なので、不連続点である。
すなわち、あるxの点が不連続である条件は、
(1)先ず、そのxの点が位相空間の数の集合に属する点であること。
(2)次に、そのxの点が連続でないこととの、
2つの条件を満足する必要がある。
点x=0は、その2つの条件を満足するので不連続点である。
(点の種別の定義付けの心)
位相空間論での「不連続点」の厳密な定義は、定められた位相空間の数の集合だけで議論することである。その位相空間の数の集合に属するxの点は、関数f(x) の定義域に属するか、定義域に属さないかの何れかである。
位相空間論は、(1°)の、変数xの定義域に属さない「取除きうる不連続点a」については、その点aが位相空間の数の集合に属する場合は、関数f(x) の定義域の外の「境界点」とする。
その「境界点」は連続な点ではないので「不連続点」である。かくして、位相空間論では、定義域の外の境界点を「不連続点」と定義付ける。
しかしながら、有理数のみの位相空間においては、以下の図の関数のx=√2 の点は無理数であって、その位相空間の数の集合に属さない。

この場合は関数f(x) の有理数の「境界点」が存在しないので、有理数の位相空間の不連続点も存在しないことに注意すべきである。古典的(基礎的)微分積分学の視点(実数を数の集合とする位相空間)で見ると、この図の関数(厳密に言うと無理数でも定義された関数の場合)は、無理数の境界点で分割された3つの異なる連続関数から成ることがわかる。
(注意3)
位相空間論の説明において、位相空間の数の集合に属する点であって「不連続点」の資格がある点の一部の、数f(x) の定義域に属する点のみを「不連続点」と説明する誤りが流通している。(そういう誤りを基礎的微分積分学(高校数学)に混ぜないでほしい)。そういう誤りに巻き込まれないために、古典的(基礎的)な微分積分学が定義する「不連続点」や、(位相空間論においても)定義域を連結させない境界点の「不連続点」は、このブログでは、「連続でない点」と呼ぶことにして数学用語を明確にする。
(補足)
なお、位相空間論で点の連続性を厳密に議論するためには、関数の定義域に属する「連続でない点」と、関数の定義域の外の(位相空間の数の集合には属する)「連続でない点」とは性格が異なる点であるので区別して考えた方が良い。
特に、連続関数の連続性を、位相空間論では独立変数xの連結性と従属変数yの連結性(位相空間論の連続関数の定義による)に分けて扱った。そのため、関数f(x) が定義されている点の不連続点は、すなわち従属変数yの連結性のみが損なわれた不連続点は、「位相空間論の不連続点」と呼ぶのが適切であろう。関数f(x) が定義されない点などの、独立変数xの連結性が損なわれた点の不連続点は、xの連結性が損なわれているだけでなく同時にyの連結性も損なわれている場合(上図のグラフ:実数の位相空間の場合)もあるので、定義付けが難しい。「位相空間論以外の不連続点」と呼ぶのが適切であろう。
【微分積分の初心者には、位相空間論の議論が破綻しているように見える】
位相空間論では、極限の概念を、例えば変数xの位相空間の数の集合を有理数のみとした場合に、変数xが限りなく近づく先を有理数のみに限定するなどの、極限の宛先を位相空間の数の集合に属する点aのみに限定している。位相空間の数の集合が有理数のみであるということは、数同士の距離が近いか遠いかの関係が有理数同士の間でのみ定義されているからである。
位相空間論では、位相空間の数の集合を有理数のみにしている場合に、その有理数の点の数列の極限を位相空間の数の集合以外の新たな数(無理数β)に向ける操作を認めない。(無理数βは有理数ではないのだから)数列の極限の数βが存在しないとみなして無視しその極限を排除する。そういうルールにより、極限の概念の適用を制限し、数学体系を再構築する。
(厳密に言うと、極限の概念の元になっている数同士の近さの関係を、位相空間の数の集合に属する数同士にしか認めないのが位相空間の概念だからである。もし、近いと思われる新しい数を発見してそれを今までの位相空間の数の集合に加えることは、それまでとは異なる位相空間を設定することになる。なお、近いと思われる新たな数が発見されるならば、それまでの位相空間の数の集合に不備があった、と言える。)
位相空間論は、そのように既存知識(数とは位相空間の数の集合に属する点=有理数のことである)という思考の枠組みからはみ出さないように極限の操作を制限して構築した数学体系である。
それにより、独立変数xを既に定めている数の集合(有理数)の範囲に限定して抽象化した関数f(x) の連続性の性質を調べている。
これは、有理数の数列の極限が有理数でない場合に新しい数(無理数)が発見されたと考えて数の概念を拡張する従来の発想とは全く逆の、(知らない数は存在しないと考える)内向きの発想を基礎にした考え方である。
位相空間論では、関数f(x) の点aにおける連続性の定義の式(10)の独立変数xの極限の宛先の数aはxの位相空間の数の集合の点に限定する制限を加えた極限を利用して、抽象化された「位相空間論の関数の連続性」を定義する。
しかし、そうして定義した関数f(x) の連続性には以下の難点がある。
位相空間論での関数の連続性の定義では、以下のグラフであらわされる、有理数を位相空間の数の集合とし、その数の集合全てを定義域とする関数f(x) が、どの有理数の点aでも連続になる。しかしそのグラフが切れ切れである。

(参考)同様な議論が、「嶺幸太郎 著:微分積分学の試練」の130ページにある。
(130ページから引用)「なお,単に関数が連続だからといってグラフが繋がるとは限らない.次の例は、連続関数のグラフが繋がるためには定義域自身が繋がっている必要があることを示唆する:例8.5.2」
上のグラフで、x=√2 の点は、位相空間のxの数の集合(有理数)に属さない。位相空間論では、位相空間のxの数の集合に属さない点 x=√2 は、関数が連続とも、不連続とも評価しない(不連続点とは、位相空間の数の集合に属する点に対して言えることである)。
上図の、位相空間の数の集合を有理数とした場合に、その数の集合をxの定義域とする関数f(x) は、定義域内(有理数)のどの点においても位相空間論の連続性が満足されている。
図の通りに関数f(x) はf(x) の値がx=√2 の点でf(x) の値が極端にずれている。しかし、その点は位相空間の数の集合に属さない。この関数f(x) は、有理数の位相空間では連続関数である。位相空間論では、独立変数xの数列の極限値がxの位相空間の数の集合に属さない場合には、その値を数で無いとして無視する。位相空間論では、そのように極限の概念を制限する。有理数の位相空間の数の集合が連結しないことに起因して、この図のようにグラフが切れ切れで繋がっていないことは位相空間論の「連続性の定義」によっては判別できず、この関数を連続関数と呼んでいる。位相空間論の定義する連続関数のグラフが繋がるためには関数の定義域が連結している(〔定義の役割〕の第1の条件を満足する)必要がある。(有理数全体は連結していない)
位相空間論では、上図の関数f(x) の定義域のxの集合の中の2つの独立したxの集合B(-√2<x<√2)と集合C(√2<x<3√2)を考える。集合BとCが、xの境界点β(x=√2 )をそれらの集合の共通の境界点としている。その境界点βが集合BにもCにも含まれない場合は、独立変数xの定義域の数の集合がその無理数βの点で連結していない。
---〔点xの定義域が連結しない条件〕---
点xの定義域の集合は左側の集合Bと右側の集合Cに分割できる。左側の集合Bの点を右側に限りなく近づけた先の境界点βは集合Bにも集合Cにも属さない。また、その境界点βは右側の集合Cの点を左側に限りなく近づけた先の境界点でもある。その境界点βが集合Bにも集合Cにも属さないので、集合Bと集合Cを合わせた集合は連結しない。
(厳密な議論)
境界点とは、有理数の位相空間の数の集合に属する有理数の点に限られる。数同士の距離が近いか遠いかの関係は、位相空間の数の集合に属する数同士の間でのみ定義されているからである。
無理数βは有理数では無いので、有理数の位相空間の数の集合に属さず、境界点にならない。(注意:この点は、定義域に属さない場合でも、もし位相空間の数の集合に属するならば「境界点」になる)。そのため、集合Bと集合Cに分割した境目の境界点βは存在しないとみなされる。この場合に位相空間論では、集合Bと集合Cがともに開集合であることを理由にして(境界点βを考えないで)点xの定義域の数の集合が連結しないと認識する。
古典的(基礎的)微分積分学では、定義域の数の集合が無理数の不連続点βによって分断されていると考えるが、位相空間論の微分積分学では、その「分断の原因」を考えない手探りで、定義域が「連結しない」と認識する。(しかし、ある数の集合に関する真実を記述する場合には、その集合を超える要素が必要になる場合があるので、このようなやり方で数の集合に係わる真実を把握することには危うさがある「間違えやすい」と考える)
---(点xの定義域が連結しない条件おわり)---
有理数の変数xの定義域の数の集合が境界点βで連結していない(境界点βが無理数なので定義域に含まれない)ことが、古典的な微分積分学での「関数f(x) が点βで連続でない」に対応する。
位相空間論には、フェリックス・ハウスドルフの貢献が大きい。
ハウスドルフの書いた集合論の教科書が位相空間論の基礎になっている。ハウスドルフの集合論の教科書を読むと、議論が破綻しているものになっていることに驚く。もちろん、議論の全体としては、(ある意味で?) 破綻をきちんと回避している。
フェリックス・ハウスドルフの研究成果の位相空間論を簡単に理解できると安易には考えずに、その理論が教えようとする心を学んで欲しい。その心の理解のためには、位相空間論を学ぶ以前に、 古典的(基礎的)微分積分学の基礎になっている連続関数の概念は、区間で連続な関数のことである ことを学んでおいて欲しい。
古典的(基礎的)微分積分学で、区間で連続な関数が千切れていなかった性質は、位相空間論によって、関数f(x) の独立変数xの定義域の連結性に依存していたことが浮き彫りになった。位相空間論によって、古典的(基礎的)微分積分学で連続関数と定義されていた、区間で連続な関数f(x) の性質が、関数の抽象化された連続性の概念と、関数の独立変数xの定義域の抽象化された連結性の概念と、で構成されていることが浮き彫りにされた。
《位相空間論に対する感想1》
有理数の数の集合Dの位相空間を定義域とする関数f(x) の連続性を定義するには、現在の位相空間論での定義では無く、以下の式(10) と式(10b) で定義することを考える。ここで、 位相空間の数の集合Dに属する独立変数xの極限値であって、集合Dに属さない無理数をβとする。式(10)と式(10b)で関数の連続性を定義すれば、有理数のみを定義域とする関数f(X) が無理数の点βで途切れることもない連続性が定義できる。なぜ、そのように関数の連続性を定義して理論を作らないのだろうか?式(10b)が成立していることをいちいち確認するのは面倒な作業である。それが、そうしない理由だと思う。

《位相空間論に対する感想2》
実数全体を位相空間の数の集合とし、関数f(x) の定義域を1点の実数aとする。すなわち、関数f(x) の定義域の数の集合を{a} とする。そして、f(a)=b とする。この関数f(x) は、位相空間論の連続関数の厳密な定義に従うと、連続関数である。連続性とは異なる点同士の関係であるべきなので、1点だけの連続性は無意味である。そのため位相空間論の関数の連続性の定義には不備があると思う。意味のある情報を得るために、位相空間論の設定・扱いには注意する必要がある。
《関数の連続性の条件》
関数がある点aで連続であるとは、第1の条件として、関数の定義域が点aと、aの近傍で連結していることである。第2の条件として、点aで関数f(x) の値域が連結していることである。その2つの条件を満足しない点aは「連続でない点」である。
第1の条件は、変数xの点aが関数f(x) の定義域に含まれることと、x=aの近傍の定義域は実数が連結したxの微小区間であることとを要請する(連結している数の集合は実数の区間だけである)。
第2の条件は、式(10)であらわすように、点aに限りなく近づく関数f(x) の極限の値がf(a) であることを要請する。

古典的(基礎的)微分積分学は、実数全体を位相空間の数の集合にした上で、実数の区間を定義域とする関数f(x) の微分積分学である。
リンク:
連続関数
連続性公理と実数を定義する3つの方法 (初学者向けの話)
関数の極限の定義
関数の極限と連続性
第3章 位相空間の基礎のキソ
ハウスドルフの集合論と位相空間論の誕生
高校数学の目次
〔前のページ〕〔次のページ〕〔微分積分の目次〕
《実数とは》
例えば、以下の図の規則によってx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が有理数の中には無い。しかし、そのように限りなく近づく先の数が存在すると考えた。その数を実数と呼ぶ。

このように、「限りなく近づける」操作(極限の操作)が、数の概念を拡張することを要請し、そうして拡張された新たな数が実数であった。この拡張された数である実数から成るとされる数直線には数の連続性があるとされた。このように極限の操作によって数の概念が実数にまで拡張され、それが数の連続性と微分積分の礎になった。
1970年代の高校数学の参考書「大道を行く数学(解析編)」から、以下の知識が得られる。
[連続の定義]

のとき、関数y=f(x)は x=a で連続であるという。
また、f(x) がある区間のすべてのxで連続のとき、その区間で連続であるという。
しかし、(10)式は単なる定義であって、それだけではいろいろな問題を考察するのに不十分であろう。連続について知るには、裏返して不連続である場合を知るのが早道である。不連続の場合は、(10)式が成り立たない場合だから、次の4通りが考えられる。

以下、これらについて、例をもって説明しよう。




例2.9 [x] はxを越えない最大の整数とする.




どちらも存在しない.このことについては多くを語る必要もないであろう.


例2.10 無限個の項の和が存在するとして定義された関数

は、x≠0のとき、次のような工夫をすると簡単な形にまとめられる.


この関数のグラフは図2.10 の通りである.

不連続な場合、f(x) のグラフは不連続なxにおいて切れていて、連結していない.このことは逆に連続なときは、グラフはxにおいて切れ目のない線になっている.また(10)式は、
x-aが無限小のとき、f(x)-f(a) が無限小
ということである.したがってf(x) が連続なところでは
xの微小変化に対応し、f(x) が微小変化する
そして、このような関数を連続関数というといいかえても良い.
(参考)藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」によると、「f(x)がx=ξで連続でない場合に、x=ξ(という変数xの数直線上の点)をf(x)の不連続点という。」と定義されている。
〔定義の役割〕
連続関数とは、第1の条件として、関数の定義域が連結していること、第2の条件として、定義域の点毎に関数f(x) の値域が連結していること。その2つの条件が成り立ちグラフが1つながりに連結している関数f(x) をどのように表すかが連続関数の定義の役割である。
(注意1)関数f(x) の点とは、関数をあらわすグラフ上の点ではなく、変数xの数直線上の点である。
(注意2)
「不連続点」の定義は、現代数学の位相空間論の定義では、その不連続なxの値で関数値f(x) が定義されている場合のみに「不連続点」という言葉を使っている。つまり、古典的(基礎的)な微分積分学における上の例2.8 のx=1の点のように関数値f(1) が定義されていない点は、位相空間論の定義では不連続点とは呼んでいない。(しかし、後に説明するように、これは誤りである)
〔古典的(基礎的)微分積分学〕
古典的(基礎的)微分積分学では、関数の連続性の定義は、〔定義の役割〕における2つの条件が満足されるように定義する。先ず、第1の条件を満足するために、変数xの点aの近傍で実数が連結する区間内(連結する全ての実数)での極限を用いる。次に、第2の条件を満足するように、式(10)によって関数f(x) の連続性を定義している。
「区間で定義された関数f(x)が、その区間のすべてのxの値で古典的(基礎的)な連続性があるとき、f(x)は古典的(基礎的)な微分積分学で定義された連続関数である」
そして、実数上のx=aの点で関数f(x) の連続性の条件が満たされない場合を、その(実数上の)点aを、不連続点と呼んでいる。
実数上のx=aの点は、関数f(x) の連続な点であるか、関数f(x) の不連続点(当ブログでは「連続でない点」と呼ぶ)かの2つの場合のどちらかである。
すなわち、あるxの点が不連続である条件は、そのxの点が連続でないことである。
古典的(基礎的)微分積分学は、実数全体の数の集合に基づいて解析することで、関数の性質の解析の見通しを良くしています。
〔位相空間論によって再構築した微分積分学〕
(微分積分を学び始めた高校生はこれ以降は読まないで良い)
一方で、位相空間論によって再構築した微分積分学は、位相空間の数の集合(限定された数)のみに基づいて関数の性質を解析するので、関数の解析の見通しが極めて悪い。手探りで関数を解析するので間違え易いという特徴があります。
位相空間論によって再構築した微分積分学では、関数の連続性の定義は、〔定義の役割〕における2つの条件のうちの第2の条件のみを満足する定義である。
すなわち、例えば位相空間の数の集合を有理数のみ(数の集合が連結しない)に定めても良く、関数f(x) の定義域はその数の集合の部分集合に限られる。そのようにして定義域の連結性が要求されていない。
そして、式(10) により値域の連続性を定義する。

すなわち、独立変数x及び点aが、位相空間の数の集合(例えば有理数)に属する場合のみを考える。そして、関数f(x) の定義域は位相空間の数の集合の部分集合に限られ、点x及び点aは定義域内の点である。式(10) は、その点xが限りなく点a近づくときに、f(x) が限りなくf(a) に近づくという関係があることによって関数f(x) の値域の連続性を表している。
「関数 f(x) が、その関数f(x) の定義域のすべての x =aの値で位相空間論的な連続性があるとき、 f(x) は位相空間論で定義された連続関数である」
そして、例えば有理数の位相空間の数の集合に属するx=aの点で関数f(x) の連続性の条件が満たされない場合を、その点aを、不連続点と呼んでいる。
位相空間の数の集合(有理数)に属するx=aの点は、
①関数f(x) の定義域に属さない点aの不連続点であるか、
②定義域上の点aであって関数f(x) の連続な点であるか、
③定義域上の点aであって関数f(x) の不連続点であるか、
の3つの場合のどれかである。
(4つ目の場合として、例えば無理数のx=βの点などの、有理数の位相空間の数の集合に属さない点βについては、位相空間の数の集合に属さないので存在しない数とみなす。その点βについては言及しない)
位相空間論では、(3°の)関数f(x)=1/x において、点x=0は、関数f(x) の定義域内の点ではないが、位相空間の数の集合(有理数や実数)に属する点なので、不連続点である。
すなわち、あるxの点が不連続である条件は、
(1)先ず、そのxの点が位相空間の数の集合に属する点であること。
(2)次に、そのxの点が連続でないこととの、
2つの条件を満足する必要がある。
点x=0は、その2つの条件を満足するので不連続点である。
(点の種別の定義付けの心)
位相空間論での「不連続点」の厳密な定義は、定められた位相空間の数の集合だけで議論することである。その位相空間の数の集合に属するxの点は、関数f(x) の定義域に属するか、定義域に属さないかの何れかである。
位相空間論は、(1°)の、変数xの定義域に属さない「取除きうる不連続点a」については、その点aが位相空間の数の集合に属する場合は、関数f(x) の定義域の外の「境界点」とする。
その「境界点」は連続な点ではないので「不連続点」である。かくして、位相空間論では、定義域の外の境界点を「不連続点」と定義付ける。
しかしながら、有理数のみの位相空間においては、以下の図の関数のx=√2 の点は無理数であって、その位相空間の数の集合に属さない。

この場合は関数f(x) の有理数の「境界点」が存在しないので、有理数の位相空間の不連続点も存在しないことに注意すべきである。古典的(基礎的)微分積分学の視点(実数を数の集合とする位相空間)で見ると、この図の関数(厳密に言うと無理数でも定義された関数の場合)は、無理数の境界点で分割された3つの異なる連続関数から成ることがわかる。
(注意3)
位相空間論の説明において、位相空間の数の集合に属する点であって「不連続点」の資格がある点の一部の、数f(x) の定義域に属する点のみを「不連続点」と説明する誤りが流通している。(そういう誤りを基礎的微分積分学(高校数学)に混ぜないでほしい)。そういう誤りに巻き込まれないために、古典的(基礎的)な微分積分学が定義する「不連続点」や、(位相空間論においても)定義域を連結させない境界点の「不連続点」は、このブログでは、「連続でない点」と呼ぶことにして数学用語を明確にする。
(補足)
なお、位相空間論で点の連続性を厳密に議論するためには、関数の定義域に属する「連続でない点」と、関数の定義域の外の(位相空間の数の集合には属する)「連続でない点」とは性格が異なる点であるので区別して考えた方が良い。
特に、連続関数の連続性を、位相空間論では独立変数xの連結性と従属変数yの連結性(位相空間論の連続関数の定義による)に分けて扱った。そのため、関数f(x) が定義されている点の不連続点は、すなわち従属変数yの連結性のみが損なわれた不連続点は、「位相空間論の不連続点」と呼ぶのが適切であろう。関数f(x) が定義されない点などの、独立変数xの連結性が損なわれた点の不連続点は、xの連結性が損なわれているだけでなく同時にyの連結性も損なわれている場合(上図のグラフ:実数の位相空間の場合)もあるので、定義付けが難しい。「位相空間論以外の不連続点」と呼ぶのが適切であろう。
【微分積分の初心者には、位相空間論の議論が破綻しているように見える】
位相空間論では、極限の概念を、例えば変数xの位相空間の数の集合を有理数のみとした場合に、変数xが限りなく近づく先を有理数のみに限定するなどの、極限の宛先を位相空間の数の集合に属する点aのみに限定している。位相空間の数の集合が有理数のみであるということは、数同士の距離が近いか遠いかの関係が有理数同士の間でのみ定義されているからである。
位相空間論では、位相空間の数の集合を有理数のみにしている場合に、その有理数の点の数列の極限を位相空間の数の集合以外の新たな数(無理数β)に向ける操作を認めない。(無理数βは有理数ではないのだから)数列の極限の数βが存在しないとみなして無視しその極限を排除する。そういうルールにより、極限の概念の適用を制限し、数学体系を再構築する。
(厳密に言うと、極限の概念の元になっている数同士の近さの関係を、位相空間の数の集合に属する数同士にしか認めないのが位相空間の概念だからである。もし、近いと思われる新しい数を発見してそれを今までの位相空間の数の集合に加えることは、それまでとは異なる位相空間を設定することになる。なお、近いと思われる新たな数が発見されるならば、それまでの位相空間の数の集合に不備があった、と言える。)
位相空間論は、そのように既存知識(数とは位相空間の数の集合に属する点=有理数のことである)という思考の枠組みからはみ出さないように極限の操作を制限して構築した数学体系である。
それにより、独立変数xを既に定めている数の集合(有理数)の範囲に限定して抽象化した関数f(x) の連続性の性質を調べている。
これは、有理数の数列の極限が有理数でない場合に新しい数(無理数)が発見されたと考えて数の概念を拡張する従来の発想とは全く逆の、(知らない数は存在しないと考える)内向きの発想を基礎にした考え方である。
位相空間論では、関数f(x) の点aにおける連続性の定義の式(10)の独立変数xの極限の宛先の数aはxの位相空間の数の集合の点に限定する制限を加えた極限を利用して、抽象化された「位相空間論の関数の連続性」を定義する。
しかし、そうして定義した関数f(x) の連続性には以下の難点がある。
位相空間論での関数の連続性の定義では、以下のグラフであらわされる、有理数を位相空間の数の集合とし、その数の集合全てを定義域とする関数f(x) が、どの有理数の点aでも連続になる。しかしそのグラフが切れ切れである。

(参考)同様な議論が、「嶺幸太郎 著:微分積分学の試練」の130ページにある。
(130ページから引用)「なお,単に関数が連続だからといってグラフが繋がるとは限らない.次の例は、連続関数のグラフが繋がるためには定義域自身が繋がっている必要があることを示唆する:例8.5.2」
上のグラフで、x=√2 の点は、位相空間のxの数の集合(有理数)に属さない。位相空間論では、位相空間のxの数の集合に属さない点 x=√2 は、関数が連続とも、不連続とも評価しない(不連続点とは、位相空間の数の集合に属する点に対して言えることである)。
上図の、位相空間の数の集合を有理数とした場合に、その数の集合をxの定義域とする関数f(x) は、定義域内(有理数)のどの点においても位相空間論の連続性が満足されている。
図の通りに関数f(x) はf(x) の値がx=√2 の点でf(x) の値が極端にずれている。しかし、その点は位相空間の数の集合に属さない。この関数f(x) は、有理数の位相空間では連続関数である。位相空間論では、独立変数xの数列の極限値がxの位相空間の数の集合に属さない場合には、その値を数で無いとして無視する。位相空間論では、そのように極限の概念を制限する。有理数の位相空間の数の集合が連結しないことに起因して、この図のようにグラフが切れ切れで繋がっていないことは位相空間論の「連続性の定義」によっては判別できず、この関数を連続関数と呼んでいる。位相空間論の定義する連続関数のグラフが繋がるためには関数の定義域が連結している(〔定義の役割〕の第1の条件を満足する)必要がある。(有理数全体は連結していない)
位相空間論では、上図の関数f(x) の定義域のxの集合の中の2つの独立したxの集合B(-√2<x<√2)と集合C(√2<x<3√2)を考える。集合BとCが、xの境界点β(x=√2 )をそれらの集合の共通の境界点としている。その境界点βが集合BにもCにも含まれない場合は、独立変数xの定義域の数の集合がその無理数βの点で連結していない。
---〔点xの定義域が連結しない条件〕---
点xの定義域の集合は左側の集合Bと右側の集合Cに分割できる。左側の集合Bの点を右側に限りなく近づけた先の境界点βは集合Bにも集合Cにも属さない。また、その境界点βは右側の集合Cの点を左側に限りなく近づけた先の境界点でもある。その境界点βが集合Bにも集合Cにも属さないので、集合Bと集合Cを合わせた集合は連結しない。
(厳密な議論)
境界点とは、有理数の位相空間の数の集合に属する有理数の点に限られる。数同士の距離が近いか遠いかの関係は、位相空間の数の集合に属する数同士の間でのみ定義されているからである。
無理数βは有理数では無いので、有理数の位相空間の数の集合に属さず、境界点にならない。(注意:この点は、定義域に属さない場合でも、もし位相空間の数の集合に属するならば「境界点」になる)。そのため、集合Bと集合Cに分割した境目の境界点βは存在しないとみなされる。この場合に位相空間論では、集合Bと集合Cがともに開集合であることを理由にして(境界点βを考えないで)点xの定義域の数の集合が連結しないと認識する。
古典的(基礎的)微分積分学では、定義域の数の集合が無理数の不連続点βによって分断されていると考えるが、位相空間論の微分積分学では、その「分断の原因」を考えない手探りで、定義域が「連結しない」と認識する。(しかし、ある数の集合に関する真実を記述する場合には、その集合を超える要素が必要になる場合があるので、このようなやり方で数の集合に係わる真実を把握することには危うさがある「間違えやすい」と考える)
---(点xの定義域が連結しない条件おわり)---
有理数の変数xの定義域の数の集合が境界点βで連結していない(境界点βが無理数なので定義域に含まれない)ことが、古典的な微分積分学での「関数f(x) が点βで連続でない」に対応する。
位相空間論には、フェリックス・ハウスドルフの貢献が大きい。
ハウスドルフの書いた集合論の教科書が位相空間論の基礎になっている。ハウスドルフの集合論の教科書を読むと、議論が破綻しているものになっていることに驚く。もちろん、議論の全体としては、(ある意味で?) 破綻をきちんと回避している。
フェリックス・ハウスドルフの研究成果の位相空間論を簡単に理解できると安易には考えずに、その理論が教えようとする心を学んで欲しい。その心の理解のためには、位相空間論を学ぶ以前に、 古典的(基礎的)微分積分学の基礎になっている連続関数の概念は、区間で連続な関数のことである ことを学んでおいて欲しい。
古典的(基礎的)微分積分学で、区間で連続な関数が千切れていなかった性質は、位相空間論によって、関数f(x) の独立変数xの定義域の連結性に依存していたことが浮き彫りになった。位相空間論によって、古典的(基礎的)微分積分学で連続関数と定義されていた、区間で連続な関数f(x) の性質が、関数の抽象化された連続性の概念と、関数の独立変数xの定義域の抽象化された連結性の概念と、で構成されていることが浮き彫りにされた。
《位相空間論に対する感想1》
有理数の数の集合Dの位相空間を定義域とする関数f(x) の連続性を定義するには、現在の位相空間論での定義では無く、以下の式(10) と式(10b) で定義することを考える。ここで、 位相空間の数の集合Dに属する独立変数xの極限値であって、集合Dに属さない無理数をβとする。式(10)と式(10b)で関数の連続性を定義すれば、有理数のみを定義域とする関数f(X) が無理数の点βで途切れることもない連続性が定義できる。なぜ、そのように関数の連続性を定義して理論を作らないのだろうか?式(10b)が成立していることをいちいち確認するのは面倒な作業である。それが、そうしない理由だと思う。

《位相空間論に対する感想2》
実数全体を位相空間の数の集合とし、関数f(x) の定義域を1点の実数aとする。すなわち、関数f(x) の定義域の数の集合を{a} とする。そして、f(a)=b とする。この関数f(x) は、位相空間論の連続関数の厳密な定義に従うと、連続関数である。連続性とは異なる点同士の関係であるべきなので、1点だけの連続性は無意味である。そのため位相空間論の関数の連続性の定義には不備があると思う。意味のある情報を得るために、位相空間論の設定・扱いには注意する必要がある。
《関数の連続性の条件》
関数がある点aで連続であるとは、第1の条件として、関数の定義域が点aと、aの近傍で連結していることである。第2の条件として、点aで関数f(x) の値域が連結していることである。その2つの条件を満足しない点aは「連続でない点」である。
第1の条件は、変数xの点aが関数f(x) の定義域に含まれることと、x=aの近傍の定義域は実数が連結したxの微小区間であることとを要請する(連結している数の集合は実数の区間だけである)。
第2の条件は、式(10)であらわすように、点aに限りなく近づく関数f(x) の極限の値がf(a) であることを要請する。

古典的(基礎的)微分積分学は、実数全体を位相空間の数の集合にした上で、実数の区間を定義域とする関数f(x) の微分積分学である。
リンク:
連続関数
連続性公理と実数を定義する3つの方法 (初学者向けの話)
関数の極限の定義
関数の極限と連続性
第3章 位相空間の基礎のキソ
ハウスドルフの集合論と位相空間論の誕生
高校数学の目次
ベクトルの一次独立とは何か
《ベクトルの一次独立とは何か》
2つの独立したベクトルのことを、「2つの一次独立なベクトル」と呼びます。
2つのベクトルのうちのある1つのベクトルが、他の1つのベクトルの実数倍であらわせる場合は、その2つのベクトルが1次従属である、と呼びます。
2つの独立したベクトルという意味は、そういうことはない、という意味です。
3つの独立したベクトルのことを、「3つの一次独立なベクトル」と呼びます。
3つのベクトルのうちのある1つのベクトルが、他の2つのベクトルの合成であらわせる場合は、その3つのベクトルが1次従属である、と呼びます。
3つの独立したベクトルという意味は、そういうことはない、という意味です。
〔2次元ベクトルの2つのベクトルが1次独立であるとは〕
2つのベクトルが0ベクトルではなく、かつ、同一直線上にはないことです。
〔3次元ベクトルの3つのベクトルが1次独立であるとは〕
3つのベクトルが0ベクトルではなく、かつ、同一平面上にはないことです。
別の視点から説明すると、
▷2つのベクトル(2次元平面上のベクトルであっても空間ベクトルであっても良い)が1次独立であるとは、
その2つの(0べクトルではない)ベクトルで(直線につぶれていない)2次元(平面)の斜交座標系を作れるということです。
▷3つのベクトルが1次独立であるとは、
その3つの(0べクトルではない)ベクトルで(平面につぶれていない)3次元(3次元空間)の斜交座標系を作れるということです。

すなわち、
①1次独立な2つのベクトルが平面を構成し、 その2つのベクトルの合成により、その平面上のあらゆるベクトルがあらわせる。
しかも、平面上のあるベクトルを2つの1次独立なベクトルの合成であらわすとき、各ベクトルの合成係数が1つに定まる(式の一意性)。
②1次独立な3つのベクトルが3次元空間を構成し、 その3つのベクトルの合成により、その3次元空間上のあらゆるベクトルがあらわせる。
しかも、3次元空間上のあるベクトルを3つの1次独立なベクトルの合成であらわすとき、各ベクトルの合成係数が1つに定まる(式の一意性)。
例えば、以下のように考える。
2次元ベクトル、又は3次元ベクトル、又は4次元ベクトルで、3つのベクトルが1次独立であるとは、
3つのベクトルが同一平面上にはないことです。
3つの空間ベクトルが同一平面上にあることの確認方法や、同一平面上にはないことの確認方法は、ここをクリックした先のページで説明する。
ここで、2次元ベクトルは、ある平面上のベクトルなので、
2次元ベクトルの3つのベクトルは、同一平面上にある。
すなわち、2次元ベクトルの3つのベクトルは、その3つのベクトルが一次独立になる条件(その3つのベクトルが3次元空間を構成する)を満足しない。
そのため、
2次元ベクトルの3つのベクトルは1次独立にはならない。
2次元ベクトルでの3つのベクトルは、必ず1次従属になる。
1次独立な2つのベクトルaとベクトルbがある場合を考える。その2つのベクトルを合成することで、その2つのベクトルを含む2次元平面上の全てのベクトルがあらわされる。
その2次元平面に垂直な(ベクトルaに垂直で、かつ、ベクトルbに垂直な)ベクトルcを考える。(2次元平面に垂直なベクトルcの求め方は、ここをクリックした先にある)
ベクトルcは、先の2次元平面上のベクトルでは無いので、ベクトルcは、ベクトルaとベクトルbの合成では作ることができない。また、ベクトルcとベクトルbを合成したベクトルにはベクトルaに垂直な成分が含まれるので、ベクトルaは、ベクトルcとベクトルbの合成では作ることができない。同様に、ベクトルbは、ベクトルcとベクトルaの合成では作ることができない。つまり、ベクトルcとベクトルbとベクトルaとの3つのベクトルは、3つの独立したベクトルになる。
その3つのベクトルは1次独立なベクトルである。その3つのベクトルは同一平面上には無い。そして、その3つのベクトルを合成することで、3次元空間の全てのベクトルを表すことができる。
一次独立な2個のベクトルは、平面に含まれる全てのベクトルをあらわす2次元平面の斜交座標系を構成する。一次独立な3個のベクトルは、3次元空間に含まれる全てのベクトルをあらわす3次元空間の斜交座標系を構成する。一次独立なn個のベクトルがn次元空間の斜交座標系を構成する場合に、そのn次元空間の全てのベクトルに垂直なベクトルcをn+1個目のベクトルにしたn+1個のベクトルは、n+1個の独立したベクトルになる。すなわち、一次独立なベクトルになる。そのn+1個のベクトルは、n+1次元空間に含まれる全てのベクトルを表すn+1次元空間の斜交座標系を構成する。
n次元空間の斜交座標系の原点である0ベクトルをn個の一次独立なベクトルの合成で表す場合には、各ベクトルの合成成分が全て0の場合にのみ、0ベクトルがあらわせる(式の一意性)。
大学数学では、n次元のベクトルをあらわすn次元の斜交座標系(つぶれていない)の原点(0ベクトル)をベクトルの合成であらわす式が、n個のベクトルの合成成分を全て0にした式のみであること(一意性)を使って、n個のベクトルの一次独立を定義している。
n個の(0ベクトルでない)ベクトルの作る斜交座標系がつぶれていてn個のベクトルが(n-1)次元の空間に含まれる場合は、0ベクトルをn個のベクトルの合成であらわすとき、各ベクトルの合成成分が0で無い式でも0ベクトルがあらわせる。また、0ベクトルは、n個のベクトルの全ての合成成分が0の式でもあらわせる。そのように0ベクトルを複数の式であらわせるので、0ベクトルをn個のベクトルであらわす式の一意性が失われる。
n個のベクトルが張る斜交座標系の原点(0ベクトル)をn個のベクトルの合成であらわす式が、n個のベクトルの合成成分が全て0の式のみである(式の一意性がある)ならば、n次元の斜交座標系はつぶれていない。そのとき、そのn個のべクトルが一次独立である、と定義している。
リンク:
ベクトルの1次独立と分解
1次独立(空間ベクトル)
(大学数学)ベクトルの一次独立,一次従属の定義と意味
高校数学の目次
2つの独立したベクトルのことを、「2つの一次独立なベクトル」と呼びます。
2つのベクトルのうちのある1つのベクトルが、他の1つのベクトルの実数倍であらわせる場合は、その2つのベクトルが1次従属である、と呼びます。
2つの独立したベクトルという意味は、そういうことはない、という意味です。
3つの独立したベクトルのことを、「3つの一次独立なベクトル」と呼びます。
3つのベクトルのうちのある1つのベクトルが、他の2つのベクトルの合成であらわせる場合は、その3つのベクトルが1次従属である、と呼びます。
3つの独立したベクトルという意味は、そういうことはない、という意味です。
〔2次元ベクトルの2つのベクトルが1次独立であるとは〕
2つのベクトルが0ベクトルではなく、かつ、同一直線上にはないことです。
〔3次元ベクトルの3つのベクトルが1次独立であるとは〕
3つのベクトルが0ベクトルではなく、かつ、同一平面上にはないことです。
別の視点から説明すると、
▷2つのベクトル(2次元平面上のベクトルであっても空間ベクトルであっても良い)が1次独立であるとは、
その2つの(0べクトルではない)ベクトルで(直線につぶれていない)2次元(平面)の斜交座標系を作れるということです。
▷3つのベクトルが1次独立であるとは、
その3つの(0べクトルではない)ベクトルで(平面につぶれていない)3次元(3次元空間)の斜交座標系を作れるということです。

すなわち、
①1次独立な2つのベクトルが平面を構成し、 その2つのベクトルの合成により、その平面上のあらゆるベクトルがあらわせる。
しかも、平面上のあるベクトルを2つの1次独立なベクトルの合成であらわすとき、各ベクトルの合成係数が1つに定まる(式の一意性)。
②1次独立な3つのベクトルが3次元空間を構成し、 その3つのベクトルの合成により、その3次元空間上のあらゆるベクトルがあらわせる。
しかも、3次元空間上のあるベクトルを3つの1次独立なベクトルの合成であらわすとき、各ベクトルの合成係数が1つに定まる(式の一意性)。
例えば、以下のように考える。
2次元ベクトル、又は3次元ベクトル、又は4次元ベクトルで、3つのベクトルが1次独立であるとは、
3つのベクトルが同一平面上にはないことです。
3つの空間ベクトルが同一平面上にあることの確認方法や、同一平面上にはないことの確認方法は、ここをクリックした先のページで説明する。
ここで、2次元ベクトルは、ある平面上のベクトルなので、
2次元ベクトルの3つのベクトルは、同一平面上にある。
すなわち、2次元ベクトルの3つのベクトルは、その3つのベクトルが一次独立になる条件(その3つのベクトルが3次元空間を構成する)を満足しない。
そのため、
2次元ベクトルの3つのベクトルは1次独立にはならない。
2次元ベクトルでの3つのベクトルは、必ず1次従属になる。
1次独立な2つのベクトルaとベクトルbがある場合を考える。その2つのベクトルを合成することで、その2つのベクトルを含む2次元平面上の全てのベクトルがあらわされる。
その2次元平面に垂直な(ベクトルaに垂直で、かつ、ベクトルbに垂直な)ベクトルcを考える。(2次元平面に垂直なベクトルcの求め方は、ここをクリックした先にある)
ベクトルcは、先の2次元平面上のベクトルでは無いので、ベクトルcは、ベクトルaとベクトルbの合成では作ることができない。また、ベクトルcとベクトルbを合成したベクトルにはベクトルaに垂直な成分が含まれるので、ベクトルaは、ベクトルcとベクトルbの合成では作ることができない。同様に、ベクトルbは、ベクトルcとベクトルaの合成では作ることができない。つまり、ベクトルcとベクトルbとベクトルaとの3つのベクトルは、3つの独立したベクトルになる。
その3つのベクトルは1次独立なベクトルである。その3つのベクトルは同一平面上には無い。そして、その3つのベクトルを合成することで、3次元空間の全てのベクトルを表すことができる。
一次独立な2個のベクトルは、平面に含まれる全てのベクトルをあらわす2次元平面の斜交座標系を構成する。一次独立な3個のベクトルは、3次元空間に含まれる全てのベクトルをあらわす3次元空間の斜交座標系を構成する。一次独立なn個のベクトルがn次元空間の斜交座標系を構成する場合に、そのn次元空間の全てのベクトルに垂直なベクトルcをn+1個目のベクトルにしたn+1個のベクトルは、n+1個の独立したベクトルになる。すなわち、一次独立なベクトルになる。そのn+1個のベクトルは、n+1次元空間に含まれる全てのベクトルを表すn+1次元空間の斜交座標系を構成する。
n次元空間の斜交座標系の原点である0ベクトルをn個の一次独立なベクトルの合成で表す場合には、各ベクトルの合成成分が全て0の場合にのみ、0ベクトルがあらわせる(式の一意性)。
大学数学では、n次元のベクトルをあらわすn次元の斜交座標系(つぶれていない)の原点(0ベクトル)をベクトルの合成であらわす式が、n個のベクトルの合成成分を全て0にした式のみであること(一意性)を使って、n個のベクトルの一次独立を定義している。
n個の(0ベクトルでない)ベクトルの作る斜交座標系がつぶれていてn個のベクトルが(n-1)次元の空間に含まれる場合は、0ベクトルをn個のベクトルの合成であらわすとき、各ベクトルの合成成分が0で無い式でも0ベクトルがあらわせる。また、0ベクトルは、n個のベクトルの全ての合成成分が0の式でもあらわせる。そのように0ベクトルを複数の式であらわせるので、0ベクトルをn個のベクトルであらわす式の一意性が失われる。
n個のベクトルが張る斜交座標系の原点(0ベクトル)をn個のベクトルの合成であらわす式が、n個のベクトルの合成成分が全て0の式のみである(式の一意性がある)ならば、n次元の斜交座標系はつぶれていない。そのとき、そのn個のべクトルが一次独立である、と定義している。
リンク:
ベクトルの1次独立と分解
1次独立(空間ベクトル)
(大学数学)ベクトルの一次独立,一次従属の定義と意味
高校数学の目次
連続関数とは何か
やさしい微分積分
〔前のページ〕〔次のページ〕不連続点と連続でない点
〔微分積分の目次〕
《連続関数》
微分積分の命綱を握っているのが連続関数の概念です。
【1つながりに連続する関数】
微分積分で扱う関数は、均質な基本的な要素の関数を単位にして考える。具体的には、1つながりに連続する関数を単位にして考える。その1つながりに連続する関数が、正しく定義された連続関数である。 連続関数は、グラフが途切れることなくつながっている関数です。
【区間とは】
関数のグラフが途切れる、すなわグラフがちちぎれる場合は、下図のように、関数 f(x) のy=f(x) のグラフのy軸の方向にすき間を空けてちぎれる場合と、

下図のように、変数xのx軸の方向にすき間を空けてちぎれる場合と

の2通りのちぎれ方がある。
区間とは、x軸上で実数がすき間なくつまったx軸上での1つの連結領域のことを区間と呼ぶ。
上図の2通りのちぎれ方をともに判定できるようにするために、x軸の数直線上の実数がすき間なくつまった区間内の点毎に、ちぎれているか、連続であるかを把握する。
区間内の点とはx軸の数直線上の点である。
《実数の連続性》
実数には連続性がある。有理数には連続性が無い。
実数の連続性とは、連続性の公理を満足することである。連続性の公理とは、
「実数の部分集合のうち、上に有界かつ空でないものは、必ず最小上界(上限)を持つ(連続性の公理)」
というものである。
この連続性の公理を満足する数の集合(実数)では、例えば、以下の図の規則によってx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が実数の中にある。

しかし、連続性の公理を満足しない数の集合(有理数)の場合では、限りなく近づける先の数がその数の集合(有理数)の中に無い。その場合には、「限りなく近づける」先は、有理数以外の実数であると定義されている。実数の集合で考えるならば、限りなく近づける先の数も実数の集合の中にある。
この実数の連続性公理が微分積分の概念の出発点になっている。
連続関数の定義は、1817年にBolzanoが中間値の定理を証明する前提条件に定義した連続関数の定義により、歴史上初めて連続関数が正しく定義された(その定義は関数の連続性を区間で定義するものである)。
日本の大学数学では、1817年にBolzanoが定義した連続関数を、「区間で連続な関数」と呼んでいる。
関数の連続性に係る定理には、必ず「区間で連続な関数」という言葉が使われる。
関数f(x)の連続性は、x軸でのxの点毎に、各点の近傍に微小区間を定めてその微小区間で関数の連続性を判定する。
更に、x軸での所定の幅の広がりがある区間において、その区間内の全ての実数のxの点で関数f(x)が連続である場合に、その区間で定義された関数f(x)が連続関数であるという。
下図の3つの区間で定義された3つの関数F1(x), F2(x), F3(x)が3つの連続関数です。
1つながりのグラフが1つの連続関数です。
【区間の定義】
「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がない1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。「隙間が無い」大前提のために、連続性の公理を満足する実数の集合でなければならない。
a, b を実数とする. a≦x≦b の実数xをすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区間と呼ぶ.
a<x<b の実数xをすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.
変数xの「区間」の大切な特徴は、「区間」は、所定の1かたまりのxの範囲内での隙間が無い全ての実数の集合が「区間」である。
【連続でない点】
y=f(x) ≡ 1/xは、x=0でグラフが途切れた関数です。
関数の連続性は、x軸上の点毎に判定する。x軸上のx=0という点が存在します。その点で f(x) の値が無いので、x=0の点では関数 f(x) は連続ではない。x=0の点は、関数 f(x) が「連続でない点」と呼ぶ。
連続関数とは、関数の定義域が実数の区間で連結していて、
その連結区間の点毎に関数の値域が連結することで、関数のグラフが1つながりに連結している関数の事である。
《連続関数の定義域の指定》
連続関数は、関数の定義域が連結するために、所定の区間とセットにして定義されます。
上図の y=f(x) であらわされたグラフは、X=0とX=2で不連続ですが、
0≦x≦2の閉区間 [0,2] で定義された関数 f(x) は連続関数です。
高校数学で学ぶ初等関数はすべて、区間の端点以外には関数が連続でない点が存在しない区間を選び、その区間とセットにして区間で連続な関数が作れます。
例えば、

は、2つの区間(-∞,2)、(2,∞)で連続である。すなわち、2つの「区間で連続な関数」が作れます。
その個別の「区間で連続な関数」を単位にして微分積分を考えます。
このサイトでは、以降では、1817年にBolzanoが正しく定義した連続関数を、誤って定義された連続関数と区別するために、「区間で連続な関数」と呼ぶ。
(補足1)
高校数学の数Ⅲの教科書「数学Ⅲ Advanced」(東京書籍)では、1817年にBolzanoが正しく定義した連続関数を、以下のように正しく定義している。
「関数f(x) がある区間Iに属するすべての値xで連続であるとき、f(x) は区間Iで連続である。」
(補足2)
大学数学で登場する現代数学の位相空間論で定義される(点aで)位相空間論的連続性を持つ連続関数f(x) では、実数の区間に限定されない(例えば有理数を定義域とする)関数f(x) の(点aでの)位相空間論的連続性が定義される。しかし、その位相空間論的連続関数f(x) は、積分可能ではない。また、その関数f(x) は千切れている。そういう現代数学の位相空間論的連続関数を学ぶ以前に、微分積分の基礎知識として、古典的微分積分学の連続関数(区間で連続な関数)の概念をしっかり学んでおく必要がある。
区間で連続な関数の性質を、位相空間論では、「位相空間論的連続関数(千切れていても良い)」の性質と、「(定義域が)連結する関数」の性質、という2つの要素に分けて解析している。その位相空間論を理解する以前の基礎知識として、区間で連続な関数(千切れていない関数)の概念を学んでおく必要がある。
大学数学で学ぶ位相空間論の微分積分を学ぶには、
「嶺幸太郎 著「微分積分学の試練」」を学ぶと良い。
最近の大学数学の微分積分の講義は、微分積分を0から学び始めた初心者向けの古典的な(基礎的な)微分積分の概念は教えなくなっているようです。「微分積分の概念の正しい基礎は高校数学で学んで来たハズだから、大学では現代数学の微分積分を教える」という大学の数学の講義の方針があるように思います。しかし、古典的な(基礎的な)微分積分の概念を知らずして現代数学の微分積分は理解できないと思います。そういう状況なので、高校数学を学ぶ中で、古典的な(基礎的な)微分積分の概念を自力でしっかり学ぶしかないようです。
リンク:
関数が連続であるとは
やさしい微分積分
連続関数の定義
連続性公理と実数を定義する3つの方法 (初学者向けの話)
関数の極限の定義
実数はどう定義される?|実数の連続性公理から理解する
コンパクトであれば有界な閉区間である
高校数学の目次
〔前のページ〕〔次のページ〕不連続点と連続でない点
〔微分積分の目次〕
《連続関数》
微分積分の命綱を握っているのが連続関数の概念です。
【1つながりに連続する関数】
微分積分で扱う関数は、均質な基本的な要素の関数を単位にして考える。具体的には、1つながりに連続する関数を単位にして考える。その1つながりに連続する関数が、正しく定義された連続関数である。 連続関数は、グラフが途切れることなくつながっている関数です。
【区間とは】
関数のグラフが途切れる、すなわグラフがちちぎれる場合は、下図のように、関数 f(x) のy=f(x) のグラフのy軸の方向にすき間を空けてちぎれる場合と、

下図のように、変数xのx軸の方向にすき間を空けてちぎれる場合と

の2通りのちぎれ方がある。
区間とは、x軸上で実数がすき間なくつまったx軸上での1つの連結領域のことを区間と呼ぶ。
上図の2通りのちぎれ方をともに判定できるようにするために、x軸の数直線上の実数がすき間なくつまった区間内の点毎に、ちぎれているか、連続であるかを把握する。
区間内の点とはx軸の数直線上の点である。
《実数の連続性》
実数には連続性がある。有理数には連続性が無い。
実数の連続性とは、連続性の公理を満足することである。連続性の公理とは、
「実数の部分集合のうち、上に有界かつ空でないものは、必ず最小上界(上限)を持つ(連続性の公理)」
というものである。
この連続性の公理を満足する数の集合(実数)では、例えば、以下の図の規則によってx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が実数の中にある。

しかし、連続性の公理を満足しない数の集合(有理数)の場合では、限りなく近づける先の数がその数の集合(有理数)の中に無い。その場合には、「限りなく近づける」先は、有理数以外の実数であると定義されている。実数の集合で考えるならば、限りなく近づける先の数も実数の集合の中にある。
この実数の連続性公理が微分積分の概念の出発点になっている。
連続関数の定義は、1817年にBolzanoが中間値の定理を証明する前提条件に定義した連続関数の定義により、歴史上初めて連続関数が正しく定義された(その定義は関数の連続性を区間で定義するものである)。
日本の大学数学では、1817年にBolzanoが定義した連続関数を、「区間で連続な関数」と呼んでいる。
関数の連続性に係る定理には、必ず「区間で連続な関数」という言葉が使われる。
関数f(x)の連続性は、x軸でのxの点毎に、各点の近傍に微小区間を定めてその微小区間で関数の連続性を判定する。
更に、x軸での所定の幅の広がりがある区間において、その区間内の全ての実数のxの点で関数f(x)が連続である場合に、その区間で定義された関数f(x)が連続関数であるという。
下図の3つの区間で定義された3つの関数F1(x), F2(x), F3(x)が3つの連続関数です。
1つながりのグラフが1つの連続関数です。
【区間の定義】
「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がない1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。「隙間が無い」大前提のために、連続性の公理を満足する実数の集合でなければならない。
a, b を実数とする. a≦x≦b の実数xをすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区間と呼ぶ.
a<x<b の実数xをすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.
変数xの「区間」の大切な特徴は、「区間」は、所定の1かたまりのxの範囲内での隙間が無い全ての実数の集合が「区間」である。
【連続でない点】
y=f(x) ≡ 1/xは、x=0でグラフが途切れた関数です。
関数の連続性は、x軸上の点毎に判定する。x軸上のx=0という点が存在します。その点で f(x) の値が無いので、x=0の点では関数 f(x) は連続ではない。x=0の点は、関数 f(x) が「連続でない点」と呼ぶ。
連続関数とは、関数の定義域が実数の区間で連結していて、
その連結区間の点毎に関数の値域が連結することで、関数のグラフが1つながりに連結している関数の事である。
《連続関数の定義域の指定》
連続関数は、関数の定義域が連結するために、所定の区間とセットにして定義されます。
上図の y=f(x) であらわされたグラフは、X=0とX=2で不連続ですが、
0≦x≦2の閉区間 [0,2] で定義された関数 f(x) は連続関数です。
高校数学で学ぶ初等関数はすべて、区間の端点以外には関数が連続でない点が存在しない区間を選び、その区間とセットにして区間で連続な関数が作れます。
例えば、

は、2つの区間(-∞,2)、(2,∞)で連続である。すなわち、2つの「区間で連続な関数」が作れます。
その個別の「区間で連続な関数」を単位にして微分積分を考えます。
このサイトでは、以降では、1817年にBolzanoが正しく定義した連続関数を、誤って定義された連続関数と区別するために、「区間で連続な関数」と呼ぶ。
(補足1)
高校数学の数Ⅲの教科書「数学Ⅲ Advanced」(東京書籍)では、1817年にBolzanoが正しく定義した連続関数を、以下のように正しく定義している。
「関数f(x) がある区間Iに属するすべての値xで連続であるとき、f(x) は区間Iで連続である。」
(補足2)
大学数学で登場する現代数学の位相空間論で定義される(点aで)位相空間論的連続性を持つ連続関数f(x) では、実数の区間に限定されない(例えば有理数を定義域とする)関数f(x) の(点aでの)位相空間論的連続性が定義される。しかし、その位相空間論的連続関数f(x) は、積分可能ではない。また、その関数f(x) は千切れている。そういう現代数学の位相空間論的連続関数を学ぶ以前に、微分積分の基礎知識として、古典的微分積分学の連続関数(区間で連続な関数)の概念をしっかり学んでおく必要がある。
区間で連続な関数の性質を、位相空間論では、「位相空間論的連続関数(千切れていても良い)」の性質と、「(定義域が)連結する関数」の性質、という2つの要素に分けて解析している。その位相空間論を理解する以前の基礎知識として、区間で連続な関数(千切れていない関数)の概念を学んでおく必要がある。
大学数学で学ぶ位相空間論の微分積分を学ぶには、
「嶺幸太郎 著「微分積分学の試練」」を学ぶと良い。
最近の大学数学の微分積分の講義は、微分積分を0から学び始めた初心者向けの古典的な(基礎的な)微分積分の概念は教えなくなっているようです。「微分積分の概念の正しい基礎は高校数学で学んで来たハズだから、大学では現代数学の微分積分を教える」という大学の数学の講義の方針があるように思います。しかし、古典的な(基礎的な)微分積分の概念を知らずして現代数学の微分積分は理解できないと思います。そういう状況なので、高校数学を学ぶ中で、古典的な(基礎的な)微分積分の概念を自力でしっかり学ぶしかないようです。
リンク:
関数が連続であるとは
やさしい微分積分
連続関数の定義
連続性公理と実数を定義する3つの方法 (初学者向けの話)
関数の極限の定義
実数はどう定義される?|実数の連続性公理から理解する
コンパクトであれば有界な閉区間である
高校数学の目次
微分可能の定義
(ページ内リンク先)
▽はじめに
▽ 微分とは何か
▽微分可能の厳密な定義
▽関数の増減表
▽微分可能の定義の拡張=区間の端での微分可能の定義
▽接線の定義
▽右側微分係数と左側微分係数
▽関数の連続を前提にした、とある定理
▽微分不可能が微分可能に変わる例
▽行なって良い変数変換の条件
▽例題2.4
▽微分の式の前提条件:関数が存在すること
▽リーマン積分可能の定義
▽積分が不可能な関数
(はじめに)「微分・積分」の勉強について
高校2年生から、極限・微分・積分の「意味がわからない」「つまらない」「教わる計算方法が正しいと言える理由(証明)がわからない」で数学の学習から脱落する高校2年生が多いらしい。
その脱落の原因は、高校2年の極限・微分・積分の授業では、数学のうたい文句から外れた教育がされるからではないかと考えます。
すなわち、今までは、
「数学は、公式を正しく証明した後にその公式を使う」
と言って来たが、
高校2年生の、極限・微分・積分の授業からは、
「数学は、計算結果さえ合えば良い、途中の経緯は問わない、公式の証明は間違っていても問題視しない」
という教育思想が入り込み、
その思想の行き過ぎを避けるため、
「便利すぎる公式は、それをつかって直ぐ答えが得られてしまうから教えない」
という思想が混ざり、
数学教育に大きな濁りが入り込むので「微分積分がつまらない」となる原因があるのではないかと考えます。
その濁りに押し流され無いため、高校2年生も 公式を厳密に証明して納得してから使う、数学の心に従って極限・微分・積分の学習をして欲しいと考えます。
また、微分積分の正しい情報を与えてくれる、高校2年生が勉強しても、内容がわかり易くて良い微分積分の参考書の「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円 等の正しい情報を与えてくれる参考書を入手して、正しい情報を学習するのが良いと思います。
(微分とは何か)
先ず、微分とは何かを、微分可能のハッキリした定義を知ることで頭を整理しましょう。
微分可能の定義は:
(1)第1の定義(区間の内点で)の微分可能:
関数f(x) が定義される区間の内点(区間の境界点以外の点)xで関数f(x) の右側微分係数と左側微分係数が一致する場合に微分可能であるとし、微分係数が存在するとする定義。
(2)第2の定義(区間の端点で)の微分可能:
閉区間( a≦x≦b)の関数f(x)の、x=aとx=bとの区間の端点では、片側微分係数があるだけで、微分係数が存在し微分可能であるとする定義。
との2通りの定義があるので要注意です。
(微分積分学の基本定理との関係)
微分積分学の基本定理の根底を支えているのが微分可能の定義です。高校数学では、関数の定義域の区間の内点での微分可能性だけが詳しく教えられている。高校数学は、内点での微分可能の条件があたかも全ての微分可能の条件であるように教えていて、閉区間の端点では条件が満足されないので微分不可能であるように教えている。しかし、閉区間の端点でも(傾きが無限大でなければ)微分可能である。
一方、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の閉区間の端点x=a,bでの微分可能性の定義も明らかにされる。そのため、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)でも、微分積分学の基本定理が成り立つことが把握できる。
《実数とは》
微分積分の命綱を握っているのが実数の概念です。以下の例を用いて実数について考える。
下の図のようにx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が有理数の中には無い。しかし、そのように限りなく近づく先の数が存在すると考えた。その数を実数と呼ぶ。

このように、「限りなく近づける」操作(極限の操作)が、数の概念を拡張することを要請し、そうして拡張された新たな数が実数であった。この拡張された数である実数から成るとされる数直線には数の連続性があるとされた。このように極限の操作によって数の概念が実数にまで拡張され、それが数の連続性と微分積分の礎になった。
《数列の極限》
項が限りなく続く数列x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・を無限数列と言う。xnをその第n項といい、この無限数列を{xn}であらわす。また、an を自然数nの式であらわしたものを数列{xn} の一般項という。
「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の定義は、数の集合Aにおいて、以下のことが成り立つこととして、極限を定義する。
【数列の極限の定義】
以下の図で、「数の集合Aの要素で、点a以外の値の、変数xの無限数列{xn}を考える。

この数列{xn}では、自然数nが限りなく大きくなるとき、第n項は限りなく値aに近づく。
一般に、数列{xn}において、nが限りなく大きくなるにつれて、xn が一定の値aに限りなく近づくとき、数列{xn}はaに収束する、または、数列{xn}の極限はaであるという。その値aを数列{xn}の極限値であるという。(点aは数の集合Aの要素で無くても良い)。
数列{xn}の極限値がaであるとき、次のように書く。

すなわち、「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の概念を、点aに収束する、数の集合Aの要素のxの無限数列を使って数学的に定義した。
その結果、変数xが限りなく近づく先の点aは、すなわち、変数xの極限の数の点aは、
数の集合Aの要素の点xの無限数列の集積点であるという結論が得られる。
--(集積点の定義)--
実数の集合Rの部分集合の数の集合Aを考える。
(1)実数の点aが数の集合Aの集積点であるとは、
点aの値以外の数の集合Aの要素の点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在すること(点aは実数ではあるが、数の集合Aの要素とは限らない)である。
(2)数の集合Aの要素のある数の点yが集積点ではないとき、その点yを数の集合Aの孤立点と呼ぶ。
--(集積点の定義おわり)---
《関数の極限》
関数f(x) の定義域のxの数の集合Aから、aと異なる数x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・ を選んで、点aに収束するxの無限数列{xn}を作った場合に、その無限数列{xn}が点aに収束するのにともなってf(x) が値Cに収束することが、x→aで関数f(x)に極限値Cが存在するための基礎条件である。
関数f(x) において、変数xがaと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくならば、
x→aのときf(x) の極限値がCである。
といい、次のように書く。

また、この場合、”x→aのときf(x) はCに収束する”という。
【関数の極限の定義】
変数xがaと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、関数f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくという関数の極限は、以下のように定義する。
関数f(x) の定義域の集合Aを区間とする。そして、「変数xが限りなくaに近づくとき関数f(x) に極限値Cが存在する」ことの数学的定義を:
「区間A内の点xの、点aに収束する全ての無限数列{xn}で共通して、関数f(x) が同じ値Cに収束する」ことと定義する。
そう定義する理由は、関数f(x) によっては、点aに収束する各無限数列{xn}毎に、関数f(x) が異なる値Cに収束したり、収束しなかったりすることがあるからである。
【関数の極限の定義の論理的帰結】
(区間Aの内点での極限)関数f(x) が定義される区間Aの内点aでの極限は、右側極限と左側極限との両側で極限値が存在して、両側の極限値が一致することが内点で極限が存在する条件である。(区間Aの内点とは、区間Aの端点以外の、区間内の点のことである)。
xが、内点aの値よりも大きい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのf(x) の右側極限値といい、次のようにあらわす。

xが、内点aの値よりも小さい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのf(x) の左側極限値といい、次のようにあらわす。

〔極限が存在する条件〕区間Aの内点aでは、極限が存在する条件は、区間A内の点xの、点aに収束するどの無限数列{xn}であっても関数f(x) が同じ値Cに収束することである。そのため、区間A内の点xの、点aより大きい数の無限数列{xn}による右側極限でも値Cに収束する。また、区間A内の点xの、点aより小さい数の無限数列{xn}による左側極限でも同じ値Cに収束する。すなわち、右側極限も存在し、左側極限も存在して、両者の極限値が一致することが内点で極限が存在するために必要十分な条件である。
(区間Aの端点での極限) 関数f(x) が定義される区間Aの端点aでの極限は、区間A内の点xの、点aに収束するどの無限数列{xn}であっても関数f(x) が同じ値Cに収束することである。
▷区間Aの左側の端点aでは、無限数列{xn}は、区間A内の点xの、点aより大きい数の無限数列{xn}による右側極限しか無いので、右側極限値が存在するだけで、端点aで極限値が存在する条件になる。
▷区間Aの右側の端点aでは、無限数列{xn}は、区間A内の点xの、点aより小さい数の無限数列{xn}による左側極限しか無いので、左側極限値が存在するだけで、端点aで極限値が存在する条件になる。
《関数の連続性》
「連続関数とは何か」
https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_93.html
のページが参考になる。
関数の連続性の定義についても、極限の定義と同じで、
関数が定義される区間の内点aでの連続性は、点aの両側極限が一致した上で、かつf(a) と等しくなることが、点aで関数が連続である条件です。
関数が定義される区間の端点aでの連続性は、点aの片側極限が存在した上で、かつf(a) と等しくなることが、点aで関数が連続である条件です。
《関数の微分可能性》
「微分とは何か」
https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_6.html
のページが参考になる。
関数の微分可能性の定義についても、極限の定義と同じで、
関数が定義される区間の内点aでの微分可能性は、点aで関数が連続であって、点aの両側での微分係数が一致することが、点aで関数が微分可能である条件です。
関数が定義される区間の端点aでの微分可能性は、点aで関数が連続であって、点aの片側での微分係数が存在することが、点aで関数が微分可能である条件です。
ーー【区間の定義】ーー
「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がない1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。
《神奈川大学》【定義 14.2.4.】
a, b を実数とする. a 以上かつ b 以下の実数をすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区 間と呼ぶ.
a より大きくかつ b 未満の実数をすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.
----定義おわり----
a≦x≦bを満足するxの区間という表現は、a≦x≦bの範囲内の全ての実数xという意味です。
-∞<x<∞という区間もあります。
区間はxの値の範囲を限定するためのa≦x≦bという式とは意味が異なることに注意する必要があります。
(A)「0≦x≦2の区間の変数xで定義された関数f(x)がその区間の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という文では、
f(x)は、0≦x≦2の区間で1つながりに連続した関数f(x)として定義されます。連続関数は、平均値の定理を満足する関数です。。
(B)高校数学での、誤った連続関数の定義
「変数xの0≦x≦2の範囲内の値で関数f(x)が定義されていて、その関数f(x)が定義域の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という高校数学の連続関数の定義では、f(x)は、例えば、
0<x<1で f(x)=0, この定義域内の各点で連続。
1<x<2で f(x)=1, この定義域内の各点で連続。
結局、0≦x≦2の範囲内の全ての定義域の各点で連続という関数も連続関数f(x)にされます。しかし、そのように、すき間をはさんだ2つの区間を合わせた複合区間を定義域とする関数は平均値の定理を満足しない。それは連続関数ではなく、その定義は正しい連続関数の定義ではない。
この例の様に、「区間」という用語は変数xの数直線上の、すき間がない1かたまりの実数の集合をあらわす。変数xの数直線上の「区間」では、その変数xの範囲内に実数のすき間があってはいけない。
「区間」という用語は、特に重要な関数である連続関数の連続性を定義するために必要な、連続関数f(x)の変数xの集合体がいつも持っていなければならない連続性という重要な性質が「区間」という概念を用いてあらわされている。
すなわち、変数xの「区間」の性質で大切なのは、
「区間」のなかに変数xの値が隙間なく存在すること。
つまり所定範囲内での隙間が無い1かたまりの実数の集合という概念が「区間」という用語で定義されている。
区間について考えるという事は、その区間内の全ての実数の座標xの点を考えるという事を意味する。すなわち、区間で定義された関数の微分可能性は、変数xの数直線上の実数が隙間なくつまっている区間を基にして定義される概念である。
----------区間の定義終わり-------------
--(連続関数の定義の誤りに注意)---
また、高校で教えている連続関数の定義が間違っていて、それも微分可能の意味を理解できなくする原因になっているので要注意です。
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」で定義されている連続関数の定義のように、大学では、定義域として、実数を完全に含んで連結している1つながりの「区間」の全ての実数のxで定義されている関数f(x)に限って連続関数を定義しています。
「区間Aで定義された関数f(x)がその定義域Aの各点で連続であるとき,f(x)は連続関数であるという」
という表現が正しい連続関数の定義です。
ここで、「区間」という言葉が使われた時点で、それは1つながりの連結区間であって、それは、連続で無い点で分断された領域のことでは無い事に十分に注意する必要があります。
ーー注意のおわり---
関数f(x)であらわされるグラフの傾きは、以下のようにあらわされます。
この傾きは以下に説明する微分によって求めます。
---(定義2.1 「微分積分学入門」(横田 壽)60ページ---
(区間の内点と端点での関数の微分可能の定義)
関数f(x) の変数xの定義域Aが、点x0 を含むある区間A(開区間でも閉区間でも良く、x0は閉区間の端点であっても良い)で定義されているとき,(その区間Aの点x=x0+hでの関数の値f(x0+h) に係わる以下の式の)極限値

(有限の傾きC)が存在するならば,
関数f(x) は, x = x0 で微分可能(differentiable) であるという.
また,この極限値Cを点x0 における微分係数といい,
で表わす.
-----(定義おわり)---------------------------
-----(定義の言い換え)---------------
微分可能の定義を理解するために、以下の様に、自分の言葉で定義を言い換えするのが良いと考えます。
(1)
X0がある区間Aの内点(区間Aの境界点以外の点)の場合は、
x0に近い(例えばx0から微小な値 δ 以内の誤差の)区間A内の全ての実数の値の変数x(ただしx0を除外する)を考える。
(注意1)
微分可能の定義には、x0 と、それ以外の値のxとを考えるという条件が必ず入るので(曲線の傾きを求めるには、必ず異なる2点を使う必要がある)、 x0の近傍の区間Aの全ての実数の点を調べる極限の定義と相性が良いので、極限を使って微分可能を定義している。
また、関数f(x) の定義される区間Aの内点x=x0でのf(x)の微分可能の定義は、点x=x0だけで定義されるのでは無く、x0の点とその近傍の区間Aの点の集合全体を使って、x0の点でのf(x)の微分可能性を定義している。
高校数学で主に教えられている区間Aの内点x0の微分可能性では、内点x0の左右の近傍に区間Aの点の集合が存在する。その左右の片側微分係数が一致することで内点x0 の微分可能性を調べている。
▽はじめに
▽ 微分とは何か
▽微分可能の厳密な定義
▽関数の増減表
▽微分可能の定義の拡張=区間の端での微分可能の定義
▽接線の定義
▽右側微分係数と左側微分係数
▽関数の連続を前提にした、とある定理
▽微分不可能が微分可能に変わる例
▽行なって良い変数変換の条件
▽例題2.4
▽微分の式の前提条件:関数が存在すること
▽リーマン積分可能の定義
▽積分が不可能な関数
(はじめに)「微分・積分」の勉強について
高校2年生から、極限・微分・積分の「意味がわからない」「つまらない」「教わる計算方法が正しいと言える理由(証明)がわからない」で数学の学習から脱落する高校2年生が多いらしい。
その脱落の原因は、高校2年の極限・微分・積分の授業では、数学のうたい文句から外れた教育がされるからではないかと考えます。
すなわち、今までは、
「数学は、公式を正しく証明した後にその公式を使う」
と言って来たが、
高校2年生の、極限・微分・積分の授業からは、
「数学は、計算結果さえ合えば良い、途中の経緯は問わない、公式の証明は間違っていても問題視しない」
という教育思想が入り込み、
その思想の行き過ぎを避けるため、
「便利すぎる公式は、それをつかって直ぐ答えが得られてしまうから教えない」
という思想が混ざり、
数学教育に大きな濁りが入り込むので「微分積分がつまらない」となる原因があるのではないかと考えます。
その濁りに押し流され無いため、高校2年生も 公式を厳密に証明して納得してから使う、数学の心に従って極限・微分・積分の学習をして欲しいと考えます。
また、微分積分の正しい情報を与えてくれる、高校2年生が勉強しても、内容がわかり易くて良い微分積分の参考書の「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円 等の正しい情報を与えてくれる参考書を入手して、正しい情報を学習するのが良いと思います。
(微分とは何か)
先ず、微分とは何かを、微分可能のハッキリした定義を知ることで頭を整理しましょう。
微分可能の定義は:
(1)第1の定義(区間の内点で)の微分可能:
関数f(x) が定義される区間の内点(区間の境界点以外の点)xで関数f(x) の右側微分係数と左側微分係数が一致する場合に微分可能であるとし、微分係数が存在するとする定義。
(2)第2の定義(区間の端点で)の微分可能:
閉区間( a≦x≦b)の関数f(x)の、x=aとx=bとの区間の端点では、片側微分係数があるだけで、微分係数が存在し微分可能であるとする定義。
との2通りの定義があるので要注意です。
(微分積分学の基本定理との関係)
微分積分学の基本定理の根底を支えているのが微分可能の定義です。高校数学では、関数の定義域の区間の内点での微分可能性だけが詳しく教えられている。高校数学は、内点での微分可能の条件があたかも全ての微分可能の条件であるように教えていて、閉区間の端点では条件が満足されないので微分不可能であるように教えている。しかし、閉区間の端点でも(傾きが無限大でなければ)微分可能である。
一方、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の閉区間の端点x=a,bでの微分可能性の定義も明らかにされる。そのため、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)でも、微分積分学の基本定理が成り立つことが把握できる。
《実数とは》
微分積分の命綱を握っているのが実数の概念です。以下の例を用いて実数について考える。
下の図のようにx=1から、x=2、次にx=3/2 というように有理数の値を変えてくと、限りなく近づく先の数が有理数の中には無い。しかし、そのように限りなく近づく先の数が存在すると考えた。その数を実数と呼ぶ。

このように、「限りなく近づける」操作(極限の操作)が、数の概念を拡張することを要請し、そうして拡張された新たな数が実数であった。この拡張された数である実数から成るとされる数直線には数の連続性があるとされた。このように極限の操作によって数の概念が実数にまで拡張され、それが数の連続性と微分積分の礎になった。
《数列の極限》
項が限りなく続く数列x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・を無限数列と言う。xnをその第n項といい、この無限数列を{xn}であらわす。また、an を自然数nの式であらわしたものを数列{xn} の一般項という。
「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の定義は、数の集合Aにおいて、以下のことが成り立つこととして、極限を定義する。
【数列の極限の定義】
以下の図で、「数の集合Aの要素で、点a以外の値の、変数xの無限数列{xn}を考える。

この数列{xn}では、自然数nが限りなく大きくなるとき、第n項は限りなく値aに近づく。
一般に、数列{xn}において、nが限りなく大きくなるにつれて、xn が一定の値aに限りなく近づくとき、数列{xn}はaに収束する、または、数列{xn}の極限はaであるという。その値aを数列{xn}の極限値であるという。(点aは数の集合Aの要素で無くても良い)。
数列{xn}の極限値がaであるとき、次のように書く。

すなわち、「変数xが限りなく点aに近づく」という極限の概念を、点aに収束する、数の集合Aの要素のxの無限数列を使って数学的に定義した。
その結果、変数xが限りなく近づく先の点aは、すなわち、変数xの極限の数の点aは、
数の集合Aの要素の点xの無限数列の集積点であるという結論が得られる。
--(集積点の定義)--
実数の集合Rの部分集合の数の集合Aを考える。
(1)実数の点aが数の集合Aの集積点であるとは、
点aの値以外の数の集合Aの要素の点xn による、点aに収束する無限数列 {xn}が存在すること(点aは実数ではあるが、数の集合Aの要素とは限らない)である。
(2)数の集合Aの要素のある数の点yが集積点ではないとき、その点yを数の集合Aの孤立点と呼ぶ。
--(集積点の定義おわり)---
《関数の極限》
関数f(x) の定義域のxの数の集合Aから、aと異なる数x1, x2, x3, ・・・, xn, ・・・ を選んで、点aに収束するxの無限数列{xn}を作った場合に、その無限数列{xn}が点aに収束するのにともなってf(x) が値Cに収束することが、x→aで関数f(x)に極限値Cが存在するための基礎条件である。
関数f(x) において、変数xがaと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくならば、
x→aのときf(x) の極限値がCである。
といい、次のように書く。

また、この場合、”x→aのときf(x) はCに収束する”という。
【関数の極限の定義】
変数xがaと異なる値をとりながら限りなくaに近づくとき、関数f(x) の値が一定の値Cに限りなく近づくという関数の極限は、以下のように定義する。
関数f(x) の定義域の集合Aを区間とする。そして、「変数xが限りなくaに近づくとき関数f(x) に極限値Cが存在する」ことの数学的定義を:
「区間A内の点xの、点aに収束する全ての無限数列{xn}で共通して、関数f(x) が同じ値Cに収束する」ことと定義する。
そう定義する理由は、関数f(x) によっては、点aに収束する各無限数列{xn}毎に、関数f(x) が異なる値Cに収束したり、収束しなかったりすることがあるからである。
【関数の極限の定義の論理的帰結】
(区間Aの内点での極限)関数f(x) が定義される区間Aの内点aでの極限は、右側極限と左側極限との両側で極限値が存在して、両側の極限値が一致することが内点で極限が存在する条件である。(区間Aの内点とは、区間Aの端点以外の、区間内の点のことである)。
xが、内点aの値よりも大きい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのf(x) の右側極限値といい、次のようにあらわす。

xが、内点aの値よりも小さい値をとりながら限りなくaに近づくときf(x) の値が限りなくCに近づくならば、Cを点aでのf(x) の左側極限値といい、次のようにあらわす。

〔極限が存在する条件〕区間Aの内点aでは、極限が存在する条件は、区間A内の点xの、点aに収束するどの無限数列{xn}であっても関数f(x) が同じ値Cに収束することである。そのため、区間A内の点xの、点aより大きい数の無限数列{xn}による右側極限でも値Cに収束する。また、区間A内の点xの、点aより小さい数の無限数列{xn}による左側極限でも同じ値Cに収束する。すなわち、右側極限も存在し、左側極限も存在して、両者の極限値が一致することが内点で極限が存在するために必要十分な条件である。
(区間Aの端点での極限) 関数f(x) が定義される区間Aの端点aでの極限は、区間A内の点xの、点aに収束するどの無限数列{xn}であっても関数f(x) が同じ値Cに収束することである。
▷区間Aの左側の端点aでは、無限数列{xn}は、区間A内の点xの、点aより大きい数の無限数列{xn}による右側極限しか無いので、右側極限値が存在するだけで、端点aで極限値が存在する条件になる。
▷区間Aの右側の端点aでは、無限数列{xn}は、区間A内の点xの、点aより小さい数の無限数列{xn}による左側極限しか無いので、左側極限値が存在するだけで、端点aで極限値が存在する条件になる。
《関数の連続性》
「連続関数とは何か」
https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_93.html
のページが参考になる。
関数の連続性の定義についても、極限の定義と同じで、
関数が定義される区間の内点aでの連続性は、点aの両側極限が一致した上で、かつf(a) と等しくなることが、点aで関数が連続である条件です。
関数が定義される区間の端点aでの連続性は、点aの片側極限が存在した上で、かつf(a) と等しくなることが、点aで関数が連続である条件です。
《関数の微分可能性》
「微分とは何か」
https://schoolhmath.blogspot.com/2024/11/blog-post_6.html
のページが参考になる。
関数の微分可能性の定義についても、極限の定義と同じで、
関数が定義される区間の内点aでの微分可能性は、点aで関数が連続であって、点aの両側での微分係数が一致することが、点aで関数が微分可能である条件です。
関数が定義される区間の端点aでの微分可能性は、点aで関数が連続であって、点aの片側での微分係数が存在することが、点aで関数が微分可能である条件です。
ーー【区間の定義】ーー
「区間」という数学用語は、変数xの数直線上の1つの範囲内の、実数のすき間がない1かたまりの数の集合をあらわす数学用語である。
《神奈川大学》【定義 14.2.4.】
a, b を実数とする. a 以上かつ b 以下の実数をすべて集めた集合を [a, b] と書き, これを閉区 間と呼ぶ.
a より大きくかつ b 未満の実数をすべて集めた集合を (a, b) と書き, これを開区間と呼ぶ.
----定義おわり----
a≦x≦bを満足するxの区間という表現は、a≦x≦bの範囲内の全ての実数xという意味です。
-∞<x<∞という区間もあります。
区間はxの値の範囲を限定するためのa≦x≦bという式とは意味が異なることに注意する必要があります。
(A)「0≦x≦2の区間の変数xで定義された関数f(x)がその区間の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という文では、
f(x)は、0≦x≦2の区間で1つながりに連続した関数f(x)として定義されます。連続関数は、平均値の定理を満足する関数です。。
(B)高校数学での、誤った連続関数の定義
「変数xの0≦x≦2の範囲内の値で関数f(x)が定義されていて、その関数f(x)が定義域の各点で連続であるとき,f(x)は連続関数である」という高校数学の連続関数の定義では、f(x)は、例えば、
0<x<1で f(x)=0, この定義域内の各点で連続。
1<x<2で f(x)=1, この定義域内の各点で連続。
結局、0≦x≦2の範囲内の全ての定義域の各点で連続という関数も連続関数f(x)にされます。しかし、そのように、すき間をはさんだ2つの区間を合わせた複合区間を定義域とする関数は平均値の定理を満足しない。それは連続関数ではなく、その定義は正しい連続関数の定義ではない。
この例の様に、「区間」という用語は変数xの数直線上の、すき間がない1かたまりの実数の集合をあらわす。変数xの数直線上の「区間」では、その変数xの範囲内に実数のすき間があってはいけない。
「区間」という用語は、特に重要な関数である連続関数の連続性を定義するために必要な、連続関数f(x)の変数xの集合体がいつも持っていなければならない連続性という重要な性質が「区間」という概念を用いてあらわされている。
すなわち、変数xの「区間」の性質で大切なのは、
「区間」のなかに変数xの値が隙間なく存在すること。
つまり所定範囲内での隙間が無い1かたまりの実数の集合という概念が「区間」という用語で定義されている。
区間について考えるという事は、その区間内の全ての実数の座標xの点を考えるという事を意味する。すなわち、区間で定義された関数の微分可能性は、変数xの数直線上の実数が隙間なくつまっている区間を基にして定義される概念である。
----------区間の定義終わり-------------
--(連続関数の定義の誤りに注意)---
また、高校で教えている連続関数の定義が間違っていて、それも微分可能の意味を理解できなくする原因になっているので要注意です。
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」で定義されている連続関数の定義のように、大学では、定義域として、実数を完全に含んで連結している1つながりの「区間」の全ての実数のxで定義されている関数f(x)に限って連続関数を定義しています。
「区間Aで定義された関数f(x)がその定義域Aの各点で連続であるとき,f(x)は連続関数であるという」
という表現が正しい連続関数の定義です。
ここで、「区間」という言葉が使われた時点で、それは1つながりの連結区間であって、それは、連続で無い点で分断された領域のことでは無い事に十分に注意する必要があります。
ーー注意のおわり---
関数f(x)であらわされるグラフの傾きは、以下のようにあらわされます。
この傾きは以下に説明する微分によって求めます。
---(定義2.1 「微分積分学入門」(横田 壽)60ページ---
(区間の内点と端点での関数の微分可能の定義)
関数f(x) の変数xの定義域Aが、点x0 を含むある区間A(開区間でも閉区間でも良く、x0は閉区間の端点であっても良い)で定義されているとき,(その区間Aの点x=x0+hでの関数の値f(x0+h) に係わる以下の式の)極限値

(有限の傾きC)が存在するならば,
関数f(x) は, x = x0 で微分可能(differentiable) であるという.
また,この極限値Cを点x0 における微分係数といい,
で表わす.
-----(定義おわり)---------------------------
-----(定義の言い換え)---------------
微分可能の定義を理解するために、以下の様に、自分の言葉で定義を言い換えするのが良いと考えます。
(1)
X0がある区間Aの内点(区間Aの境界点以外の点)の場合は、
x0に近い(例えばx0から微小な値 δ 以内の誤差の)区間A内の全ての実数の値の変数x(ただしx0を除外する)を考える。
(注意1)
微分可能の定義には、x0 と、それ以外の値のxとを考えるという条件が必ず入るので(曲線の傾きを求めるには、必ず異なる2点を使う必要がある)、 x0の近傍の区間Aの全ての実数の点を調べる極限の定義と相性が良いので、極限を使って微分可能を定義している。
また、関数f(x) の定義される区間Aの内点x=x0でのf(x)の微分可能の定義は、点x=x0だけで定義されるのでは無く、x0の点とその近傍の区間Aの点の集合全体を使って、x0の点でのf(x)の微分可能性を定義している。
高校数学で主に教えられている区間Aの内点x0の微分可能性では、内点x0の左右の近傍に区間Aの点の集合が存在する。その左右の片側微分係数が一致することで内点x0 の微分可能性を調べている。
関数f(x)がa≦x≦bの閉区間Aで定義されている場合に、その区間Aの端のx=aとなる端点aは、区間の内点では無いので、その微分可能性は高校数学では教えられていないが、その端点aでも、片側微分係数が存在すれば微分可能である。
(2)
x0の近傍の全ての実数のうちのx0 以外の実数xをどの様に選んでも、点(x,f(x))と点(x0,f(x0))を結んだ線分の傾きが、実数xのどの様な選び方でも、漏れなく、同じ有限の値に収束する(例えば、その全ての傾きの値が、確固として同じ有限の値 Cから微小な値 ε 以内の誤差の値に収まる)ならば、
その確固として同じ有限の値の傾きCが微分係数である。
(3)
また、そのグラフの点を結んだ線分の傾きが一定の、有限の値の傾きCに収束しないならば(無限大の傾きもダメ)、微分不可能である。
(4)
高校数学では、x0 が、関数f(x) が定義される区間の内点の場合の微分可能性だけ例示されている。しかし、x0 が関数f(x) が定義される閉区間の端点の場合も、(定義2.1 で示した大学数学で)微分可能性が定義されている。
大学生になると、微分可能の定義2.1 によって、関数F(x)の端点(x=a)の微分係数をF(x)の片側微分係数で定義する。つまり、関数f(x) の変数xの定義域が、
a≦x≦b
というように定義域が領域の境界点a(端点a)や境界点b(端点b)を含む場合は、
関数f(x) の端点での微分可能性がチェックできる。
これについては、後で、「微分可能の定義の拡張」で説明する。
---------(言い換え終わり)-----------
(補足1)
「微分可能」という言葉は、高校3年の数Ⅲで習うが、高校2年で微分係数を学ぶ時に直ぐ学ぶ方が良いと考える。
なぜなら、微分と積分は、ある変数値で「微分可能」な関数と、ある変数値の近くで「積分可能」な関数を選んで、微分したり積分したりするからです。「微分可能」と「積分可能」という条件が例外的な場合を考えないで良い条件となっていて、その範囲内で考えることで、例外的な場合を考える労力を節約することができるからです。
微分積分の種々の公式の前提条件として、「微分可能」と「積分可能」という条件の範囲内で考えているからです。
そういう前提条件付きで話がされているということを理解して微分積分を学ぶべきだからです。それが教えられないと、微分と積分の話の本当の事情のカヤの外で説明を聞くことになり、微分積分の説明が理解できなくなるからです。
(補足2)
なお、大学数学で学ぶ特殊な関数にδ関数がある。δ関数は超関数と呼ばれる特殊な関数で、(特殊な形の)微分が定義されている。しかし、δ関数は、x=0での値, とx≠0での値が異なり、x=0で連続ではない。すなわち、x=0では連続でないため、その点では、微分可能ではない。
(関数の増減表を書く場合:閉区間の境界での増減)
閉区間で連続な関数の増減は、閉区間の端点での様子は、片側微分で、増加か減少か、片側微分係数が0かが分かります。その片側微分でわかった結果の微分係数を括弧()の中に書いて表現する、 括弧付き表現で解答します。
上の増減表の場合では、括弧()付きの値を表に書かないと、どの様なグラフであるかが分からなくなります。
------微分可能の定義の拡張について--------------------
高校数学では、関数f(x)の定義域の区間の内点のみでの微分可能性が教えられている。そして、内点の両側の片側微分係数が一致することで内点の微分可能性を確認している。それを微分可能性の全ての条件と解釈すると、a≦x≦bという閉区間で定義されている関数f(x) の区間の端点のx=aでは、両側の微分係数が存在しないので、端点x=aでは”微分不可能”という結論になるが、それは正しくない。
大学生以上になると、閉区間の端点での微分可能が以下の様に定義される。
(区間の端での微分可能の定義)
閉区間で定義された関数F(x)=xの区間の端では、定義2.1 で定義されたように、
大学生以上では、片側微分係数が存在すれば、
その片側微分係数を、閉区間の端点での微分係数であるとする、微分可能の正しい定義を学ぶ。(高校生には、微分可能の定義の拡張のように見える)
正しい微分可能の定義では、以下のことが成り立つ。
(関数の連続性については区間の端での連続性が定義されている)
閉区間で連続する連続関数については、定義域の区間の端点以外の内点で関数が連続である。また、閉区間の端点で片側連続であれば、端点を含めた閉区間で関数が連続であるという様に、関数の連続性が定義されている。
関数の微分可能の定義も、同様に微分可能の判別が閉区間の端点でも行える。
特に、閉区間の端点で微分ができないと、以下の問題を生じる。
例えば、変数xが閉区間[a,b]で定義されている関数f(x)を考えます。その関数f(x)を、閉区間[a,x]で積分した関数F(x)-F(a)を作ります。その関数F(x)が閉区間の端点x=aでは微分係数が計算できないとすると、関数F(x)を微分することでは、x=aでは関数f(x)が求められない事になってしまう。そのように関数f(x)とF(x)とが、x=aでは、f(x) の積分ではF(x) が得られても、F(x) の微分ではf(x) が得られないことになり、微分と積分が逆演算にはならない問題を生じる。
大学生以上では、先に定義2.1で示した、正しい微分可能の定義が使われるので、この問題が生じない。
(高校生には拡張されたように見える微分可能の定義)
定義2.1による関数F(x) の微分可能性の定義では分かりにくかったが、閉区間の端でも微分可能性が定義されていることが、大阪大学の教授が書いた「微分積分学」(難波誠)の、44ページに明示されている。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義している」
閉区間a≦x≦bでの端点x=aとx=bでの微分係数が以下の式で定義されている。
(1)端点b=x0におけるf(x) の微分係数は:
h<0について、
で定義される左側微分係数(left-hand derivative )
を端点bの微分係数と定義します。
(2)端点a=x0におけるf(x) の微分係数は:
h>0について、
で定義される右側微分係数(right-hand derivative)
を端点aの微分係数と定義する。
この、閉区間の端点で、片側微分係数が存在すれば、端点でも微分可能とする微分可能の定義は、数学者の藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」の時代からの定義であって確定して受け入れられている定義である。
閉区間で1つながりに連続な関数F(x)を閉区間の端点でも微分可能が定義されていることが、
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」の112ページにも記載されている。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義している」
定義2.1 が表す正しい微分可能の定義「閉区間の端点では、関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」は大学生以上で使われている。
(不定積分との関係)
0≦x≦2という閉区間の定義域でのみ定義され、その定義域内で常にf(x)=1となる関数f(x)を考える。

f(x)の不定積分F(x)の1つは、
F(x)=x
である。
この不定積分F(x)が、閉区間の端でも、この定義の片側微分によりf(0)=1が再現できる。
F(x) がどの点でも微分可能であって、 微分してf(x) が得られるので、この不定積分F(x) =xはf(x) の原始関数である。
この閉区間の端点で微分が定義されるので、連続関数f(x)の不定積分F(x)から逆算してf(x)を計算できるので、
この微分の定義
「端点で関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」
は大学生以上で明確に把握されている。
------微分可能の定義の拡張の考察おわり------------------
【導関数の定義】
関数f(x) が,実数のある区間 I の各点で微分可能(有限の傾きを持つ)のとき
f(x) は区間 I で微分可能(differentiable on I) であるといいます.
この場合,実数の区間 I の各点にそこでの微分係数を対応させることにより定まる関数を
f(x) の導関数(derivative) といい,
であらわします。
また,関数f(x) の導関数を求めることを微分する(differentiate) といいます.
また、xの関数f(x)=yの微分(導関数)を、y’とも書きます。
(補足3)
ここで、以下の関数の微分係数f’(1)を求める場合を考えます。
この極限に使う変数h+1をxにして、以下の様に書いたらどうでしょうか。
この式も、間違いとは言えないと思いますが、
分母の(x-1)=hが正しく導入できずに、分母をxにしてしまうかもしれない、気持ち悪さがあります。
また、この式では無く、x→0の場合に微分を求める場合は、この式の場合に(x-1)=hを正しく導入できないで分母をxにしてしまう、間違った計算ルールを覚えて計算したのか、ルールを間違えていないのかが採点者に判別できない、気持ちの悪さがあります。
そのため、試験問題で微分を極限で求める場合に、hを使わないでxを使うと減点される可能性が高いと考えます。
(接線の定義)
連続なグラフ上に2点A,Bを取って、その2点をその間の1点のCに無限に近づけた時に、その2点A,Bを通る直線が1つの直線に収束する場合に、その直線を、そのグラフの、点Cにおける接線と呼びます。
(注意)グラフの不連続点においては、その点における接線は考え無いことにする。その不連続点に接する直線があるかもしれないが、その点における「接線」については考え無いことにする。
(接線の定義の言い換え)
(1) XY平面上のY=f(x)であらわすグラフの、X=X0となる1点Cにおいて、
微分係数f’(X0)が存在するとき、その点Cを通り、傾きf’(X0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(2) その微分係数f’(X0)が存在しない(無限大になる)場合には:
そのグラフを、YX平面上のX=g(Y)というグラフとみなして考える。そう考えた場合に、
そのグラフ上の1点C(X0,Y0)において、微分係数dx/dY=g’(Y0)が存在するとき(この場合は、g’(Y0)=0になると思うが)、その点Cを通り、YX平面での傾きdX/dY=g’(Y0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(3) 微分係数f’(X0)が存在せず、微分係数g’(Y0)も存在しない場合、その点Cにおける「接線」については考え無いことにする。その点Cでグラフに接する直線はあるかもしれないが、その点における「接線」は考え無いことにする。
(補足4)
「関数が x0 で微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数 x のその値 x0 に限って、その変数 x で微分可能であれば良く、その変数 x のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
(補足5)
df/dx=∞
の場合は、傾きが有限で無いので、
変数xで微分可能ではありません。
df/dx=無限大
という関係が存在しても、
「微分係数(df/dx)が存在しない」
とも言われ、微分不可能です。
それは、
x=0において、
関数f(x)=1/x
の値が無限大という関係が存在しても、
「x=0において関数値1/xが存在しない」
と言うのと同じ意味です。
下図のグラフの関数は、x=0となるO点では傾きが無限大なのでx=0では変数xによる微分係数が存在せず、変数xで微分不可能です。
なお、このグラフは、O点でX=0という直線と接します。
それは、このグラフの座標(変数)を変換して、Y座標値を変数であるとみなし、グラフのX座標値を、関数値とみなせば、グラフの微分係数(dX/dY)=0は存在するので、変数Yによるその微分係数で接線X=0が定められるからです。
すなわち、このグラフのYを与えるxの関数はx=0でYがxで微分不可能ですが、この関数の逆関数の、xを与えるYの関数は、変数としてのYの全ての定義域でxがYで微分可能です。
このように、座標系を回転させる座標変換(変数変換の一種とも言える)によって角度を変えて見ると、ある変数Xでは微分不能であった点が、他の変数Yでは微分可能に変わることがあります。
(注意)
このグラフの関数は、x=0で微分不可能ですが、以下の性質は持っています。
すなわち、
Δx→0の場合にΔy→0となる性質は持っています。
そして、このグラフは、
x1<x2の場合にf(x1)<f(x2)となる、単調増加の性質は持っています。
(注意おわり)
「微分可能」を定めた意味は、ある制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」という制限条件を定めたた本当の理由だと思います。
以下のグラフの関数については:
このグラフには、X=0の点に接する「接線」が存在しませんが、
その「存在しない」の本当の意味は、
X=0においては微分係数が存在しないので、X=0では「接線のことを考えないことにした」のです。
その影響を受けて、このグラフにおける、X=0で接する線については「接線では無い」と言われるようになったのだと思います。
「接線が無い」のでは無く、「微分不可能な点では接線を考えないことにした」だけなのですが、、、
実際、以下のグラフでは、X=0での微分係数が∞になり微分不可能な曲線の点にY軸に平行な接線が接する。
その場合に、その変数Xで微分不可能な点において、「接線が無い」のではなく「接線を考え無いことにした」ことが明らかです。
また、上のグラフは、x=0の点で変数xで微分不可能です。ところがx=0の点で滑らかにつながっています。
微分のごまかし説明で、「微分可能性の定義は、滑らかにグラフがつながる点が微分可能な点である」というごまかし説明が流布されていますが、その定義は間違いですので気をつけてください。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
----(滑らかなグラフと微分可能性との関係)-----
滑らかなグラフと微分可能なグラフは、次の1点のみの差がありますので、その1点のみの差を覚えておきましょう。
滑らかなグラフY=f(x)のうち、傾きdY/dxが無限大になる変数x=x0 の点では、そのグラフの関数f(x)は微分不可能です。それ以外の点では微分可能です。
また、滑らかなグラフでは、その傾きdY/dxが無限大になる点も含む全てのグラフが滑らかに繋がる点で接線が引けます。
----------------------------------------------------
また、Yを変数とした、グラフの、変数Yによる微分係数(dx/dY)は存在し、変数Yによっては微分可能ですが、それが微分可能であっても、変数xによる微分係数(dY/dx)が存在せず、変数xで微分不可能であることに変わりはありません。
(メモ知識)
以下の2つのグラフの関数は、いずれも、x→0の極限で、微分係数(dY/dX)が無限大に発散し、x=0では微分不可能です。

(メモおわり)
【右側微分係数と左側微分係数】
なお、
f(x) がx0 で微分可能でなくても、
h<0について、
または、
h>0について、
が存在することがあります.
下の図のような場合です。
その場合,
最初の値を左側微分係数(left-hand derivative ) と いい,
で表わし,
後の値を右側微分係数(right-hand derivative) といい,
で表わします.
区間で定義された関数f(x) の区間の内点x0 においては,
が共に存在し,かつ両者が等しいとき に限りf(x) は内点x = x0 で微分可能となります。
------------(補足6)--------------------------
しかし、区間を定義域とする関数f(x) の区間の内点x0 では、右側微分係数と左側微分係数が一致しなければ、その点x0 では微分可能では無い(微分係数が存在しない)ということには、以下のような違和感があります。すなわち、区間の内点x0 で、右側微分係数も左側微分係数も存在するのに、両者が一致しないからといって、その点x0 を微分不可能な点と定義して良いのだろうか?と感じる違和感があるのです。
例えば、以下の図のグラフを考えてみます。
このグラフのx=0でのグラフの傾きは2つありますが、そのx=0での点で微分不可能と言うのは不適切だと考えます。なぜなら、そもそも、このグラフは、1つのxの値に対して2つのyの値を対応させている2価関数です。2つのyの値があるので、当然に2つの微分係数があります。その2つの微分係数がたまたま同じ値のyの点で現れたのがx=0の点であるというだけです。また、この2価関数を、xもyも、そして(x,y)の原点からの距離rを角度θの1価の関数と考えると、x=0での2つの傾き(dy/dx)は、θ=π/4の場合と、θ=-π/4の場合と、の2つの異なるθの場合における傾きと考えられます。そういう2つの微分係数が同じ(x,y)の点であらわれるからと言って微分不可能であると言う事はできません。
----補足6おわり----------------------
《関数の連続を前提にした、とある定理》
(とある定理)「ある点での関数の微分可能性を調べる場合に、
その点でその関数が連続である場合は、
微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によっても左側微分係数を求めることができ、
微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によっても右側微分係数を求めることができ、
微分係数の左側極限と微分係数の右側極限によって、微分可能性を調べることができる。」(とある定理おわり)
すなわち、左側微分係数を計算するのが面倒な場合:
x<x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x<x0 の微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によって左側微分係数を求めることもできます。
右側微分係数についても:
x>x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x>x0 の微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によって右側微分係数を求めることもできます。
ただし、関数f(x)がx0 で連続でない場合は、例えば下図のような場合は:
x=x0≡0 の左側微分係数は、-∞ですが、
x<0の関数f(x)のx<0における微分係数f’(x)は1であり、
x→0-
の極限でも、1になりますので、
x0が不連続点である場合に、上の「とある定理」を使うと(定理の適用違反ですが)、
x=x0≡0 の左側微分係数が1であるとしてしまい、
答えを間違えます。
このように、微分するには、先ず、その点で関数が連続であることを調べる確認作業を欠かしてはいけません。その確認の後に、この「とある定理」を使ってください。
(注意)
関数の変数xの値毎に、関数が微分可能か可能でないかが定義されています。
関数f(x)が変数xの値x0において微分可能の場合に、
関数f(x)が初等関数などの通常の関数の場合は、
Δyの誤差が以下の式であらわせます。
----ビッグオー O(Δx2)の 定義--------
ここで、O(Δx2)は、以下のように定義されます。
x=x0+Δxとする絶対値が十分小さいΔxに対して、
ある定数Mがあって、
|Δy-(df/dx)Δx| ≦ MΔxμ
が成り立つとき、
|Δy-(df/dx)Δx|はオーダーμの無限小であると言い、
Δy-(df/dx)Δx=O(Δxμ)とあらわす。
つまり、O(Δx2)は、MのΔx2倍程度の誤差をあらわす誤差関数です。(ΔX=0の場合は、O(0)=0と定義する)
Δxが0に近づくと、誤差O(Δx2)は、Δxよりも更に急速にMのΔx2倍のオーダー(概算値)で0に近づくということをあらわしています。
----(定義おわり)---------------
全ての関数について厳密に成り立つ関係としては:
関数f(x)が変数xのある値xにおいて微分可能であれば、Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差が、MのΔx倍よりも急速に小さくなる誤差関数(スモールオー)で表した以下の式が成り立っています。
スモールオー o(Δx)の定義は、上の極限の式であらわされ、Δxよりも急速に小さくなる誤差関数です。(ΔX=0の場合は、o(0)=0と定義する)
Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差o(Δx)が、MのΔx倍よりも急速に小さくなるので、Δxが十分小さいと考えれば、誤差が十分小さくなり、以下の近似式がいっそう正確に成り立つようになります。
そのため、Δyを上の式であらわして微分を計算して良いです。
【微分不可能が微分可能に変わる例】
(注意1)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがある。
下図のグラフの関数は、O点では傾きが無限大なのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換する、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
という関係があります。
有限の微分係数が存在する(微分可能)という状態は、変数を変換すると変わることがあります。
それは、微分する変数に応じる「微分可能」という条件が、
いわば、
「式を0で割り算する計算をしてはいけない」
という計算の縛りと似た意味を持つことを意味しています。
(注意2)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがあるもう1つの例を考える。
下図のグラフの関数は、O点では、左側微分係数と右側微分係数が異なるのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換すると、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
(注意3)関数の変数を変換すると、接する2つグラフが接さない2つのグラフに変換される例を考える。
下の2つの関数のグラフは、O点で同じ微分係数=0を持ち、O点で接しています。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
(この関数のグラフは、t=0の点での微分係数が無限大になってしまい、t=0では微分可能ではありません)
この変数tで元の2つの関数をあらわすと以下の2つのグラフになります。
元の2つのグラフの変数xを変数tに変換した2つのグラフは、O点で変数tで微分すると異なる微分係数を持ち、O点で接さず交差しています。
変数を変換すると、このように、互いに接する2つのグラフが、接触する点での微分係数が異なる2つのグラフに変わってしまうことがあることに気をつけましょう。
すなわち、「2つの接するグラフが接点において等しい微分係数を持つ」ことが、グラフの座標変換によって変わってしまい2つのグラフの接触点での微分係数が等しく無くなることが有り得ます。
その様なおかしな事が起こる場合は、変数のその値で微分可能では無い関数を使って変数を変換すると生じ得ます。おかしな事が起こらないようにする1つの十分条件として、変数変換に使う関数を、変数のその値で「微分可能」な関数を使えば、変数がその値の部分でのグラフにはおかしな事が起こりません。
「微分可能」は、このようにおかしな事が起こらないようにする十分条件なのです。これが、「微分可能」と「微分不可能」を区別する意味だと考えます。
この「微分可能」によって、自然な直感で想像できる事がどのようにして生じ得るかの答えは、「合成関数の微分の公式」によって明らかにされますので、それまで地道に勉強を進めて欲しいと思います。
(交差している2つのグラフが、変数変換すると互いに接する2つのグラフに変わる例)
上図のように、変数tの関数f(t)とg(t)との2つの関数値をY=f(t)、及びY=g(t)とする。
f(t)=t
g(t)=t/2
とする。 この場合に、上図のように、2つのグラフが、tY座標平面上では互いに交差しているだけで、接していない。
このグラフの変数tを以下のグラフの関数であらわす媒介変数xを考える。
変数tをこのグラフの関数であらわす媒介変数Xを使うと、
XY平面上で先の2つのグラフをあらわすと以下の図の様になる。
x≧0の場合に:
関数f(t)=x2
関数g(t)=x2/2
になる。
この様にXY座標平面上では、互いに接する2つのグラフに変換されてしまった。
すなわち、接さずに単に交差しているだけの2つのグラフが、互い接するグラフに変わってしまった。
(行なって良い変数変換の条件)
tY座標平面上の2つのグラフがある変数値において接するか否かを調べている時に、そのように変わってしまわないようにするための、行なって良い変数tの媒介変数xへの変数変換は、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
(A)
dt/dx ≠ 0
となることが必要です。
(B)
また、その関数が”微分可能”であることも必要で、すなわち、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
dt/dx ≠ ±∞
も必要です。
なお、変数を変換する関数t=m(x)が、
dm(x)/dx≠0となるxの連結区間では、
m(x)は単調増加関数か単調減少関数になります。
その区間の単調増加か単調減少な関数t=m(x)には逆関数x=p(t)が存在します。
特に、
dt/dx ≠ 0,
dt/dx ≠ ±∞,
が成り立つ場合には、
逆関数の微分の公式も成り立ちます。
この2つの条件を満足する関数t=m(x)で変数変換をするならば、グラフの所定の点での「微分可能」または「微分不可能」というグラフの性質が変数変換の後でも同じに維持されます。
例えば、t=m(x)=log(x)という関数は、X=0以外の点では、この2つの条件を満足します。
そのため、この関数t=m(x)を使って変数変換するならば、X=0以外の点では、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
(行なって良い変数変換の使用例)
以下の式1であらわされるグラフを考えます。
Y=xa (式1) (定数 a は所定の実数)
この式1であらわされるグラフは、
グラフが滑らかである大部分の変数値xにおいて、
傾きが∞にならない点で、微分可能です。
この式1のグラフの微分可能性は、以下の様に変数変換して調べることもできます。
この式1を関数log(x)で変換すると、
log(Y)=a*log(X) (式2)
に変換されます。
この式2を
Z=log(Y) (Z>0)
t=log(X) (t>0)
で変数変換すると、
Z=a*t (式3) (ただし、Z>0,t>0)
が得られます。
この式3であらわされるグラフは、元の変数であらわされたグラフと、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
式3のグラフは「微分可能」ですので、元の式1であらわされたグラフも「微分可能」であることがわかります。
(行なって良い変数変換に関する注意)
「微分可能性」の性質を維持する変数変換の条件は、以上で説明した通りですが、その条件を満足していなくても、式を自由に関数で変換して、関数の微分係数の計算式を導きだして良いのです。0を0で割り算するような計算ルールに違反するような計算をせず正しく微分係数の計算式を導き出せれば、その計算式が得られたことが、その関数が「微分可能」であることの証明になります。
ただし、上の条件を満足せずに、微分係数の計算式を導き出せた場合でも、以下の場合には「微分可能」にはなりませんので注意が必要です。
(1)関数f(x)が、x≧x0 と、x<x0 とで異なる式で定義されていて、x<x0 でのf’(x)の、x→x0 における値と、x>x0 でのf’(x)の、x→x0 における値が異なる場合、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ の範囲における微分係数の値が1つに確定しないので、x0 で微分不可能です。
(2)このように、微分可能性を、微分係数の計算式の存在によって判定しようとする場合には、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ において全ての関数値f(x)をしらべることができるか否かをチェックして判定するよう注意してください。
例題2.4
f(x) = xn (n 整数) を微分してみましょう.
となります。
(解答おわり)
が得られました。
次に、以下の微分も計算してみます。
この図形を直線y=xに関して折り返して考えます。
こうして、
が得られました。
(微分の式の前提条件:関数が存在すること)
微分をあらわす式:
(dy/dx)は関数f(x)の導関数をあらわす式です。
そのため、
(dy/dx)=(df(x)/dx)
であり、変数yを微分で使う場合には、
y=f(x)とあらわす関数f(x)が必ず存在することが、変数yを使う前提条件にあります。
関数f(x)が必ず存在するということは、変数xに対して、必ず1つの値のy=f(x)が定まる関係(規則)が、変わらず、存在するということです。
(関数が存在しない例)
以下の関数f(x)で:
(df(x)/dx)=0となっているグラフの部分(y=0の部分)については、以下の逆関数g(y)のグラフの様に:
y=0となっているグラフの部分では、逆関数g(y)が存在しない。 そして、g(y)のy=0での右側極限と左側極限が一致しない。そのため、Δy→0の場合にΔx→0とはならない。
----関数が存在しない例おわり------------------
微分の式は、定まった関数であらわされる関係が必ず存在する変数yとxその他の媒介変数の間の関係をあらわす式です。
微分の計算で使う全ての変数yやxやその他の媒介変数同士は、必ず、その変数を他の変数であらわす不変な関数で結ばれていることが前提にあります。
その関数はどの式であっても良いですが、計算の途中で変化することが無い、いつも変わらない関係式であることが微分の計算の前提になっています。
(微分可能な関数を選んで微分すること)
下図のグラフの関数はでこぼこしていて、でこぼこがあらゆる細部にまで在り、どの有理数のxの位置においても微分不可能な関数の例です。
また、微分不可能な関数F(x)として、連続関数であり、かつ、あらゆるところで微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数F(x)などもあります。
この図の関数のように、関数が微分不可能な変数の値を判定して、変数の範囲(定義域)から除外するために、「微分」の定義を使って関数の変数を選別して、その変数の範囲の関数を微分計算の対象にします。
実際は、微分不可能な関数は、警戒しなければならないほどに多く存在するわけでは無く。数学で学んで来た、ほとんど大部分の初等関数は微分可能な関数です。
また、上のグラフのようf(x)が微分不可能な変数の値(有理数)が無限にある関数f(x)であっても、積分はできます。
(ただし、あらゆるところで微分不可能な関数F(x)については、その関数F(x)を微分した結果の片りんさえも存在しないので、その関数F(x)は何かの関数f(x)の積分では得られません。)
元の関数f(x)が連続関数等の、関数の極限が存在する関数の場合は、その関数f(x)を積分して得た関数F(x)は微分可能な関数になります。こうして、極限が存在する関数f(x)の集合の要素の各関数f(x)を積分して関数F(x)の集合を作れば、その関数の集合の要素の各関数F(x)は、どれも微分可能な関数であることが保証されます。
(「リーマン積分可能」の定義)
「微分積分学入門」(横田 壽)の124ページから125ページに「リーマン積分可能」の定義が書いてあります:
(この本は書店で購入できます。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
ここではドイツの数学者G.F.B. Riemann (1826-1917) によって示されたRiemann 積分につ いて学んでいきます.リーマン積分による「積分可能」の定義は、全ての種類の「積分可能」の定義の基礎になっています。
f(x) は閉区間[a, b] で定義されているとします.この閉区間[a, b] を次のような点xi(i = 1, 2, . . . , n) でn 個の小区間に分割します.
(a = x0 < x1 < x2 < · · · < xi < · · · < xn = b)
この分割をΔ で表わし, Δxi = xi − xi−1 (i = 1, 2, . . . , n) のうちで最も大きい値を|Δ| で 表わします.
いま,それぞれの小区間[xi−1, xi] のなかに任意の点ξi をとり,Riemann 和 (Riemann sum) とよばれる次の和を考えます.
このとき、
となる実数S が存在するならば,このS をf(x) の定積分(definite integral) といい, f(x) は閉区間[a, b] で積分可能(integrable) であるといいます.また,このS を次のように表わします.
つまり関数f(x) が閉区間[a, b] で積分可能であるということは,分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まるということです.
この定義に従い、関数の積分可能性を以下の様にして調べることができます。
先ず小さな閉区間[a, b] を定めて、
その区間の小区間への分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まる(積分可能)か否かを調べることができます。
【積分が不可能な関数】
下のグラフの関数f(x)のように、どの位置においても関数の極限が存在しない関数もあり得ます。
例えば、
xが有理数の場合にf(x)=0であって、
xが無理数の場合のf(x)=1
という、極限が存在しない関数f(x)などです。
そういう、極限が存在しない関数f(x)を積分して関数F(x)を得た場合(もし積分できた場合)、その積分により得られた関数F(x)は微分可能だろうか。
そもそも、微分の計算は極限を求める計算なので、その関数f(x)が積分できても、その積分した関数F(x)を微分した場合に、元の関数f(x)は(極限値が存在しないので)、微分によっては得られないと考えます。
この関数f(x)の変数x=x1からx=x2までの変数xの閉区間をn等分した小区間を作り、その各小区間毎にf(x)の値f(ξ)を求めて、その値の和で積分します。
(1)その際に、 変数x=ξが全て有理数なら、f(ξ)=0になり、積分結果は0になります。
(2)一方、変数x=ξが全て無理数√2の有理数倍なら、f(ξ)=1になり、積分結果は(x2-x1)になります。
(3)小区間内の変数xの点ξの選び方によってf(ξ)の和による積分結果が変わるような計算の値は定かでは無いので、その様な関数f(x)は積分することができません。
なお、以下の関数F(x)は微分可能ですが、それを微分して得た導関数f(x)に不連続点(微分不可能な点)があります。
x≠0の場合:
x=0の場合: F(0)=0,
この関数F(x)はx≠0の場合に微分可能で、
その導関数f(x)は:
になり、xが0に近づくとー1と1の間を振動します。
この導関数が含むcos(1/x)の関数が以下のグラフであらわす形の関数になるからです。
X=0の場合にも、F(x)は微分可能で:
というように、0になります。
そのため、関数F(x)は、全てのxの値で微分可能です。
しかし、関数F(x)の導関数f(x)は、x=0で値f(0)=0を持ちますが、x=0で不連続です。
このF(x)のように、微分すると不連続点を持つ関数f(x)になるが、F(x)自体は、全ての変数値で微分が可能という関数F(x)があるのです。
なお、関数f(x)が変数xのある値で不連続ならば、必ずその点でf(x)は微分不可能になります。これは、「関数が変数xのある値で微分可能ならば、必ずその点で連続である」と言う定理の対偶として成り立っています。
このように、微分積分学では、あらゆる関数に微分積分を行う理論を作ろうとすると、いろいろな難しい問題があることがわかりました。
微分積分学で、難しい問題が生じない関数の範囲を把握して、その範囲内で微分積分の計算をすることで、応用上で微分積分を使い易くできます。
そのため、使い易い関数として、極限が存在し、かつ、変数xの実数のすき間がない1つながりの区間内で連続な「連続関数」 を主に扱う対象にする。また、「微分可能性」で関数の変数の定義域を微分可能な区間に制限する。そのように、扱う関数を制限します。その関数の変数xの区間内で、その関数に関して成り立つ法則を把握して、種々の公式を導き出して使う。そうすることで微分積分学を最大限に応用できるようになります。
(連続関数を使う利点)
変数xが、閉区間の、
a≦x≦b
で連続な連続関数f(x)の関数については、
(関数の連続性については連続性の定義が拡張されている) で説明したように、閉区間の端点での連続性の定義の修正があります。
また、大学生以上で、閉区間での端点での微分可能の定義を修正することで、
関数f(x)が連続な変数xの範囲で、関数f(x)が微分可能にもなり得るという、微分の概念が使い易くされています。
こうして、微分積分学は、微分可能な関数と積分可能な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をします。「微分可能」と「積分可能」という制限条件を定め、その制限条件を満足する関数を扱うのが微分積分学だと認識することがとても大切です。
その様に、「微分可能」の制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」を定義した本当の理由だと思います。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
積分前の関数f(x)と、微分前の関数F(x)との、変数xの一部の定義域での微分積分のあり得る関係が以下の図であらわせます。
(上図で、関数f2(x)は、除去可能な不連続点を除去した関数です。関数F(x)は、関数F(x)の不連続点を除いた変数xの範囲でf(x)の不定積分であるとともに、f2(x)の不定積分でもあります)
「微分可能」な関数と「積分可能」な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をすることが微分積分学の本質です。しかし、その本質を考える礎である一番大切な概念である「微分可能」と「積分可能」を高校2年には教えない。高校3年に至っても「積分可能」の概念を教えていないようです。
しかも、1997年からは、日本の高校の数学IIで面積が無定義に用いられという、数学センスを否定する蛮行が行なわれた。そして、関数f(x)のグラフとx軸で囲まれる領域の面積を,x方向で微分するともとの関数f(x)になり、面積の微分がf(x)となるという本末転倒なことを教えるようになった。
現在の高等学校の教科書は,積分の概念の説明を回避している。
このようなデタラメな教育では、高校生に微分積分が分からないのも無理無いと考えます。
(微分積分の教育方針)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
大学生向けの参考書の、
「微分積分学入門」(横田 壽)
を読んでみることをお勧めします。
(この本は書店で購入できます。)
(しかし、同じ著者の書いた高校生向けの参考書「確実に身につく微分積分(2012年)」の1版は、内容が劣化しているのでお勧めできません。大学生向けの本物の知識の参考書「微分積分学入門(2004年)」を読んでください。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
「微分積分学入門」(横田 壽)の読み方は、 66ページから始まる2章「微分法」の以前のページは斜め読みして、何が書いてあるらしいかを漠然と把握しておいて、2章「微分法」以降を精読することをお勧めします。読んでいるうちに知らない関数や概念が出てきたら、66ページ以前に書いてありますので、探して、その部分を読んで理解するように勉強してください。
《位相空間論での、関数f(x) の微分可能の定義》
関数の微分可能性については、変数xを変数tに変換すると、以下の現象がおきる。
変数変換の関数:
x=g(t)
また、その逆関数:
t=h(x)
が、
dg(t)/dt=0, となる点や、
dh(x)/dx=0, となる点で、
変数がxかtかに依存して、微分可能か微分不可能かの関数の性質が変化することがある。
微分では、関数の独立変数の変換によってそういうことが起きるので、微分を定義するために必要な条件が、関数f(x)を微分する点aは、関数f(x) の定義域の集積点である必要がある。また、微分の定義の根底を支える極限の定義に以下の条件が必要だからである。
《x がaに限りなく近づくことの定義(その1)》
古典的(基礎的)微分積分学においては、x がaに限りなく近づくとは,
点aに収束するxの無限数列が存在して点aが集積点になるということと同じだと考えて良い。
すなわち、aに収束するxの無限数列が存在し、点aがその無限数列の集積点であること。
そして、そのxの値を与える数列の全てのxの値に対して関数f(x) が定義されていること。そして、そのxの数列がaに収束するのにともなって、 f(x) が値Cに収束することが、x→aでf(x)に極限値が存在するための基礎条件である。その基礎条件が、全ての、aに収束するxの無限数列で成り立ち、関数f(x) の値が同じ値のCに収束する場合に、f(x) のaでの極限が存在する。それが、厳密な(第1の)極限の定義である。
《x がaに限りなく近づくことの定義(その2)》
また、古典的(基礎的)微分積分学のもう1つの考え方では、x がaに限りなく近づくとは,
絶対値|x−a| を限りなく小さくできる(そういう条件を満たす値xが存在する)ということと同じだと考えてもよい.
そして, f(x) が値Cに限りなく近づくということも
|f(x) − C| を限りなく小さくできることだと考えてもよい.
そこで,限りなく小さくできるということで考えてみると,以下の様に考えることができる。
xの値がaに近い全ての実数値の場合において、f(x)がf(x0)=Cに近い値になることが、x=aでf(x)に極限値が存在することの厳密な(第2の)定義である。
(微分の定義)
関数f(x) が 定義域xの集積点aで、
∀ε>0,∃δ>0, {0 < |x-a| < δ⇒| ( f(x)-f(a) )/(x-a) - C| <ε}
が成り立つような1つの値の実数 Cが存在するとき、関数f は x = a で微分可能であるという。このとき Cを x=a における 関数f の微分係数といい f'(a) で表す。
リンク:
高校数学の目次
(2)
x0の近傍の全ての実数のうちのx0 以外の実数xをどの様に選んでも、点(x,f(x))と点(x0,f(x0))を結んだ線分の傾きが、実数xのどの様な選び方でも、漏れなく、同じ有限の値に収束する(例えば、その全ての傾きの値が、確固として同じ有限の値 Cから微小な値 ε 以内の誤差の値に収まる)ならば、
その確固として同じ有限の値の傾きCが微分係数である。
(3)
また、そのグラフの点を結んだ線分の傾きが一定の、有限の値の傾きCに収束しないならば(無限大の傾きもダメ)、微分不可能である。
(4)
高校数学では、x0 が、関数f(x) が定義される区間の内点の場合の微分可能性だけ例示されている。しかし、x0 が関数f(x) が定義される閉区間の端点の場合も、(定義2.1 で示した大学数学で)微分可能性が定義されている。
大学生になると、微分可能の定義2.1 によって、関数F(x)の端点(x=a)の微分係数をF(x)の片側微分係数で定義する。つまり、関数f(x) の変数xの定義域が、
a≦x≦b
というように定義域が領域の境界点a(端点a)や境界点b(端点b)を含む場合は、
関数f(x) の端点での微分可能性がチェックできる。
これについては、後で、「微分可能の定義の拡張」で説明する。
---------(言い換え終わり)-----------
(補足1)
「微分可能」という言葉は、高校3年の数Ⅲで習うが、高校2年で微分係数を学ぶ時に直ぐ学ぶ方が良いと考える。
なぜなら、微分と積分は、ある変数値で「微分可能」な関数と、ある変数値の近くで「積分可能」な関数を選んで、微分したり積分したりするからです。「微分可能」と「積分可能」という条件が例外的な場合を考えないで良い条件となっていて、その範囲内で考えることで、例外的な場合を考える労力を節約することができるからです。
微分積分の種々の公式の前提条件として、「微分可能」と「積分可能」という条件の範囲内で考えているからです。
そういう前提条件付きで話がされているということを理解して微分積分を学ぶべきだからです。それが教えられないと、微分と積分の話の本当の事情のカヤの外で説明を聞くことになり、微分積分の説明が理解できなくなるからです。
(補足2)
なお、大学数学で学ぶ特殊な関数にδ関数がある。δ関数は超関数と呼ばれる特殊な関数で、(特殊な形の)微分が定義されている。しかし、δ関数は、x=0での値, とx≠0での値が異なり、x=0で連続ではない。すなわち、x=0では連続でないため、その点では、微分可能ではない。
(関数の増減表を書く場合:閉区間の境界での増減)
閉区間で連続な関数の増減は、閉区間の端点での様子は、片側微分で、増加か減少か、片側微分係数が0かが分かります。その片側微分でわかった結果の微分係数を括弧()の中に書いて表現する、 括弧付き表現で解答します。
------微分可能の定義の拡張について--------------------
高校数学では、関数f(x)の定義域の区間の内点のみでの微分可能性が教えられている。そして、内点の両側の片側微分係数が一致することで内点の微分可能性を確認している。それを微分可能性の全ての条件と解釈すると、a≦x≦bという閉区間で定義されている関数f(x) の区間の端点のx=aでは、両側の微分係数が存在しないので、端点x=aでは”微分不可能”という結論になるが、それは正しくない。
大学生以上になると、閉区間の端点での微分可能が以下の様に定義される。
(区間の端での微分可能の定義)
閉区間で定義された関数F(x)=xの区間の端では、定義2.1 で定義されたように、
大学生以上では、片側微分係数が存在すれば、
その片側微分係数を、閉区間の端点での微分係数であるとする、微分可能の正しい定義を学ぶ。(高校生には、微分可能の定義の拡張のように見える)
正しい微分可能の定義では、以下のことが成り立つ。
(関数の連続性については区間の端での連続性が定義されている)
閉区間で連続する連続関数については、定義域の区間の端点以外の内点で関数が連続である。また、閉区間の端点で片側連続であれば、端点を含めた閉区間で関数が連続であるという様に、関数の連続性が定義されている。
関数の微分可能の定義も、同様に微分可能の判別が閉区間の端点でも行える。
特に、閉区間の端点で微分ができないと、以下の問題を生じる。
例えば、変数xが閉区間[a,b]で定義されている関数f(x)を考えます。その関数f(x)を、閉区間[a,x]で積分した関数F(x)-F(a)を作ります。その関数F(x)が閉区間の端点x=aでは微分係数が計算できないとすると、関数F(x)を微分することでは、x=aでは関数f(x)が求められない事になってしまう。そのように関数f(x)とF(x)とが、x=aでは、f(x) の積分ではF(x) が得られても、F(x) の微分ではf(x) が得られないことになり、微分と積分が逆演算にはならない問題を生じる。
大学生以上では、先に定義2.1で示した、正しい微分可能の定義が使われるので、この問題が生じない。
(高校生には拡張されたように見える微分可能の定義)
定義2.1による関数F(x) の微分可能性の定義では分かりにくかったが、閉区間の端でも微分可能性が定義されていることが、大阪大学の教授が書いた「微分積分学」(難波誠)の、44ページに明示されている。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義している」
閉区間a≦x≦bでの端点x=aとx=bでの微分係数が以下の式で定義されている。
(1)端点b=x0におけるf(x) の微分係数は:
h<0について、
で定義される左側微分係数(left-hand derivative )
を端点bの微分係数と定義します。
(2)端点a=x0におけるf(x) の微分係数は:
h>0について、
で定義される右側微分係数(right-hand derivative)
を端点aの微分係数と定義する。
この、閉区間の端点で、片側微分係数が存在すれば、端点でも微分可能とする微分可能の定義は、数学者の藤原松三郎の「微分積分学 第1巻」の時代からの定義であって確定して受け入れられている定義である。
閉区間で1つながりに連続な関数F(x)を閉区間の端点でも微分可能が定義されていることが、
小平邦彦「[軽装版]解析入門Ⅰ」の112ページにも記載されている。
「閉区間の端点で関数F(x)が片側微分可能であれば、その片側微分を端点での微分係数と定義している」
定義2.1 が表す正しい微分可能の定義「閉区間の端点では、関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」は大学生以上で使われている。
(不定積分との関係)
0≦x≦2という閉区間の定義域でのみ定義され、その定義域内で常にf(x)=1となる関数f(x)を考える。

f(x)の不定積分F(x)の1つは、
F(x)=x
である。
この不定積分F(x)が、閉区間の端でも、この定義の片側微分によりf(0)=1が再現できる。
F(x) がどの点でも微分可能であって、 微分してf(x) が得られるので、この不定積分F(x) =xはf(x) の原始関数である。
この閉区間の端点で微分が定義されるので、連続関数f(x)の不定積分F(x)から逆算してf(x)を計算できるので、
この微分の定義
「端点で関数F(x)の微分を片側微分係数で定義する」
は大学生以上で明確に把握されている。
------微分可能の定義の拡張の考察おわり------------------
【導関数の定義】
関数f(x) が,実数のある区間 I の各点で微分可能(有限の傾きを持つ)のとき
f(x) は区間 I で微分可能(differentiable on I) であるといいます.
この場合,実数の区間 I の各点にそこでの微分係数を対応させることにより定まる関数を
f(x) の導関数(derivative) といい,
であらわします。
また,関数f(x) の導関数を求めることを微分する(differentiate) といいます.
また、xの関数f(x)=yの微分(導関数)を、y’とも書きます。
(補足3)
ここで、以下の関数の微分係数f’(1)を求める場合を考えます。
この極限に使う変数h+1をxにして、以下の様に書いたらどうでしょうか。
この式も、間違いとは言えないと思いますが、
分母の(x-1)=hが正しく導入できずに、分母をxにしてしまうかもしれない、気持ち悪さがあります。
また、この式では無く、x→0の場合に微分を求める場合は、この式の場合に(x-1)=hを正しく導入できないで分母をxにしてしまう、間違った計算ルールを覚えて計算したのか、ルールを間違えていないのかが採点者に判別できない、気持ちの悪さがあります。
そのため、試験問題で微分を極限で求める場合に、hを使わないでxを使うと減点される可能性が高いと考えます。
(接線の定義)
連続なグラフ上に2点A,Bを取って、その2点をその間の1点のCに無限に近づけた時に、その2点A,Bを通る直線が1つの直線に収束する場合に、その直線を、そのグラフの、点Cにおける接線と呼びます。
(注意)グラフの不連続点においては、その点における接線は考え無いことにする。その不連続点に接する直線があるかもしれないが、その点における「接線」については考え無いことにする。
(接線の定義の言い換え)
(1) XY平面上のY=f(x)であらわすグラフの、X=X0となる1点Cにおいて、
微分係数f’(X0)が存在するとき、その点Cを通り、傾きf’(X0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(2) その微分係数f’(X0)が存在しない(無限大になる)場合には:
そのグラフを、YX平面上のX=g(Y)というグラフとみなして考える。そう考えた場合に、
そのグラフ上の1点C(X0,Y0)において、微分係数dx/dY=g’(Y0)が存在するとき(この場合は、g’(Y0)=0になると思うが)、その点Cを通り、YX平面での傾きdX/dY=g’(Y0)を持つ直線が点Cにおける接線である。
(3) 微分係数f’(X0)が存在せず、微分係数g’(Y0)も存在しない場合、その点Cにおける「接線」については考え無いことにする。その点Cでグラフに接する直線はあるかもしれないが、その点における「接線」は考え無いことにする。
(補足4)
「関数が x0 で微分可能(有限の値の確定した値の微分係数が存在する)」
という意味は、
「関数が、その変数 x のその値 x0 に限って、その変数 x で微分可能であれば良く、その変数 x のその他の値での関数の微分可能性は関係しない」
という意味です。
(補足5)
df/dx=∞
の場合は、傾きが有限で無いので、
変数xで微分可能ではありません。
df/dx=無限大
という関係が存在しても、
「微分係数(df/dx)が存在しない」
とも言われ、微分不可能です。
それは、
x=0において、
関数f(x)=1/x
の値が無限大という関係が存在しても、
「x=0において関数値1/xが存在しない」
と言うのと同じ意味です。
下図のグラフの関数は、x=0となるO点では傾きが無限大なのでx=0では変数xによる微分係数が存在せず、変数xで微分不可能です。
なお、このグラフは、O点でX=0という直線と接します。
それは、このグラフの座標(変数)を変換して、Y座標値を変数であるとみなし、グラフのX座標値を、関数値とみなせば、グラフの微分係数(dX/dY)=0は存在するので、変数Yによるその微分係数で接線X=0が定められるからです。
すなわち、このグラフのYを与えるxの関数はx=0でYがxで微分不可能ですが、この関数の逆関数の、xを与えるYの関数は、変数としてのYの全ての定義域でxがYで微分可能です。
このように、座標系を回転させる座標変換(変数変換の一種とも言える)によって角度を変えて見ると、ある変数Xでは微分不能であった点が、他の変数Yでは微分可能に変わることがあります。
(注意)
このグラフの関数は、x=0で微分不可能ですが、以下の性質は持っています。
すなわち、
Δx→0の場合にΔy→0となる性質は持っています。
そして、このグラフは、
x1<x2の場合にf(x1)<f(x2)となる、単調増加の性質は持っています。
(注意おわり)
「微分可能」を定めた意味は、ある制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」という制限条件を定めたた本当の理由だと思います。
以下のグラフの関数については:
このグラフには、X=0の点に接する「接線」が存在しませんが、
その「存在しない」の本当の意味は、
X=0においては微分係数が存在しないので、X=0では「接線のことを考えないことにした」のです。
その影響を受けて、このグラフにおける、X=0で接する線については「接線では無い」と言われるようになったのだと思います。
「接線が無い」のでは無く、「微分不可能な点では接線を考えないことにした」だけなのですが、、、
実際、以下のグラフでは、X=0での微分係数が∞になり微分不可能な曲線の点にY軸に平行な接線が接する。
その場合に、その変数Xで微分不可能な点において、「接線が無い」のではなく「接線を考え無いことにした」ことが明らかです。
また、上のグラフは、x=0の点で変数xで微分不可能です。ところがx=0の点で滑らかにつながっています。
微分のごまかし説明で、「微分可能性の定義は、滑らかにグラフがつながる点が微分可能な点である」というごまかし説明が流布されていますが、その定義は間違いですので気をつけてください。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
----(滑らかなグラフと微分可能性との関係)-----
滑らかなグラフと微分可能なグラフは、次の1点のみの差がありますので、その1点のみの差を覚えておきましょう。
滑らかなグラフY=f(x)のうち、傾きdY/dxが無限大になる変数x=x0 の点では、そのグラフの関数f(x)は微分不可能です。それ以外の点では微分可能です。
また、滑らかなグラフでは、その傾きdY/dxが無限大になる点も含む全てのグラフが滑らかに繋がる点で接線が引けます。
----------------------------------------------------
また、Yを変数とした、グラフの、変数Yによる微分係数(dx/dY)は存在し、変数Yによっては微分可能ですが、それが微分可能であっても、変数xによる微分係数(dY/dx)が存在せず、変数xで微分不可能であることに変わりはありません。
(メモ知識)
以下の2つのグラフの関数は、いずれも、x→0の極限で、微分係数(dY/dX)が無限大に発散し、x=0では微分不可能です。

(メモおわり)
【右側微分係数と左側微分係数】
なお、
f(x) がx0 で微分可能でなくても、
h<0について、
または、
h>0について、
が存在することがあります.
下の図のような場合です。
その場合,
最初の値を左側微分係数(left-hand derivative ) と いい,
で表わし,
後の値を右側微分係数(right-hand derivative) といい,
で表わします.
区間で定義された関数f(x) の区間の内点x0 においては,
が共に存在し,かつ両者が等しいとき に限りf(x) は内点x = x0 で微分可能となります。
------------(補足6)--------------------------
しかし、区間を定義域とする関数f(x) の区間の内点x0 では、右側微分係数と左側微分係数が一致しなければ、その点x0 では微分可能では無い(微分係数が存在しない)ということには、以下のような違和感があります。すなわち、区間の内点x0 で、右側微分係数も左側微分係数も存在するのに、両者が一致しないからといって、その点x0 を微分不可能な点と定義して良いのだろうか?と感じる違和感があるのです。
例えば、以下の図のグラフを考えてみます。
このグラフのx=0でのグラフの傾きは2つありますが、そのx=0での点で微分不可能と言うのは不適切だと考えます。なぜなら、そもそも、このグラフは、1つのxの値に対して2つのyの値を対応させている2価関数です。2つのyの値があるので、当然に2つの微分係数があります。その2つの微分係数がたまたま同じ値のyの点で現れたのがx=0の点であるというだけです。また、この2価関数を、xもyも、そして(x,y)の原点からの距離rを角度θの1価の関数と考えると、x=0での2つの傾き(dy/dx)は、θ=π/4の場合と、θ=-π/4の場合と、の2つの異なるθの場合における傾きと考えられます。そういう2つの微分係数が同じ(x,y)の点であらわれるからと言って微分不可能であると言う事はできません。
----補足6おわり----------------------
《関数の連続を前提にした、とある定理》
(とある定理)「ある点での関数の微分可能性を調べる場合に、
その点でその関数が連続である場合は、
微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によっても左側微分係数を求めることができ、
微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によっても右側微分係数を求めることができ、
微分係数の左側極限と微分係数の右側極限によって、微分可能性を調べることができる。」(とある定理おわり)
すなわち、左側微分係数を計算するのが面倒な場合:
x<x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x<x0 の微分係数の左側極限(真正の極限では無い)によって左側微分係数を求めることもできます。
右側微分係数についても:
x>x0 における微分係数が存在し、しかも関数f(x)がx0で連続な場合は:
と計算でき、x>x0 の微分係数の右側極限(真正の極限では無い)によって右側微分係数を求めることもできます。
ただし、関数f(x)がx0 で連続でない場合は、例えば下図のような場合は:
x=x0≡0 の左側微分係数は、-∞ですが、
x<0の関数f(x)のx<0における微分係数f’(x)は1であり、
x→0-
の極限でも、1になりますので、
x0が不連続点である場合に、上の「とある定理」を使うと(定理の適用違反ですが)、
x=x0≡0 の左側微分係数が1であるとしてしまい、
答えを間違えます。
このように、微分するには、先ず、その点で関数が連続であることを調べる確認作業を欠かしてはいけません。その確認の後に、この「とある定理」を使ってください。
(注意)
関数の変数xの値毎に、関数が微分可能か可能でないかが定義されています。
関数f(x)が変数xの値x0において微分可能の場合に、
関数f(x)が初等関数などの通常の関数の場合は、
Δyの誤差が以下の式であらわせます。
----ビッグオー O(Δx2)の 定義--------
ここで、O(Δx2)は、以下のように定義されます。
x=x0+Δxとする絶対値が十分小さいΔxに対して、
ある定数Mがあって、
|Δy-(df/dx)Δx| ≦ MΔxμ
が成り立つとき、
|Δy-(df/dx)Δx|はオーダーμの無限小であると言い、
Δy-(df/dx)Δx=O(Δxμ)とあらわす。
つまり、O(Δx2)は、MのΔx2倍程度の誤差をあらわす誤差関数です。(ΔX=0の場合は、O(0)=0と定義する)
Δxが0に近づくと、誤差O(Δx2)は、Δxよりも更に急速にMのΔx2倍のオーダー(概算値)で0に近づくということをあらわしています。
----(定義おわり)---------------
全ての関数について厳密に成り立つ関係としては:
関数f(x)が変数xのある値xにおいて微分可能であれば、Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差が、MのΔx倍よりも急速に小さくなる誤差関数(スモールオー)で表した以下の式が成り立っています。
スモールオー o(Δx)の定義は、上の極限の式であらわされ、Δxよりも急速に小さくなる誤差関数です。(ΔX=0の場合は、o(0)=0と定義する)
Δxが小さくなればなる程、Δyの誤差o(Δx)が、MのΔx倍よりも急速に小さくなるので、Δxが十分小さいと考えれば、誤差が十分小さくなり、以下の近似式がいっそう正確に成り立つようになります。
そのため、Δyを上の式であらわして微分を計算して良いです。
【微分不可能が微分可能に変わる例】
(注意1)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがある。
下図のグラフの関数は、O点では傾きが無限大なのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換する、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
という関係があります。
有限の微分係数が存在する(微分可能)という状態は、変数を変換すると変わることがあります。
それは、微分する変数に応じる「微分可能」という条件が、
いわば、
「式を0で割り算する計算をしてはいけない」
という計算の縛りと似た意味を持つことを意味しています。
(注意2)関数の変数を変換すると微分不可能な点が微分可能な点に変わることがあるもう1つの例を考える。
下図のグラフの関数は、O点では、左側微分係数と右側微分係数が異なるのでxで微分不可能です。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
この変数tで元の関数をあらわすと以下のグラフになります。
このグラフはO点で、tで微分可能です。
このように関数の変数を変換すると、変数xでは微分不可能だった関数の点が、変数tでは微分可能になる、ということが起こり得ます。
(注意3)関数の変数を変換すると、接する2つグラフが接さない2つのグラフに変換される例を考える。
下の2つの関数のグラフは、O点で同じ微分係数=0を持ち、O点で接しています。
しかし、変数xを以下のグラフの関係を持つ変数tに変換してみます。
(この関数のグラフは、t=0の点での微分係数が無限大になってしまい、t=0では微分可能ではありません)
この変数tで元の2つの関数をあらわすと以下の2つのグラフになります。
元の2つのグラフの変数xを変数tに変換した2つのグラフは、O点で変数tで微分すると異なる微分係数を持ち、O点で接さず交差しています。
変数を変換すると、このように、互いに接する2つのグラフが、接触する点での微分係数が異なる2つのグラフに変わってしまうことがあることに気をつけましょう。
すなわち、「2つの接するグラフが接点において等しい微分係数を持つ」ことが、グラフの座標変換によって変わってしまい2つのグラフの接触点での微分係数が等しく無くなることが有り得ます。
その様なおかしな事が起こる場合は、変数のその値で微分可能では無い関数を使って変数を変換すると生じ得ます。おかしな事が起こらないようにする1つの十分条件として、変数変換に使う関数を、変数のその値で「微分可能」な関数を使えば、変数がその値の部分でのグラフにはおかしな事が起こりません。
「微分可能」は、このようにおかしな事が起こらないようにする十分条件なのです。これが、「微分可能」と「微分不可能」を区別する意味だと考えます。
この「微分可能」によって、自然な直感で想像できる事がどのようにして生じ得るかの答えは、「合成関数の微分の公式」によって明らかにされますので、それまで地道に勉強を進めて欲しいと思います。
(交差している2つのグラフが、変数変換すると互いに接する2つのグラフに変わる例)
上図のように、変数tの関数f(t)とg(t)との2つの関数値をY=f(t)、及びY=g(t)とする。
f(t)=t
g(t)=t/2
とする。 この場合に、上図のように、2つのグラフが、tY座標平面上では互いに交差しているだけで、接していない。
このグラフの変数tを以下のグラフの関数であらわす媒介変数xを考える。
変数tをこのグラフの関数であらわす媒介変数Xを使うと、
XY平面上で先の2つのグラフをあらわすと以下の図の様になる。
x≧0の場合に:
関数f(t)=x2
関数g(t)=x2/2
になる。
この様にXY座標平面上では、互いに接する2つのグラフに変換されてしまった。
すなわち、接さずに単に交差しているだけの2つのグラフが、互い接するグラフに変わってしまった。
(行なって良い変数変換の条件)
tY座標平面上の2つのグラフがある変数値において接するか否かを調べている時に、そのように変わってしまわないようにするための、行なって良い変数tの媒介変数xへの変数変換は、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
(A)
dt/dx ≠ 0
となることが必要です。
(B)
また、その関数が”微分可能”であることも必要で、すなわち、その2つのグラフが交差する点の位置の変数値において:
dt/dx ≠ ±∞
も必要です。
なお、変数を変換する関数t=m(x)が、
dm(x)/dx≠0となるxの連結区間では、
m(x)は単調増加関数か単調減少関数になります。
その区間の単調増加か単調減少な関数t=m(x)には逆関数x=p(t)が存在します。
特に、
dt/dx ≠ 0,
dt/dx ≠ ±∞,
が成り立つ場合には、
逆関数の微分の公式も成り立ちます。
この2つの条件を満足する関数t=m(x)で変数変換をするならば、グラフの所定の点での「微分可能」または「微分不可能」というグラフの性質が変数変換の後でも同じに維持されます。
例えば、t=m(x)=log(x)という関数は、X=0以外の点では、この2つの条件を満足します。
そのため、この関数t=m(x)を使って変数変換するならば、X=0以外の点では、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
(行なって良い変数変換の使用例)
以下の式1であらわされるグラフを考えます。
Y=xa (式1) (定数 a は所定の実数)
この式1であらわされるグラフは、
グラフが滑らかである大部分の変数値xにおいて、
傾きが∞にならない点で、微分可能です。
この式1のグラフの微分可能性は、以下の様に変数変換して調べることもできます。
この式1を関数log(x)で変換すると、
log(Y)=a*log(X) (式2)
に変換されます。
この式2を
Z=log(Y) (Z>0)
t=log(X) (t>0)
で変数変換すると、
Z=a*t (式3) (ただし、Z>0,t>0)
が得られます。
この式3であらわされるグラフは、元の変数であらわされたグラフと、「微分可能」と「微分不可能」という性質が変わりません。
式3のグラフは「微分可能」ですので、元の式1であらわされたグラフも「微分可能」であることがわかります。
(行なって良い変数変換に関する注意)
「微分可能性」の性質を維持する変数変換の条件は、以上で説明した通りですが、その条件を満足していなくても、式を自由に関数で変換して、関数の微分係数の計算式を導きだして良いのです。0を0で割り算するような計算ルールに違反するような計算をせず正しく微分係数の計算式を導き出せれば、その計算式が得られたことが、その関数が「微分可能」であることの証明になります。
ただし、上の条件を満足せずに、微分係数の計算式を導き出せた場合でも、以下の場合には「微分可能」にはなりませんので注意が必要です。
(1)関数f(x)が、x≧x0 と、x<x0 とで異なる式で定義されていて、x<x0 でのf’(x)の、x→x0 における値と、x>x0 でのf’(x)の、x→x0 における値が異なる場合、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ の範囲における微分係数の値が1つに確定しないので、x0 で微分不可能です。
(2)このように、微分可能性を、微分係数の計算式の存在によって判定しようとする場合には、変数xの範囲のx0 ーδ<x <x0 +δ において全ての関数値f(x)をしらべることができるか否かをチェックして判定するよう注意してください。
例題2.4
f(x) = xn (n 整数) を微分してみましょう.
となります。
(解答おわり)
が得られました。
次に、以下の微分も計算してみます。
この図形を直線y=xに関して折り返して考えます。
こうして、
が得られました。
(微分の式の前提条件:関数が存在すること)
微分をあらわす式:
(dy/dx)は関数f(x)の導関数をあらわす式です。
そのため、
(dy/dx)=(df(x)/dx)
であり、変数yを微分で使う場合には、
y=f(x)とあらわす関数f(x)が必ず存在することが、変数yを使う前提条件にあります。
関数f(x)が必ず存在するということは、変数xに対して、必ず1つの値のy=f(x)が定まる関係(規則)が、変わらず、存在するということです。
(関数が存在しない例)
以下の関数f(x)で:
(df(x)/dx)=0となっているグラフの部分(y=0の部分)については、以下の逆関数g(y)のグラフの様に:
y=0となっているグラフの部分では、逆関数g(y)が存在しない。 そして、g(y)のy=0での右側極限と左側極限が一致しない。そのため、Δy→0の場合にΔx→0とはならない。
----関数が存在しない例おわり------------------
微分の式は、定まった関数であらわされる関係が必ず存在する変数yとxその他の媒介変数の間の関係をあらわす式です。
微分の計算で使う全ての変数yやxやその他の媒介変数同士は、必ず、その変数を他の変数であらわす不変な関数で結ばれていることが前提にあります。
その関数はどの式であっても良いですが、計算の途中で変化することが無い、いつも変わらない関係式であることが微分の計算の前提になっています。
(微分可能な関数を選んで微分すること)
下図のグラフの関数はでこぼこしていて、でこぼこがあらゆる細部にまで在り、どの有理数のxの位置においても微分不可能な関数の例です。
また、微分不可能な関数F(x)として、連続関数であり、かつ、あらゆるところで微分不可能な関数であるワイエルシュトラス関数F(x)などもあります。
この図の関数のように、関数が微分不可能な変数の値を判定して、変数の範囲(定義域)から除外するために、「微分」の定義を使って関数の変数を選別して、その変数の範囲の関数を微分計算の対象にします。
実際は、微分不可能な関数は、警戒しなければならないほどに多く存在するわけでは無く。数学で学んで来た、ほとんど大部分の初等関数は微分可能な関数です。
また、上のグラフのようf(x)が微分不可能な変数の値(有理数)が無限にある関数f(x)であっても、積分はできます。
(ただし、あらゆるところで微分不可能な関数F(x)については、その関数F(x)を微分した結果の片りんさえも存在しないので、その関数F(x)は何かの関数f(x)の積分では得られません。)
元の関数f(x)が連続関数等の、関数の極限が存在する関数の場合は、その関数f(x)を積分して得た関数F(x)は微分可能な関数になります。こうして、極限が存在する関数f(x)の集合の要素の各関数f(x)を積分して関数F(x)の集合を作れば、その関数の集合の要素の各関数F(x)は、どれも微分可能な関数であることが保証されます。
(「リーマン積分可能」の定義)
「微分積分学入門」(横田 壽)の124ページから125ページに「リーマン積分可能」の定義が書いてあります:
(この本は書店で購入できます。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
ここではドイツの数学者G.F.B. Riemann (1826-1917) によって示されたRiemann 積分につ いて学んでいきます.リーマン積分による「積分可能」の定義は、全ての種類の「積分可能」の定義の基礎になっています。
f(x) は閉区間[a, b] で定義されているとします.この閉区間[a, b] を次のような点xi(i = 1, 2, . . . , n) でn 個の小区間に分割します.
(a = x0 < x1 < x2 < · · · < xi < · · · < xn = b)
この分割をΔ で表わし, Δxi = xi − xi−1 (i = 1, 2, . . . , n) のうちで最も大きい値を|Δ| で 表わします.
いま,それぞれの小区間[xi−1, xi] のなかに任意の点ξi をとり,Riemann 和 (Riemann sum) とよばれる次の和を考えます.
このとき、
となる実数S が存在するならば,このS をf(x) の定積分(definite integral) といい, f(x) は閉区間[a, b] で積分可能(integrable) であるといいます.また,このS を次のように表わします.
つまり関数f(x) が閉区間[a, b] で積分可能であるということは,分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まるということです.
この定義に従い、関数の積分可能性を以下の様にして調べることができます。
先ず小さな閉区間[a, b] を定めて、
その区間の小区間への分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まる(積分可能)か否かを調べることができます。
【積分が不可能な関数】
下のグラフの関数f(x)のように、どの位置においても関数の極限が存在しない関数もあり得ます。
例えば、
xが有理数の場合にf(x)=0であって、
xが無理数の場合のf(x)=1
という、極限が存在しない関数f(x)などです。
そういう、極限が存在しない関数f(x)を積分して関数F(x)を得た場合(もし積分できた場合)、その積分により得られた関数F(x)は微分可能だろうか。
そもそも、微分の計算は極限を求める計算なので、その関数f(x)が積分できても、その積分した関数F(x)を微分した場合に、元の関数f(x)は(極限値が存在しないので)、微分によっては得られないと考えます。
この関数f(x)の変数x=x1からx=x2までの変数xの閉区間をn等分した小区間を作り、その各小区間毎にf(x)の値f(ξ)を求めて、その値の和で積分します。
(1)その際に、 変数x=ξが全て有理数なら、f(ξ)=0になり、積分結果は0になります。
(2)一方、変数x=ξが全て無理数√2の有理数倍なら、f(ξ)=1になり、積分結果は(x2-x1)になります。
(3)小区間内の変数xの点ξの選び方によってf(ξ)の和による積分結果が変わるような計算の値は定かでは無いので、その様な関数f(x)は積分することができません。
なお、以下の関数F(x)は微分可能ですが、それを微分して得た導関数f(x)に不連続点(微分不可能な点)があります。
x≠0の場合:
x=0の場合: F(0)=0,
この関数F(x)はx≠0の場合に微分可能で、
その導関数f(x)は:
になり、xが0に近づくとー1と1の間を振動します。
この導関数が含むcos(1/x)の関数が以下のグラフであらわす形の関数になるからです。
X=0の場合にも、F(x)は微分可能で:
というように、0になります。
そのため、関数F(x)は、全てのxの値で微分可能です。
しかし、関数F(x)の導関数f(x)は、x=0で値f(0)=0を持ちますが、x=0で不連続です。
このF(x)のように、微分すると不連続点を持つ関数f(x)になるが、F(x)自体は、全ての変数値で微分が可能という関数F(x)があるのです。
なお、関数f(x)が変数xのある値で不連続ならば、必ずその点でf(x)は微分不可能になります。これは、「関数が変数xのある値で微分可能ならば、必ずその点で連続である」と言う定理の対偶として成り立っています。
このように、微分積分学では、あらゆる関数に微分積分を行う理論を作ろうとすると、いろいろな難しい問題があることがわかりました。
微分積分学で、難しい問題が生じない関数の範囲を把握して、その範囲内で微分積分の計算をすることで、応用上で微分積分を使い易くできます。
そのため、使い易い関数として、極限が存在し、かつ、変数xの実数のすき間がない1つながりの区間内で連続な「連続関数」 を主に扱う対象にする。また、「微分可能性」で関数の変数の定義域を微分可能な区間に制限する。そのように、扱う関数を制限します。その関数の変数xの区間内で、その関数に関して成り立つ法則を把握して、種々の公式を導き出して使う。そうすることで微分積分学を最大限に応用できるようになります。
(連続関数を使う利点)
変数xが、閉区間の、
a≦x≦b
で連続な連続関数f(x)の関数については、
(関数の連続性については連続性の定義が拡張されている) で説明したように、閉区間の端点での連続性の定義の修正があります。
また、大学生以上で、閉区間での端点での微分可能の定義を修正することで、
関数f(x)が連続な変数xの範囲で、関数f(x)が微分可能にもなり得るという、微分の概念が使い易くされています。
こうして、微分積分学は、微分可能な関数と積分可能な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をします。「微分可能」と「積分可能」という制限条件を定め、その制限条件を満足する関数を扱うのが微分積分学だと認識することがとても大切です。
その様に、「微分可能」の制限条件を定めて、その「制限条件」を外れた関数については”考えないこと”にするのが、「微分可能」を定義した本当の理由だと思います。
《下図に各種の関数の集合の包含関係をまとめた》
積分前の関数f(x)と、微分前の関数F(x)との、変数xの一部の定義域での微分積分のあり得る関係が以下の図であらわせます。
(上図で、関数f2(x)は、除去可能な不連続点を除去した関数です。関数F(x)は、関数F(x)の不連続点を除いた変数xの範囲でf(x)の不定積分であるとともに、f2(x)の不定積分でもあります)
「微分可能」な関数と「積分可能」な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をすることが微分積分学の本質です。しかし、その本質を考える礎である一番大切な概念である「微分可能」と「積分可能」を高校2年には教えない。高校3年に至っても「積分可能」の概念を教えていないようです。
しかも、1997年からは、日本の高校の数学IIで面積が無定義に用いられという、数学センスを否定する蛮行が行なわれた。そして、関数f(x)のグラフとx軸で囲まれる領域の面積を,x方向で微分するともとの関数f(x)になり、面積の微分がf(x)となるという本末転倒なことを教えるようになった。
現在の高等学校の教科書は,積分の概念の説明を回避している。
このようなデタラメな教育では、高校生に微分積分が分からないのも無理無いと考えます。
(微分積分の教育方針)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
大学生向けの参考書の、
「微分積分学入門」(横田 壽)
を読んでみることをお勧めします。
(この本は書店で購入できます。)
(しかし、同じ著者の書いた高校生向けの参考書「確実に身につく微分積分(2012年)」の1版は、内容が劣化しているのでお勧めできません。大学生向けの本物の知識の参考書「微分積分学入門(2004年)」を読んでください。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) \2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
「微分積分学入門」(横田 壽)の読み方は、 66ページから始まる2章「微分法」の以前のページは斜め読みして、何が書いてあるらしいかを漠然と把握しておいて、2章「微分法」以降を精読することをお勧めします。読んでいるうちに知らない関数や概念が出てきたら、66ページ以前に書いてありますので、探して、その部分を読んで理解するように勉強してください。
《位相空間論での、関数f(x) の微分可能の定義》
関数の微分可能性については、変数xを変数tに変換すると、以下の現象がおきる。
変数変換の関数:
x=g(t)
また、その逆関数:
t=h(x)
が、
dg(t)/dt=0, となる点や、
dh(x)/dx=0, となる点で、
変数がxかtかに依存して、微分可能か微分不可能かの関数の性質が変化することがある。
微分では、関数の独立変数の変換によってそういうことが起きるので、微分を定義するために必要な条件が、関数f(x)を微分する点aは、関数f(x) の定義域の集積点である必要がある。また、微分の定義の根底を支える極限の定義に以下の条件が必要だからである。
《x がaに限りなく近づくことの定義(その1)》
古典的(基礎的)微分積分学においては、x がaに限りなく近づくとは,
点aに収束するxの無限数列が存在して点aが集積点になるということと同じだと考えて良い。
すなわち、aに収束するxの無限数列が存在し、点aがその無限数列の集積点であること。
そして、そのxの値を与える数列の全てのxの値に対して関数f(x) が定義されていること。そして、そのxの数列がaに収束するのにともなって、 f(x) が値Cに収束することが、x→aでf(x)に極限値が存在するための基礎条件である。その基礎条件が、全ての、aに収束するxの無限数列で成り立ち、関数f(x) の値が同じ値のCに収束する場合に、f(x) のaでの極限が存在する。それが、厳密な(第1の)極限の定義である。
《x がaに限りなく近づくことの定義(その2)》
また、古典的(基礎的)微分積分学のもう1つの考え方では、x がaに限りなく近づくとは,
絶対値|x−a| を限りなく小さくできる(そういう条件を満たす値xが存在する)ということと同じだと考えてもよい.
そして, f(x) が値Cに限りなく近づくということも
|f(x) − C| を限りなく小さくできることだと考えてもよい.
そこで,限りなく小さくできるということで考えてみると,以下の様に考えることができる。
xの値がaに近い全ての実数値の場合において、f(x)がf(x0)=Cに近い値になることが、x=aでf(x)に極限値が存在することの厳密な(第2の)定義である。
(微分の定義)
関数f(x) が 定義域xの集積点aで、
∀ε>0,∃δ>0, {0 < |x-a| < δ⇒| ( f(x)-f(a) )/(x-a) - C| <ε}
が成り立つような1つの値の実数 Cが存在するとき、関数f は x = a で微分可能であるという。このとき Cを x=a における 関数f の微分係数といい f'(a) で表す。
リンク:
高校数学の目次
微分積分はどうすれば勉強できるか
「微分・積分」の勉強
高校の数Ⅱで、微分・積分を学ぶようになり、その勉強がつまらなくなり数学を学ぶのをあきらめて文系に進むことにする学生が多いらしい。そうなる以前に早めに数学がつまらなくなることを見切って早々と文系に進むことに決める学生も多いらしい。
そのため、このページでは、「微分・積分」をどうすればおもしろく勉強できるかというコツを考えます。
(当ブログの結論)
高校2年生が微分積分を学習するのに適切な本は、高校生用の教科書や参考書なのでは無く、大学1年生向けの参考書:例えば:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子)
書評「素晴らしいほどわかりやすい。 高校2年の知識があれば、すらすら読める。 数学苦手な人でも、やさしくシリーズは、微積とベクトルはとっつきやすいと思うので、おすすめです。」
などだと思います。
その本は、初めて微分積分を学ぶ高校2年生にとって、内容がわかり易いです。説明が正確でごまかしが無いので、高校教科書の微分積分の説明にあるようなごまかしが納得できず(ごまかしに納得する方がおかしい)学習が止まってしまう様なことが無く、スムーズに勉強を進めることできるので良いと思います。その本の36ページから45ページまで勉強するだけで、微分の必須知識が学べます。
当ブログでは、先ず、勉強の順番が、
(1)極限
(2)微分
(3)積分
になっている事が、
「微分・積分」の勉強をつまらなくしていると考えます。
数学が好きでいつも数学を勉強している学生は、「微分・積分」の授業の順番には「微分・積分」を学んでいないと考えます。
数学の問題を多く解いていて、数学の問題を解く技術を磨いてきた学生は、「微分・積分」の基礎的な概念は既に考えたことがあり、その概念も利用して問題を解いている。
そして、「微分・積分」の授業に出会ったら、既に知っている自分の知識を整理するために役立てようとして授業を聞くから、「微分・積分」の勉強ができるのだと考えます。
その、既に知っている「微分・積分」の知識とは、どのようなものかを以下で考えます。
数学が好きでいつも数学を勉強している学生は、好奇心を満足させる面白いテーマの順に数学を学んで行くと思います。
面白い数学の課題を見つける都度、その課題を自分で研究するという道草を食います。その道草の1つに、基礎的な「微分・積分」の概念の修得があると思います。
そのため、以下では、その、面白い順に、微分積分を学んでいこうと思います。
(1)積分
(2)微分
(3)極限
の概念の順に学ぶのが面白く、
それを学んだら、
(4)極限の概念の精密化
(5)微分の知識の整理
(6)積分の知識の整理
を勉強するのが、勉強の順番として適切だと考えます。
(1)積分:
以下の問題を考えます。
【問題1】
なぜ、三角錐の体積Vは、
体積V=底面積S×高さh×(1/3)
なのか。
この公式は、何とか覚えられたと思いますが、
もっと、すっきり覚える方法が無いか?
と考えたことがあると思います。
この問題は、以下の様に分析することができます。
この解に法則性があるように思われますが、
この問題は難しいので、これを解くための準備として、
この問題をもっとやさしくした以下の問題を先に解くことにします。
【問題2】
なぜ、三角形の面積Sは、S=底辺L×高さh×(1/2)
なのか。
この問題ならば、上のような場合を考えて、解くためのヒントを見つけることができます。
この問題2で得られたヒントを拡張して、
以下の様に問題1を解析します。
【問題1(再)】
これは、以下のグラフの面積を分割して計算することに対応すると考えることができます。
(この計算で用いた2乗の数列の和の式はここをクリックした先のページにあります)
このように問題を解析することで、後は、この2次関数のグラフの面積を与える法則性を把握すれば、この種の問題が自由に解けるようになることが理解できます。
この様に、分割した要素の総計を求めてグラフの面積を計算する手法が「積分」です。
また、その計算のための法則性を整理して覚えることが「積分」を勉強するということです。
もう1つ、分割した要素の総計を求める例を追加しておきます。
《グラフの微小増分の総和がグラフの高さになる》
上の図のように、グラフの傾きにΔxを掛け算した要素は、グラフの高さの増分Δyです。
上図のように、
グラフの高さの増分Δyの総計=グラフの高さy
になります。
(グラフの微小部分の総和おわり)
(応用例)
分割した要素の総和を考える応用例として、下図の点Aまでの円弧の長さ θ と、長さtanθ の点Tまでの垂直線の長さの大小関係を、
下図の平行線で分割した微小部分の大小関係から求めます。平行線で円弧θを切った部分の長さをΔθと表します。平行線で(1,0)の点から点Tまでの、長さがtanθの垂直な線分を切った部分の長さをΔ(tanθ)と表します。
円弧 θ を平行線で分割した微小ベクトルの平行線への射影成分Pθ の長さよりも、垂直な線分tanθ を平行線で分割した微小ベクトルの平行線への射影成分Pt の長さの方が長い。そのため、円弧θを平行線で分割した微小ベクトルの長さΔθよりも、垂直な線分tanθを平行線で分割した微小ベクトルの長さΔ(tanθ)の方が長い。
その個々の微小ベクトルの長さの総和(積分)を考えることで、
θ <tanθ という大小関係が分かりました。
(応用例おわり)
(積分の特徴)
積分とは、連続した階段を登ることに似ています。
先ず、階段の1歩1歩の段差は有限でなければならない。
無限の段差の階段は登れないので、それは積分できない。
積分は有限の階段でつながっている。
ある点からある点まで積分できたならば、必ず、その点間をつなぐ道が、どこかを通って、通じている。その点をつなぐ道は目前の無限の高さの崖では無いが、他の道が必ずあるのです。
(微分積分学の歴史)
ライプニッツが、1684年に「極大と極小にかんする新しい方法」を出版して、その中で微分法を発表し、
ついで1686年に「深遠な幾何学」を出版して積分法を発表しました。
その後に、ニュートンが微分積分学を発表しました。
それに対して、旧い数学者のバークレー司教(Bishop George Berkeley)が微分積分学を攻撃した論争が微分積分学を正しく育てました。
バークレー司教は、ダブリンのトリニティ・カレッジで神学を学び、後に講義をする。アイルランド、クロインの(英国国教会の)監督Bishopとなる(1734)。
バークレー司教は、数学から唯物論を追放する目的で、『解析者―不誠実な数学者へ向けての論説』(The Analyst: or a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician, 1734)で、ニュートン・ライプニッツ理論(微分積分学)を攻撃し、大論争を引き起こす(『解析教程』第II章第1節参照)。
ド・モアブル、テイラー、マクローリン、ラグランジュ、ヤコブ・ベルヌーイ、ヨハン・ベルヌーイなどが論争に加わり、微積分学の論理的基礎づけに対する関心を高めた功績は大きい。
とくに、マクローリンは反論のためにニュートンの方法の厳密な構成を行った。
以下で、バークレー司教の微分積分学に対する感想を見てみます。
『バークレー司教:解析者より』
「しかし、速度の速度、その速度、そのまた速度、またその速度、またまたその速度などなどというのは、私が間違っているのでなければ、すべての人間の理解を越えてしまっています。
精神がこの捉え難いアイデア(微分積分学)を解析し追及すればするほど、それはまごつき狼狽えることになり.....」
『バークレー司教:解析者より』
「......我が時代の解析者(微分積分学)は有限の量の差を考えるだけでは満足しません。
彼ら(微分積分学)はさらにその差の差を考え、最初の差の差の差を考えます。 そしてさらに無限にまで。
つまり彼ら(微分積分学)は認識できる最小の量よりさらに無限に小さい量を考えます。
その無限に小さい量よりもさらに無限に小さな量を、そしてその上これまでの無限小量よりもさらに無限に小さい量を考え、終わりも限界もないのです。
......もう告白するしかありませんが、無限に小さい量を心に描くことは ......私の能力を超えています。
しかし、そのような無限に小さい量の、それよりさらに無限に小さい一部、だから結局それを無限倍したとしても最も微細な有限の量にまでなることもできない、そんなものを想像するということは、どんな人にとってもそれこそ無限に困難なことだろうと、私は思うのです。.....」
『バークレー司教:解析者より』
「そして、この流率(微分)とは何だろうか?
無限小の増分の速度。 そして、これら同じ無限小の増分の速度とは何なんだろうか?
これらは有限の量でもなく、無限に小さい量でもなく、無でもない。 こんなものなら、過ぎ去った量の幽霊と呼んではいけないというのだろうか? 」
ニュートンとライプニッツの微分は、「無限小」の概念が十分に論理付けされていなかったため、今日のような厳密さが欠けていた。だが、微分は、力学や天文学などで応用可能、しかも実用的であったため、ベルヌーイやロピタル、オイラー、ラグランジュ、ラプラスなどの研究によって普及していった。
微分学が厳密性を伴うようになったのは、19世紀に入ってからである。仏の数学者コーシーは、1821年に発表した「解析教程」で「極限」や「無限小」、「連続関数」の概念を定義し、解析学の基礎を刷新し、その後デデキントやカントールによる実数論などを経て、今日の微分の基礎が完成した。
しかし、この、微分積分が歴史的に持っていたあいまいさとごまかしは、現在の日本の高校の微分積分の教育においては、更にごまかしが拡大されて教えられています。例えば、微分積分学の命綱が「連続関数」の概念ですが、高校数学では間違った定義が教えられています。以下で、その高校教育の実態を見ていきましょう。
連続関数の定義は1817年にBolzanoが中間値の定理を証明する前提条件に連続関数の定義が必要であることを明確にしてから、その定義が定まった。その歴史的経緯から、中間値の定理を成り立たせない関数を連続関数と呼ぶ高校数学での連続関数の定義は偽物である。なお、高校数学で定義された連続関数という言葉が使い物にならないので、大学数学では、連続関数という言葉を使わずに「区間連続」という言葉で本来の意味の連続関数をあらわすことにしています。
【閉区間で連続な関数の最大値・最小値の定理】
閉区間( a≦x≦b)で連続な関数f(x)は、
その区間内で有限の値の最大値と最小値を持つ。
(ここまでが定理)
この定理は、誤った連続関数の定義と異なる、正しい連続関数の定義を前提にした定理です。そのため、この定理は、高校数学では無視することが強いられています。
高校数学では、
y=1/xは、x=0以外の、全ての定義域の点で連続なので「連続関数」と呼ばれています。
また、高校数学では、閉区間( a≦x≦b)とは、変数xの値の範囲を限定する式のことであるという間違いが教えられています。
その誤った知識に基づくと、
【閉区間で連続な関数の最大値・最小値の定理】とは、
変数xの範囲( a≦x≦b)内に関数が連続である定義域を持つ連続関数f(x)は、
その範囲( a≦x≦b)内で有限の値の最大値と最小値を持つ。
(ここまでが定理)
という定理と解釈されます。
この「定理」には以下の反例があります。
関数f(x)=1/xは、
変数xの範囲
-1≦x≦1
内に定義域(ただしx≠0という定義域)が存在し、
-1≦x≦1
内で定義されているどの点でも連続なので、
高校の数Ⅱで、微分・積分を学ぶようになり、その勉強がつまらなくなり数学を学ぶのをあきらめて文系に進むことにする学生が多いらしい。そうなる以前に早めに数学がつまらなくなることを見切って早々と文系に進むことに決める学生も多いらしい。
そのため、このページでは、「微分・積分」をどうすればおもしろく勉強できるかというコツを考えます。
(当ブログの結論)
高校2年生が微分積分を学習するのに適切な本は、高校生用の教科書や参考書なのでは無く、大学1年生向けの参考書:例えば:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子)
書評「素晴らしいほどわかりやすい。 高校2年の知識があれば、すらすら読める。 数学苦手な人でも、やさしくシリーズは、微積とベクトルはとっつきやすいと思うので、おすすめです。」
などだと思います。
その本は、初めて微分積分を学ぶ高校2年生にとって、内容がわかり易いです。説明が正確でごまかしが無いので、高校教科書の微分積分の説明にあるようなごまかしが納得できず(ごまかしに納得する方がおかしい)学習が止まってしまう様なことが無く、スムーズに勉強を進めることできるので良いと思います。その本の36ページから45ページまで勉強するだけで、微分の必須知識が学べます。
当ブログでは、先ず、勉強の順番が、
(1)極限
(2)微分
(3)積分
になっている事が、
「微分・積分」の勉強をつまらなくしていると考えます。
数学が好きでいつも数学を勉強している学生は、「微分・積分」の授業の順番には「微分・積分」を学んでいないと考えます。
数学の問題を多く解いていて、数学の問題を解く技術を磨いてきた学生は、「微分・積分」の基礎的な概念は既に考えたことがあり、その概念も利用して問題を解いている。
そして、「微分・積分」の授業に出会ったら、既に知っている自分の知識を整理するために役立てようとして授業を聞くから、「微分・積分」の勉強ができるのだと考えます。
その、既に知っている「微分・積分」の知識とは、どのようなものかを以下で考えます。
数学が好きでいつも数学を勉強している学生は、好奇心を満足させる面白いテーマの順に数学を学んで行くと思います。
面白い数学の課題を見つける都度、その課題を自分で研究するという道草を食います。その道草の1つに、基礎的な「微分・積分」の概念の修得があると思います。
そのため、以下では、その、面白い順に、微分積分を学んでいこうと思います。
(1)積分
(2)微分
(3)極限
の概念の順に学ぶのが面白く、
それを学んだら、
(4)極限の概念の精密化
(5)微分の知識の整理
(6)積分の知識の整理
を勉強するのが、勉強の順番として適切だと考えます。
(1)積分:
以下の問題を考えます。
【問題1】
なぜ、三角錐の体積Vは、
体積V=底面積S×高さh×(1/3)
なのか。
この公式は、何とか覚えられたと思いますが、
もっと、すっきり覚える方法が無いか?
と考えたことがあると思います。
この問題は、以下の様に分析することができます。
この解に法則性があるように思われますが、
この問題は難しいので、これを解くための準備として、
この問題をもっとやさしくした以下の問題を先に解くことにします。
【問題2】
なぜ、三角形の面積Sは、S=底辺L×高さh×(1/2)
なのか。
この問題ならば、上のような場合を考えて、解くためのヒントを見つけることができます。
この問題2で得られたヒントを拡張して、
以下の様に問題1を解析します。
【問題1(再)】
これは、以下のグラフの面積を分割して計算することに対応すると考えることができます。
(この計算で用いた2乗の数列の和の式はここをクリックした先のページにあります)
このように問題を解析することで、後は、この2次関数のグラフの面積を与える法則性を把握すれば、この種の問題が自由に解けるようになることが理解できます。
この様に、分割した要素の総計を求めてグラフの面積を計算する手法が「積分」です。
また、その計算のための法則性を整理して覚えることが「積分」を勉強するということです。
もう1つ、分割した要素の総計を求める例を追加しておきます。
《グラフの微小増分の総和がグラフの高さになる》
上の図のように、グラフの傾きにΔxを掛け算した要素は、グラフの高さの増分Δyです。
上図のように、
グラフの高さの増分Δyの総計=グラフの高さy
になります。
(グラフの微小部分の総和おわり)
(応用例)
分割した要素の総和を考える応用例として、下図の点Aまでの円弧の長さ θ と、長さtanθ の点Tまでの垂直線の長さの大小関係を、
下図の平行線で分割した微小部分の大小関係から求めます。平行線で円弧θを切った部分の長さをΔθと表します。平行線で(1,0)の点から点Tまでの、長さがtanθの垂直な線分を切った部分の長さをΔ(tanθ)と表します。
その個々の微小ベクトルの長さの総和(積分)を考えることで、
θ <tanθ という大小関係が分かりました。
(応用例おわり)
(積分の特徴)
積分とは、連続した階段を登ることに似ています。
先ず、階段の1歩1歩の段差は有限でなければならない。
無限の段差の階段は登れないので、それは積分できない。
積分は有限の階段でつながっている。
ある点からある点まで積分できたならば、必ず、その点間をつなぐ道が、どこかを通って、通じている。その点をつなぐ道は目前の無限の高さの崖では無いが、他の道が必ずあるのです。
(微分積分学の歴史)
ライプニッツが、1684年に「極大と極小にかんする新しい方法」を出版して、その中で微分法を発表し、
ついで1686年に「深遠な幾何学」を出版して積分法を発表しました。
その後に、ニュートンが微分積分学を発表しました。
それに対して、旧い数学者のバークレー司教(Bishop George Berkeley)が微分積分学を攻撃した論争が微分積分学を正しく育てました。
バークレー司教は、ダブリンのトリニティ・カレッジで神学を学び、後に講義をする。アイルランド、クロインの(英国国教会の)監督Bishopとなる(1734)。
バークレー司教は、数学から唯物論を追放する目的で、『解析者―不誠実な数学者へ向けての論説』(The Analyst: or a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician, 1734)で、ニュートン・ライプニッツ理論(微分積分学)を攻撃し、大論争を引き起こす(『解析教程』第II章第1節参照)。
ド・モアブル、テイラー、マクローリン、ラグランジュ、ヤコブ・ベルヌーイ、ヨハン・ベルヌーイなどが論争に加わり、微積分学の論理的基礎づけに対する関心を高めた功績は大きい。
とくに、マクローリンは反論のためにニュートンの方法の厳密な構成を行った。
以下で、バークレー司教の微分積分学に対する感想を見てみます。
『バークレー司教:解析者より』
「しかし、速度の速度、その速度、そのまた速度、またその速度、またまたその速度などなどというのは、私が間違っているのでなければ、すべての人間の理解を越えてしまっています。
精神がこの捉え難いアイデア(微分積分学)を解析し追及すればするほど、それはまごつき狼狽えることになり.....」
『バークレー司教:解析者より』
「......我が時代の解析者(微分積分学)は有限の量の差を考えるだけでは満足しません。
彼ら(微分積分学)はさらにその差の差を考え、最初の差の差の差を考えます。 そしてさらに無限にまで。
つまり彼ら(微分積分学)は認識できる最小の量よりさらに無限に小さい量を考えます。
その無限に小さい量よりもさらに無限に小さな量を、そしてその上これまでの無限小量よりもさらに無限に小さい量を考え、終わりも限界もないのです。
......もう告白するしかありませんが、無限に小さい量を心に描くことは ......私の能力を超えています。
しかし、そのような無限に小さい量の、それよりさらに無限に小さい一部、だから結局それを無限倍したとしても最も微細な有限の量にまでなることもできない、そんなものを想像するということは、どんな人にとってもそれこそ無限に困難なことだろうと、私は思うのです。.....」
『バークレー司教:解析者より』
「そして、この流率(微分)とは何だろうか?
無限小の増分の速度。 そして、これら同じ無限小の増分の速度とは何なんだろうか?
これらは有限の量でもなく、無限に小さい量でもなく、無でもない。 こんなものなら、過ぎ去った量の幽霊と呼んではいけないというのだろうか? 」
ニュートンとライプニッツの微分は、「無限小」の概念が十分に論理付けされていなかったため、今日のような厳密さが欠けていた。だが、微分は、力学や天文学などで応用可能、しかも実用的であったため、ベルヌーイやロピタル、オイラー、ラグランジュ、ラプラスなどの研究によって普及していった。
微分学が厳密性を伴うようになったのは、19世紀に入ってからである。仏の数学者コーシーは、1821年に発表した「解析教程」で「極限」や「無限小」、「連続関数」の概念を定義し、解析学の基礎を刷新し、その後デデキントやカントールによる実数論などを経て、今日の微分の基礎が完成した。
しかし、この、微分積分が歴史的に持っていたあいまいさとごまかしは、現在の日本の高校の微分積分の教育においては、更にごまかしが拡大されて教えられています。例えば、微分積分学の命綱が「連続関数」の概念ですが、高校数学では間違った定義が教えられています。以下で、その高校教育の実態を見ていきましょう。
連続関数の定義は1817年にBolzanoが中間値の定理を証明する前提条件に連続関数の定義が必要であることを明確にしてから、その定義が定まった。その歴史的経緯から、中間値の定理を成り立たせない関数を連続関数と呼ぶ高校数学での連続関数の定義は偽物である。なお、高校数学で定義された連続関数という言葉が使い物にならないので、大学数学では、連続関数という言葉を使わずに「区間連続」という言葉で本来の意味の連続関数をあらわすことにしています。
【閉区間で連続な関数の最大値・最小値の定理】
閉区間( a≦x≦b)で連続な関数f(x)は、
その区間内で有限の値の最大値と最小値を持つ。
(ここまでが定理)
この定理は、誤った連続関数の定義と異なる、正しい連続関数の定義を前提にした定理です。そのため、この定理は、高校数学では無視することが強いられています。
高校数学では、
y=1/xは、x=0以外の、全ての定義域の点で連続なので「連続関数」と呼ばれています。
また、高校数学では、閉区間( a≦x≦b)とは、変数xの値の範囲を限定する式のことであるという間違いが教えられています。
その誤った知識に基づくと、
【閉区間で連続な関数の最大値・最小値の定理】とは、
変数xの範囲( a≦x≦b)内に関数が連続である定義域を持つ連続関数f(x)は、
その範囲( a≦x≦b)内で有限の値の最大値と最小値を持つ。
(ここまでが定理)
という定理と解釈されます。
この「定理」には以下の反例があります。
関数f(x)=1/xは、
変数xの範囲
-1≦x≦1
内に定義域(ただしx≠0という定義域)が存在し、
-1≦x≦1
内で定義されているどの点でも連続なので、
連続関数です。しかし、この連続関数f(x)は、
x→0の近くで∞と-∞に発散するので、
有限の値の最大値と最小値を持たない。
(反例おわり)
しかし、この定理の基礎となっている正しい連続関数の定義が高校数学での連続関数の定義とは違うので、これは定理の反例にはなっていません。
(補足1)
微分と積分は,歴史的にも,数学的にも,別々に定義される. 独立して定義されたものが,結びついている。 (日本の高校の微分積分の教科書ではいちばん大切な数学の発見が,次代に伝わらない。)
【積分とは何か】
積分については,ここをクリックした先のpdfファイルにある原教授の以下のコメントが大切です。
---(原教授のコメント開始)---------
積分については高校でも習ってはいるが,その基礎を突き詰めていくといろいろと困ったことがでてくる.
特に 「積分は微分の逆演算」として定義すると,「ある関数 f の積分を求めよ」という問題や「この関数の積分は定義できるか?」という問題でハタと困ってしまう.
(微分して f になるような関数がわからない場合,高校までの知識ではお手上げだ.)
この節では高校までの知識はいったん忘れて,「積分とは何か」「積分をどのように定義すべきか」か ら話を始める.
4.1 積分(定積分)の定義
ということで,まずやるべきは「与えられた関数f(x) に対して,その積分を定義すること」である.
これから見ていくように,かなり広いクラスの関数に対してその積分(定積分)を定義することができる.
定積分を通して不定積分も定義できるので,高校までの知識とのつながりがつくことになる.
・・・
積分の最も素朴な定義はこれから紹介する「リーマン和」に基づくもので、、、
---(原教授のコメントおわり)------
(補足2)
(「リーマン積分可能」の定義)
「微分積分学入門」(横田 壽)の124ページから125ページに「リーマン積分可能」の定義が書いてあります:
(この本は書店で購入できます。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) ¥2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
ここではドイツの数学者G.F.B. Riemann (1826-1917) によって示されたRiemann 積分につ いて学んでいきます.リーマン積分による「積分可能」の定義は、全ての種類の「積分可能」の定義の基礎になっています。
f(x) は閉区間[a, b] で定義されているとします.この閉区間[a, b] を次のような点xi(i = 1, 2, . . . , n) でn 個の小区間に分割します.
(a = x0 < x1 < x2 < · · · < xi < · · · < xn = b)
この分割をΔ で表わし, Δxi = xi − xi−1 (i = 1, 2, . . . , n) のうちで最も大きい値を|Δ| で 表わします.
(注目ポイント)
高校数学で教える区分求積法では、区間を細分した部分区間のグラフの高さf(x)を求めますが、そのxの位置が部分区間の中の特定の位置に固定されています。
その固定をしないで、どの位置のxでのf(x)を棒グラフの高さにして計算しても良い、
というのがリーマン積分です。
いま,それぞれの小区間[xi−1, xi] のなかに任意の位置に点ξi をとり,Riemann 和 (Riemann sum) とよばれる次の和を考えます.
このとき、
となる実数S が存在するならば,このS をf(x) の定積分(definite integral) といい, f(x) は閉区間[a, b] で積分可能(integrable) であるといいます.また,このS を次のように表わします.
つまり関数f(x) が閉区間[a, b] で積分可能であるということは,分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まるということです.
この定義に従い、関数の積分可能性を以下の様にして調べることができます。
先ず小さな閉区間[a, b] を定めて、
その区間の小区間への分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まる(積分可能)か否かを調べることができます。
(積分が不可能な関数)
下のグラフの関数f(x)のように、どの位置においても関数の極限が存在しない関数があり得ます。
例えば、
xが有理数の場合にf(x)=0であって、
xが無理数の場合のf(x)=1
という、極限が存在しない関数f(x)などです。
そういう、極限が存在しない関数f(x)を積分して関数F(x)を得た場合(もし積分できた場合)、その積分により得られた関数F(x)は微分可能だろうか。
そもそも、微分の計算は極限を求める計算なので、その関数f(x)が積分できても、その積分した関数F(x)を微分した場合に、元の関数f(x)は(極限値が存在しないので)、微分によっては得られないと考えます。
上図の関数f(x)の変数x=x1からx=x2までの変数xの閉区間をn等分して、その区分した部分毎にf(x)の値f(ξ)を求めて、その値の和で積分します。
(1)その際に、 変数x=ξが全て有理数なら、f(ξ)=0になり、積分結果は0になります。
(2)一方、変数x=ξが全て無理数√2の有理数倍なら、f(ξ)=1になり、積分結果は(x2-x1)になります。
(3)f(x)の値f(ξ)の選び方によって結果が変わるような計算の値は定かでは無いので、その様な関数f(x)は積分することができません。
このように、微分積分学では、あらゆる関数に微分積分を行う理論を作ろうとすると、いろいろな難しい問題があることがわかりました。
微分積分学で、難しい問題が生じない関数の範囲を把握して、その範囲内で微分積分の計算をすることで、応用上で微分積分を使い易くできます。
そのため、使い易い関数として、極限が存在し、かつ、連続な「連続関数」(関数f(x)が連続な範囲にxの定義域を限定した1つながりに連続な関数が連続関数です)を主に扱う対象にし、また、「微分可能性」で関数の種類と、また、関数の変数xの定義域内の所定の範囲を定めて、その所定の範囲内だけで微分積分を行うようにします。その範囲内で成り立つ法則を把握して、種々の公式を導き出して使うことで微分積分学を最大限に応用できるようになります。
微分積分学は、微分可能な関数と積分可能な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をします。
「関数を積分して、それを微分したら元の関数に戻る」
という、微分積分学の基本定理がありますが、
その定理は、その関数f(x)の積分可能な部分に限り、かつ積分後の関数F(x)の微分可能な部分に限って成り立つ定理です。
その定理の大前提に、何が微分可能で何が積分可能であるかの定義があります。
(微分積分学の基本定理を厳密に定義すると、「微分積分学の基本定理」という命題は、積分可能条件を記述した命題です)
(微分可能の定義が微分積分学の基本定理を左右する)
微分積分学の基本定理の根底を支えているのが微分可能の定義です。高校数学の微分可能の定義は、変数xが開区間(a<x<b)で定義された関数f(x)にしか微分可能が定義されていません。そのため、高校数学の範囲内の知識では、開区間(a<x<b)で定義された関数 f(x)にしか、微分積分学の基本定理が成り立ちません。
一方、大学数学では、変数xが閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の区間の端点x=a,bでも微分可能が定義されています。そのため、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)にも微分積分学の基本定理が成り立つと教えられています。
微分積分を学ぶ者は、「微分可能」と「積分可能」という制限条件を定め、その制限条件を満足する関数を扱うのが微分積分学だと認識することがとても大切です。
しかし、この一番大切な概念を高校2年には教えない。高校3年に至っても「積分可能」の概念を教えていないようです。
しかも、1997年からは、日本の高校の数学IIで面積が無定義に用いられという、数学センスを否定する蛮行が行なわれた。そして、関数f(x)のグラフとx軸で囲まれる領域の面積を,x方向で微分するともとの関数f(x)になり、面積の微分がf(x)となるという本末転倒なことを教えるようになった。
高校数学で教える積分の定義が、微分積分学の基本定理が使っている積分の概念と異なるものになった。それにもかかわらず、異なる概念になった「積分」を同じく積分と呼んで定理を記述して紹介しているため、高校でも教える微分積分学の基本定理が意味不明になった。
しかし、「積分」がそのように定義されるという高校の教科書の記述は嘘です。そのため、微分積分学の基本定理の存在意義があります。
そもそも、積分の概念は、日本の高校の教科書が微分の逆演算で定義しているような狭い貧弱な概念ではありません。積分の概念は、数学の研究対象を微小な部分に分割して研究し、その微小部分を集積した全体にまとめ上げて全体を考えるという、適用範囲が広い概念なのです。
「歴史的に見ても、微分より積分の方がずっと前に出現している。」
現在の高等学校の教科書は,積分の概念の説明を回避している。
数学者の吉田洋ーが以下のようになげいています。
“論証"・論証"とやかましくいっておきながら,微積のところへ来ると,とたんにいいかげんな議論でごまかしている。一ーまた高校ではごまかさざるを得ないだろう。高校数学の目的は生徒のあたまを混乱させることにあるのだろうか。
また、初めて不定積分を教わり積分定数Cを教わる際に、積分定数Cの正しい扱いを教わらず高校生の頭が混乱している様です。
高校数学において、積分定数Cを省略した間違った部分積分の公式が教えられています。
また、「従来から、(高校数学での)円弧の面積を使った証明方法は、循環論法であるという指摘はあったが、依然として、教科書の記述が直らないのは、高校数学の七不思議の一つである。」
積分の被積分関数の計算においては、xのある値で0になる関数を分母にする、すなわち、そのxの値で0になる関数で式を割り算する計算が許されています。しかし、(大学で初めて学ぶ)広義積分を知らないと、その計算が何故許されるかが理解できません。
このようなデタラメな教育では、高校生に微分積分が分からないのも無理無いと考えます。
バークレー司教が、これを知ったら、「論外の教育だ」 と酷評すると思います。
(補足3:日本の微分積分の教育)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
とりあえず、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) ¥2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。大学1年生向けの参考書ですが、高校の微分積分の参考書よりも分かり易い。しかも、ごまかしが無く論理が明確なので、初めて微分積分を学ぶ高校2年生が学習につまずくことが無く、一気に読めると思います。
【数学が得意になるということ】
「スタンフォード:本当の答えを見抜く力」(キース・デブリン)
に、スタンフォード大学に入学した大学生に教える「数学移行講座」の教育内容が書かれています。
数学移行講座が必要な理由は、学生が大学の数学教育についていけるようにする基本的考え方を教える必要があるからです。
「数学的能力は2つのタイプに分類できます。
最も必要とされている能力は、2つ目のタイプの能力で、
製造業などで新しい問題に取り組んで、その鍵となる特徴を認識して数学的に記述し、その数学的記述を使って問題を正確に分析することができる能力です。
数学教育では主に1つ目のタイプの人間(公式を覚えて当てはめて定型的な問題の答えを出すことができる)を育てることに力点が置かれてきましたが、結果的に2つ目のタイプの人間も育ちました。
21世紀は、タイプ2の能力に対する需要の方が大きくなっています。
このタイプ2の人材は、
数学の箱の中ではなく、外で考えられる人材です。
「斬新な数学的思考家」と呼ぶのが良さそうです。
微分積分を学ぶ意味は、この「斬新な数学的思考家」になることにあります。
そのため、学生が「タイプ2」になることを妨害している高校生の微分積分の教科書を捨て、
正確に正しい数学を教えている本:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) ¥2000円
等を手に入れて、その本から微分積分を学ぶと良いと考えます。
なお、高校生になった学生は、心身ともに大人として完成する時期に入ったので、もう中学生時代のように受け身で勉強や生きる道を選択するのでは無く、自分から積極的に広く情報を集めて取捨選択して信頼できる情報を手に入れるようにして欲しいと思います。
世間に流通している情報には、誤った情報の方が多く、正しい情報が少ないです。誤った情報しか手に入らないと、誤った情報は問題解決の役に立たないので自信が無くなり、どうしても受け身で勉強する姿勢になり易いです。
正しい情報の貴重さを認識する経験を積んで欲しいと思います。そして、手に入れた正しい情報に基づいた確信と、生きる勇気を手に入れて、人生の永い道に乗り出して行って欲しいと思います。
リンク:
高校数学の目次
新型コロナウイルス感染対策
x→0の近くで∞と-∞に発散するので、
有限の値の最大値と最小値を持たない。
(反例おわり)
しかし、この定理の基礎となっている正しい連続関数の定義が高校数学での連続関数の定義とは違うので、これは定理の反例にはなっていません。
(補足1)
微分と積分は,歴史的にも,数学的にも,別々に定義される. 独立して定義されたものが,結びついている。 (日本の高校の微分積分の教科書ではいちばん大切な数学の発見が,次代に伝わらない。)
【積分とは何か】
積分については,ここをクリックした先のpdfファイルにある原教授の以下のコメントが大切です。
---(原教授のコメント開始)---------
積分については高校でも習ってはいるが,その基礎を突き詰めていくといろいろと困ったことがでてくる.
特に 「積分は微分の逆演算」として定義すると,「ある関数 f の積分を求めよ」という問題や「この関数の積分は定義できるか?」という問題でハタと困ってしまう.
(微分して f になるような関数がわからない場合,高校までの知識ではお手上げだ.)
この節では高校までの知識はいったん忘れて,「積分とは何か」「積分をどのように定義すべきか」か ら話を始める.
4.1 積分(定積分)の定義
ということで,まずやるべきは「与えられた関数f(x) に対して,その積分を定義すること」である.
これから見ていくように,かなり広いクラスの関数に対してその積分(定積分)を定義することができる.
定積分を通して不定積分も定義できるので,高校までの知識とのつながりがつくことになる.
・・・
積分の最も素朴な定義はこれから紹介する「リーマン和」に基づくもので、、、
---(原教授のコメントおわり)------
(補足2)
(「リーマン積分可能」の定義)
「微分積分学入門」(横田 壽)の124ページから125ページに「リーマン積分可能」の定義が書いてあります:
(この本は書店で購入できます。)
その他に、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書は:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) ¥2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。
ここではドイツの数学者G.F.B. Riemann (1826-1917) によって示されたRiemann 積分につ いて学んでいきます.リーマン積分による「積分可能」の定義は、全ての種類の「積分可能」の定義の基礎になっています。
f(x) は閉区間[a, b] で定義されているとします.この閉区間[a, b] を次のような点xi(i = 1, 2, . . . , n) でn 個の小区間に分割します.
(a = x0 < x1 < x2 < · · · < xi < · · · < xn = b)
この分割をΔ で表わし, Δxi = xi − xi−1 (i = 1, 2, . . . , n) のうちで最も大きい値を|Δ| で 表わします.
(注目ポイント)
高校数学で教える区分求積法では、区間を細分した部分区間のグラフの高さf(x)を求めますが、そのxの位置が部分区間の中の特定の位置に固定されています。
その固定をしないで、どの位置のxでのf(x)を棒グラフの高さにして計算しても良い、
というのがリーマン積分です。
いま,それぞれの小区間[xi−1, xi] のなかに任意の位置に点ξi をとり,Riemann 和 (Riemann sum) とよばれる次の和を考えます.
このとき、
となる実数S が存在するならば,このS をf(x) の定積分(definite integral) といい, f(x) は閉区間[a, b] で積分可能(integrable) であるといいます.また,このS を次のように表わします.
つまり関数f(x) が閉区間[a, b] で積分可能であるということは,分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まるということです.
この定義に従い、関数の積分可能性を以下の様にして調べることができます。
先ず小さな閉区間[a, b] を定めて、
その区間の小区間への分割の仕方および点ξi(i = 1, 2, . . . , n) のとり方に関係なく、各点の関数値の和が一通りに定まる(積分可能)か否かを調べることができます。
(積分が不可能な関数)
下のグラフの関数f(x)のように、どの位置においても関数の極限が存在しない関数があり得ます。
例えば、
xが有理数の場合にf(x)=0であって、
xが無理数の場合のf(x)=1
という、極限が存在しない関数f(x)などです。
そういう、極限が存在しない関数f(x)を積分して関数F(x)を得た場合(もし積分できた場合)、その積分により得られた関数F(x)は微分可能だろうか。
そもそも、微分の計算は極限を求める計算なので、その関数f(x)が積分できても、その積分した関数F(x)を微分した場合に、元の関数f(x)は(極限値が存在しないので)、微分によっては得られないと考えます。
上図の関数f(x)の変数x=x1からx=x2までの変数xの閉区間をn等分して、その区分した部分毎にf(x)の値f(ξ)を求めて、その値の和で積分します。
(1)その際に、 変数x=ξが全て有理数なら、f(ξ)=0になり、積分結果は0になります。
(2)一方、変数x=ξが全て無理数√2の有理数倍なら、f(ξ)=1になり、積分結果は(x2-x1)になります。
(3)f(x)の値f(ξ)の選び方によって結果が変わるような計算の値は定かでは無いので、その様な関数f(x)は積分することができません。
このように、微分積分学では、あらゆる関数に微分積分を行う理論を作ろうとすると、いろいろな難しい問題があることがわかりました。
微分積分学で、難しい問題が生じない関数の範囲を把握して、その範囲内で微分積分の計算をすることで、応用上で微分積分を使い易くできます。
そのため、使い易い関数として、極限が存在し、かつ、連続な「連続関数」(関数f(x)が連続な範囲にxの定義域を限定した1つながりに連続な関数が連続関数です)を主に扱う対象にし、また、「微分可能性」で関数の種類と、また、関数の変数xの定義域内の所定の範囲を定めて、その所定の範囲内だけで微分積分を行うようにします。その範囲内で成り立つ法則を把握して、種々の公式を導き出して使うことで微分積分学を最大限に応用できるようになります。
微分積分学は、微分可能な関数と積分可能な関数を定義して、その種の関数の間で微分したり積分をします。
「関数を積分して、それを微分したら元の関数に戻る」
という、微分積分学の基本定理がありますが、
その定理は、その関数f(x)の積分可能な部分に限り、かつ積分後の関数F(x)の微分可能な部分に限って成り立つ定理です。
その定理の大前提に、何が微分可能で何が積分可能であるかの定義があります。
(微分積分学の基本定理を厳密に定義すると、「微分積分学の基本定理」という命題は、積分可能条件を記述した命題です)
(微分可能の定義が微分積分学の基本定理を左右する)
微分積分学の基本定理の根底を支えているのが微分可能の定義です。高校数学の微分可能の定義は、変数xが開区間(a<x<b)で定義された関数f(x)にしか微分可能が定義されていません。そのため、高校数学の範囲内の知識では、開区間(a<x<b)で定義された関数 f(x)にしか、微分積分学の基本定理が成り立ちません。
一方、大学数学では、変数xが閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)の区間の端点x=a,bでも微分可能が定義されています。そのため、大学数学では、閉区間(a≦x≦b)で定義された関数f(x)にも微分積分学の基本定理が成り立つと教えられています。
微分積分を学ぶ者は、「微分可能」と「積分可能」という制限条件を定め、その制限条件を満足する関数を扱うのが微分積分学だと認識することがとても大切です。
しかし、この一番大切な概念を高校2年には教えない。高校3年に至っても「積分可能」の概念を教えていないようです。
しかも、1997年からは、日本の高校の数学IIで面積が無定義に用いられという、数学センスを否定する蛮行が行なわれた。そして、関数f(x)のグラフとx軸で囲まれる領域の面積を,x方向で微分するともとの関数f(x)になり、面積の微分がf(x)となるという本末転倒なことを教えるようになった。
高校数学で教える積分の定義が、微分積分学の基本定理が使っている積分の概念と異なるものになった。それにもかかわらず、異なる概念になった「積分」を同じく積分と呼んで定理を記述して紹介しているため、高校でも教える微分積分学の基本定理が意味不明になった。
しかし、「積分」がそのように定義されるという高校の教科書の記述は嘘です。そのため、微分積分学の基本定理の存在意義があります。
そもそも、積分の概念は、日本の高校の教科書が微分の逆演算で定義しているような狭い貧弱な概念ではありません。積分の概念は、数学の研究対象を微小な部分に分割して研究し、その微小部分を集積した全体にまとめ上げて全体を考えるという、適用範囲が広い概念なのです。
「歴史的に見ても、微分より積分の方がずっと前に出現している。」
現在の高等学校の教科書は,積分の概念の説明を回避している。
数学者の吉田洋ーが以下のようになげいています。
“論証"・論証"とやかましくいっておきながら,微積のところへ来ると,とたんにいいかげんな議論でごまかしている。一ーまた高校ではごまかさざるを得ないだろう。高校数学の目的は生徒のあたまを混乱させることにあるのだろうか。
また、初めて不定積分を教わり積分定数Cを教わる際に、積分定数Cの正しい扱いを教わらず高校生の頭が混乱している様です。
高校数学において、積分定数Cを省略した間違った部分積分の公式が教えられています。
また、「従来から、(高校数学での)円弧の面積を使った証明方法は、循環論法であるという指摘はあったが、依然として、教科書の記述が直らないのは、高校数学の七不思議の一つである。」
積分の被積分関数の計算においては、xのある値で0になる関数を分母にする、すなわち、そのxの値で0になる関数で式を割り算する計算が許されています。しかし、(大学で初めて学ぶ)広義積分を知らないと、その計算が何故許されるかが理解できません。
このようなデタラメな教育では、高校生に微分積分が分からないのも無理無いと考えます。
バークレー司教が、これを知ったら、「論外の教育だ」 と酷評すると思います。
(補足3:日本の微分積分の教育)
ヨーロッパやアメリカでは、「高校で微分積分を教えるのは、直感にうったえる内容に限られ、正確な微分積分を教えられない」という理由で、微分積分は大学生に教える科目になっています。
日本の大学でも、その欧米の教育に合わせて、初めて学ぶ者に分かるように微分積分を改めて教育しているようです。
大学で使う微分積分の参考書は、高校で教える微分積分の知識を全く知らない学生に理解できるように書かれています。
しかも、大学生向けの微分積分の参考書の方が、日本の高校生向けの微分積分の参考書よりやさしく分かり易い。
高校の微分積分を勉強するなら、先ず、大学生向けの微分積分の参考書を読むことを推薦します。高校の微分・積分の教科書は分かりにくいだけで無く、間違いも含まれています。読まない方が良いのではないかと考えます。
とりあえず、高校2年生が勉強するのに適切な、書店で購入できる微分積分の参考書:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) ¥2000円
が内容がわかり易くて良いと思います。大学1年生向けの参考書ですが、高校の微分積分の参考書よりも分かり易い。しかも、ごまかしが無く論理が明確なので、初めて微分積分を学ぶ高校2年生が学習につまずくことが無く、一気に読めると思います。
【数学が得意になるということ】
「スタンフォード:本当の答えを見抜く力」(キース・デブリン)
に、スタンフォード大学に入学した大学生に教える「数学移行講座」の教育内容が書かれています。
数学移行講座が必要な理由は、学生が大学の数学教育についていけるようにする基本的考え方を教える必要があるからです。
「数学的能力は2つのタイプに分類できます。
最も必要とされている能力は、2つ目のタイプの能力で、
製造業などで新しい問題に取り組んで、その鍵となる特徴を認識して数学的に記述し、その数学的記述を使って問題を正確に分析することができる能力です。
数学教育では主に1つ目のタイプの人間(公式を覚えて当てはめて定型的な問題の答えを出すことができる)を育てることに力点が置かれてきましたが、結果的に2つ目のタイプの人間も育ちました。
21世紀は、タイプ2の能力に対する需要の方が大きくなっています。
このタイプ2の人材は、
数学の箱の中ではなく、外で考えられる人材です。
「斬新な数学的思考家」と呼ぶのが良さそうです。
微分積分を学ぶ意味は、この「斬新な数学的思考家」になることにあります。
そのため、学生が「タイプ2」になることを妨害している高校生の微分積分の教科書を捨て、
正確に正しい数学を教えている本:
「やさしく学べる微分積分」(石村園子) ¥2000円
等を手に入れて、その本から微分積分を学ぶと良いと考えます。
なお、高校生になった学生は、心身ともに大人として完成する時期に入ったので、もう中学生時代のように受け身で勉強や生きる道を選択するのでは無く、自分から積極的に広く情報を集めて取捨選択して信頼できる情報を手に入れるようにして欲しいと思います。
世間に流通している情報には、誤った情報の方が多く、正しい情報が少ないです。誤った情報しか手に入らないと、誤った情報は問題解決の役に立たないので自信が無くなり、どうしても受け身で勉強する姿勢になり易いです。
正しい情報の貴重さを認識する経験を積んで欲しいと思います。そして、手に入れた正しい情報に基づいた確信と、生きる勇気を手に入れて、人生の永い道に乗り出して行って欲しいと思います。
リンク:
高校数学の目次
新型コロナウイルス感染対策
ベクトルの公式一覧
ベクトルが体系的に説明されている参考書:
「数学の受験教科書 5 ベクトル」でベクトルを学ぶことができます。
《ベクトルの定義》

点AからBまでの点の座標の複数の成分の移動量の集合をベクトルABと呼ぶ。
また、もっと一般的には、複数の数の集合をベクトルと呼ぶ。
【ベクトルの基本的な公式(1)】
以下の公式のリストが一般的な参考書に書いてある。

【それ以外の基本的公式】
ベクトルa=(a1,a2)
に垂直なベクトルavは
av=(-a2,a1)
で求めることができる。

また、「ベクトルを分解する道を視線でたどって式を書く」のページにある基本的な変換技術がある。

《三角形の重心の公式》

《三角形の内心の公式》

《位置ベクトルの公式》

位置ベクトルの公式は、平面上の位置ベクトルを3つの位置ベクトルの合成であらわす場合に限られず、4つ以上の位置ベクトルの合成であらわす場合にも適用できる(垂心の位置ベクトルを外心の位置ベクトルと頂点の位置ベクトルであらわす場合)。その場合の各位置ベクトルの係数の和も1になる。

内分点の位置は、(内分の比が大きい点から遠くにあり、ベクトルの係数が大きい点に引き込まれる)と覚えれば良い。
2次元ベクトルの分解の公式の要約

三角形の面積比のベクトルの公式

《内点Pからの3つの(大きさが定まった)ベクトルのベクトル方程式(1)から、それらのベクトル同士の内積の値が確定して、三角形の3辺の長さが得られる》

《4つの(大きさが定まった)ベクトルのベクトル方程式(5)によっては、それらのベクトル同士の内積の値が確定しない》

《ベクトルPと単位ベクトルの内積はベクトルPの単位ベクトルへの正射影》
下図のACベクトルが、正射影ベクトルAHに変換されます。

ただし、AHの方向がABの方向と反対の方向を向く場合は、上の式の右辺の項にマイナスが付きます。
〔【基本】ベクトルの内積の性質(ここをクリック)〕
《ベクトルによる三角形の余弦定理のやさしい覚え方》

上図の式のように、ベクトルの内積の使い方は、ベクトルの内積の分配法則を利用して使うのが最も一般的な使い方になります。
《三角形の垂心の位置ベクトル》

(三角形の頂点から垂心までのベクトル)

《ベクトルの内積の和と積の公式》



《中線定理》

《三角形の外心の位置ベクトル》


《外心を原点にした場合の垂心の位置ベクトル》

「ひし形の対角線の直交の公式」”対角線が直交する”
も基本的な公式である。

《ひし形の対角線のベクトル変換の公式》

《2重平行四辺形の面積の公式 》

《単位ベクトルの要素の2乗の差の公式》

「直交するベクトルaとavに関する、任意のベクトルzの合成の公式」
も、基本的な公式である。

《ベクトルの分解の公式》

点Bから線分OAに下した垂線の足HまでのベクトルOHの公式

2等辺三角形の辺ベクトルと底辺ベクトルの内積の公式

線対称ベクトルの公式

《直線の方程式はベクトルの内積の式/点と直線の距離 》
直線の方程式は、下図で、直線ONに垂直な直線上の点Zに係わるベクトルOZの、直線ON上への正射影の長さOHが一定になることをベクトルの内積であらわした式である。

ただし、OHの方向がONの方向と反対の方向を向く場合は、上の式の右辺の項にマイナスが付きます。
《点と直線の距離》


《ベクトルの内積であらわされた2直線の交点》

《ベクトルの長さの比の公式》

BP/BDは、水平線AC上の高さの比である。ベクトル BPとベクトルBAとベクトルBCと水平線の法線ベクトルavとの内積が同じ値である。
《三角形OABの高さベクトルh》


直線上の2点を点Cと点Zとすると、

あと、ベクトルで問題を解こうとするときに問題が解けずに挫折する場合があります。
そのときの裏技として、使うべき以下の公式があります。
「ベクトル計算での挫折を回避する方法」のページの公式

《三角形の高さhの公式の証明の簡単さの差 》



三角形の辺のベクトルa,b,cとそれを90°回転したベクトルav, bv, cvの内積の以下の式が等しい。それは、三角形の面積の2倍になる。


《ベクトルの回転移動と三角関数の加法定理》

《3つの空間ベクトルが同一平面上にある条件 》

《3次元空間で点Cから三角形OABに下した垂線の足H》

《3次元空間の平面の方程式はベクトルの内積の式》

《平面の法線ベクトルh》

《面の法線への射影の利用(9)》

《空間図形の面と直線の交点の求め方》

《ベクトルの外積の演算テクニック》

(演算テクニック)


《べクトルの基本の解説ページへのリンク》
▷ベクトルの一次独立とは何か
▷ベクトルの定義とベクトル方程式の意味
▷ベクトルaに直交するベクトルの作り方
▷ベクトルを分解する道を視線でたどって式を書く
▷空間ベクトルの3つの公式
▷位置ベクトルの公式
▷分点の位置ベクトル(三角形の重心の公式)
▷ベクトル方程式で三角形の内心の位置ベクトルを求める
▷ベクトル方程式によりメネラウスの定理が導ける
▷三角形内の点Pからのベクトルの式と三角形の面積比と点Pの位置
▷ベクトルの交点の公式の解き方のバラエティ
▷空間図形の面と直線の交点を求める解き方のバラエティ
▷ベクトルPと単位ベクトルの内積はベクトルPの単位ベクトルへの正射影
▷ベクトルによる三角形の余弦定理のやさしい覚え方
▷直線の方程式はベクトルの内積の式/点と直線の距離
▷ベクトルの内積(直線の式)
▷ベクトルの内積(点と直線の距離)
▷ベクトルの直線と点との距離及びベクトルの張る三角形の面積
▷三角形の面積をベクトルで表す公式
▷三角形の面積をベクトルで分解して計算する
▷点Bから線分OAに下した垂線の足Hを求める
▷三角形の高さhの公式の証明の簡単さの差
▷三角形の高さベクトルhの公式の要約
▷アポロニウスの円のベクトルでの証明(外サイト)
▷三角形の中線の長さの公式(中線定理)
▷三角形の中線定理のベクトルでの証明
▷三角形の角の2等分線の長さのベクトルでの解答
▷2次元ベクトルの分解の公式の要約
▷2次元ベクトルの合成の公式と分解の公式と2つのベクトルの大きさの積の三平方の定理
▷ベクトルの内積であらわされた2直線の交点
▷余弦定理に類似した公式の多さの解決策はベクトル
▷余弦定理に類似した中線の式と方ベきの定理の解答
▷余弦定理に類似した外心の高さを含む式の解答
▷余弦定理に類似した高さhを含む式の解答
▷単位ベクトルの要素の2乗の差の公式
▷ベクトルの切替の公式
▷ひし形の対角線の直交の公式
▷2重平行四辺形の面積の公式
▷ベクトルの内積の和と積の公式
▷ベクトルの内積の和と積の公式の練習問題
▷直交した基準ベクトルを使って三角形の外心を導く
▷三角形の外接円の中心の位置ベクトルの一番簡単な計算
▷三角形の垂心の位置ベクトルの一番簡単な計算
▷外心を原点にした場合の垂心の位置ベクトル
▷ベクトルの回転移動と三角関数の加法定理
▷ベクトル方程式による極と極線
▷円の外の点Aから引いた円への接線の接点の位置ベクトルの公式を初めて学ぶ方法
▷ベクトル計算での挫折を回避する方法
▷放物線の2つの接線が45°で交わる交点の軌跡
▷3つの空間ベクトルが同一平面上にある条件
▷点Cから三角形OABに下した垂線の足Hを求める
▷(14)3次元ベクトルの外積
▷直角三角錐の面の4平方の定理とベクトルの外積
▷問題をやさしくする数学:ベクトルの外積で面の法線ベクトルを求める(12)
▷立体図形の面の法線ベクトルの求め方のバラエティ
▷3次元ベクトルの分解の公式
▷工夫(4)空間直線の交点Pの計算
▷空間直線の交点の求め方
▷空間図形の面と直線の交点を求める解き方のバラエティ
▷直交ベクトル系を見出して解く問題
リンク:
高校数学の目次
「数学の受験教科書 5 ベクトル」でベクトルを学ぶことができます。
《ベクトルの定義》

点AからBまでの点の座標の複数の成分の移動量の集合をベクトルABと呼ぶ。
また、もっと一般的には、複数の数の集合をベクトルと呼ぶ。
【ベクトルの基本的な公式(1)】
以下の公式のリストが一般的な参考書に書いてある。

【それ以外の基本的公式】
ベクトルa=(a1,a2)
に垂直なベクトルavは
av=(-a2,a1)
で求めることができる。

また、「ベクトルを分解する道を視線でたどって式を書く」のページにある基本的な変換技術がある。

《三角形の重心の公式》

《三角形の内心の公式》

《位置ベクトルの公式》

位置ベクトルの公式は、平面上の位置ベクトルを3つの位置ベクトルの合成であらわす場合に限られず、4つ以上の位置ベクトルの合成であらわす場合にも適用できる(垂心の位置ベクトルを外心の位置ベクトルと頂点の位置ベクトルであらわす場合)。その場合の各位置ベクトルの係数の和も1になる。

内分点の位置は、(内分の比が大きい点から遠くにあり、ベクトルの係数が大きい点に引き込まれる)と覚えれば良い。
2次元ベクトルの分解の公式の要約

三角形の面積比のベクトルの公式

《内点Pからの3つの(大きさが定まった)ベクトルのベクトル方程式(1)から、それらのベクトル同士の内積の値が確定して、三角形の3辺の長さが得られる》

《4つの(大きさが定まった)ベクトルのベクトル方程式(5)によっては、それらのベクトル同士の内積の値が確定しない》

《ベクトルPと単位ベクトルの内積はベクトルPの単位ベクトルへの正射影》
下図のACベクトルが、正射影ベクトルAHに変換されます。

ただし、AHの方向がABの方向と反対の方向を向く場合は、上の式の右辺の項にマイナスが付きます。
〔【基本】ベクトルの内積の性質(ここをクリック)〕
《ベクトルによる三角形の余弦定理のやさしい覚え方》

上図の式のように、ベクトルの内積の使い方は、ベクトルの内積の分配法則を利用して使うのが最も一般的な使い方になります。
《三角形の垂心の位置ベクトル》

(三角形の頂点から垂心までのベクトル)

《ベクトルの内積の和と積の公式》



《中線定理》

《三角形の外心の位置ベクトル》


《外心を原点にした場合の垂心の位置ベクトル》

「ひし形の対角線の直交の公式」”対角線が直交する”
も基本的な公式である。

《ひし形の対角線のベクトル変換の公式》

《2重平行四辺形の面積の公式 》

《単位ベクトルの要素の2乗の差の公式》

「直交するベクトルaとavに関する、任意のベクトルzの合成の公式」
も、基本的な公式である。

《ベクトルの分解の公式》

点Bから線分OAに下した垂線の足HまでのベクトルOHの公式

2等辺三角形の辺ベクトルと底辺ベクトルの内積の公式

線対称ベクトルの公式

《直線の方程式はベクトルの内積の式/点と直線の距離 》
直線の方程式は、下図で、直線ONに垂直な直線上の点Zに係わるベクトルOZの、直線ON上への正射影の長さOHが一定になることをベクトルの内積であらわした式である。

ただし、OHの方向がONの方向と反対の方向を向く場合は、上の式の右辺の項にマイナスが付きます。
《点と直線の距離》


《ベクトルの内積であらわされた2直線の交点》

《ベクトルの長さの比の公式》

BP/BDは、水平線AC上の高さの比である。ベクトル BPとベクトルBAとベクトルBCと水平線の法線ベクトルavとの内積が同じ値である。
《三角形OABの高さベクトルh》


直線上の2点を点Cと点Zとすると、

あと、ベクトルで問題を解こうとするときに問題が解けずに挫折する場合があります。
そのときの裏技として、使うべき以下の公式があります。
「ベクトル計算での挫折を回避する方法」のページの公式

《三角形の高さhの公式の証明の簡単さの差 》



三角形の辺のベクトルa,b,cとそれを90°回転したベクトルav, bv, cvの内積の以下の式が等しい。それは、三角形の面積の2倍になる。


《ベクトルの回転移動と三角関数の加法定理》

《3つの空間ベクトルが同一平面上にある条件 》

《3次元空間で点Cから三角形OABに下した垂線の足H》

《3次元空間の平面の方程式はベクトルの内積の式》

《平面の法線ベクトルh》

《面の法線への射影の利用(9)》

《空間図形の面と直線の交点の求め方》

《ベクトルの外積の演算テクニック》

(演算テクニック)


《べクトルの基本の解説ページへのリンク》
▷ベクトルの一次独立とは何か
▷ベクトルの定義とベクトル方程式の意味
▷ベクトルaに直交するベクトルの作り方
▷ベクトルを分解する道を視線でたどって式を書く
▷空間ベクトルの3つの公式
▷位置ベクトルの公式
▷分点の位置ベクトル(三角形の重心の公式)
▷ベクトル方程式で三角形の内心の位置ベクトルを求める
▷ベクトル方程式によりメネラウスの定理が導ける
▷三角形内の点Pからのベクトルの式と三角形の面積比と点Pの位置
▷ベクトルの交点の公式の解き方のバラエティ
▷空間図形の面と直線の交点を求める解き方のバラエティ
▷ベクトルPと単位ベクトルの内積はベクトルPの単位ベクトルへの正射影
▷ベクトルによる三角形の余弦定理のやさしい覚え方
▷直線の方程式はベクトルの内積の式/点と直線の距離
▷ベクトルの内積(直線の式)
▷ベクトルの内積(点と直線の距離)
▷ベクトルの直線と点との距離及びベクトルの張る三角形の面積
▷三角形の面積をベクトルで表す公式
▷三角形の面積をベクトルで分解して計算する
▷点Bから線分OAに下した垂線の足Hを求める
▷三角形の高さhの公式の証明の簡単さの差
▷三角形の高さベクトルhの公式の要約
▷アポロニウスの円のベクトルでの証明(外サイト)
▷三角形の中線の長さの公式(中線定理)
▷三角形の中線定理のベクトルでの証明
▷三角形の角の2等分線の長さのベクトルでの解答
▷2次元ベクトルの分解の公式の要約
▷2次元ベクトルの合成の公式と分解の公式と2つのベクトルの大きさの積の三平方の定理
▷ベクトルの内積であらわされた2直線の交点
▷余弦定理に類似した公式の多さの解決策はベクトル
▷余弦定理に類似した中線の式と方ベきの定理の解答
▷余弦定理に類似した外心の高さを含む式の解答
▷余弦定理に類似した高さhを含む式の解答
▷単位ベクトルの要素の2乗の差の公式
▷ベクトルの切替の公式
▷ひし形の対角線の直交の公式
▷2重平行四辺形の面積の公式
▷ベクトルの内積の和と積の公式
▷ベクトルの内積の和と積の公式の練習問題
▷直交した基準ベクトルを使って三角形の外心を導く
▷三角形の外接円の中心の位置ベクトルの一番簡単な計算
▷三角形の垂心の位置ベクトルの一番簡単な計算
▷外心を原点にした場合の垂心の位置ベクトル
▷ベクトルの回転移動と三角関数の加法定理
▷ベクトル方程式による極と極線
▷円の外の点Aから引いた円への接線の接点の位置ベクトルの公式を初めて学ぶ方法
▷ベクトル計算での挫折を回避する方法
▷放物線の2つの接線が45°で交わる交点の軌跡
▷3つの空間ベクトルが同一平面上にある条件
▷点Cから三角形OABに下した垂線の足Hを求める
▷(14)3次元ベクトルの外積
▷直角三角錐の面の4平方の定理とベクトルの外積
▷問題をやさしくする数学:ベクトルの外積で面の法線ベクトルを求める(12)
▷立体図形の面の法線ベクトルの求め方のバラエティ
▷3次元ベクトルの分解の公式
▷工夫(4)空間直線の交点Pの計算
▷空間直線の交点の求め方
▷空間図形の面と直線の交点を求める解き方のバラエティ
▷直交ベクトル系を見出して解く問題
リンク:
高校数学の目次